薬機法(旧・薬事法)とは、医薬品や医療機器、化粧品などの品質・有効性・安全性を確保し、消費者を守るために定められた法律です。具体的には、製造や販売、広告表現にいたるまで厳格なルールが設けられ、違反すれば行政指導や課徴金、刑事罰のリスクが生じます。なかでも「どこからが誇大広告に該当するのか」など、境界の判断が難しいケースも多いため注意が必要です。そこで本記事では、薬機法の基本的な仕組みや広告規制のポイントを弁護士がわかりやすく解説し、トラブル回避に役立つ情報をお届けします。まずは薬機法の概要をしっかり理解し、安全かつスムーズな事業運営に役立てましょう。
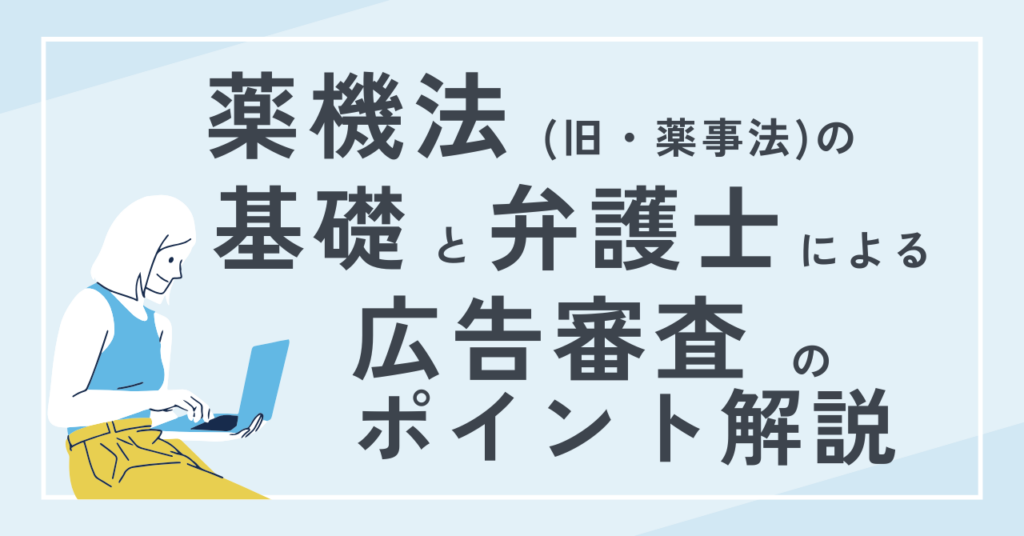
薬機法の目的と規制対象
薬機法(旧・薬事法)の最大の目的は、人々の生命や健康を守るため、医薬品や医療機器、化粧品などの品質・有効性・安全性を確保することにあります。具体的には、医薬品等の製造・販売・流通を適切に管理し、社会全体の保健衛生の向上を図ることを目指しています。また、消費者の誤解や不当な期待を招かないよう、広告や表示の内容についても厳しく規制し、問題発生時には迅速に対応できるよう法整備が行われています。
■薬機法の規制対象
薬機法が規制する主な対象は、以下のとおりです。
- 医薬品
病気の治療・予防・診断に用いられる薬。処方薬から一般用医薬品まで幅広く含まれます。 - 医薬部外品
医薬品ほどの強い作用はないものの、特定の効能を持つと認められている製品(育毛剤、薬用歯みがき粉など)。 - 化粧品
人の外見を美化したり、肌や髪を健やかに保ったりする製品(シャンプー、化粧水など)。 - 医療機器
病気の診断・治療に用いられる機械や器具(人工関節、ペースメーカーなど)。 - 再生医療等製品
細胞加工製品や遺伝子治療用製品など、身体の一部を再生・修復する目的で使われるもの。
これらの製品を扱う事業者や個人は、薬機法の規定を守らないと行政指導や刑事罰、課徴金などのペナルティを科される可能性があります。
薬機法の規制内容(製造・販売・広告規制など)

■製造・販売規制
薬機法では、医薬品や医療機器などを製造・販売する際に、許可や承認を受けることが義務付けられています。具体的には、製造販売業者は製品の品質管理や安全管理を行うための基準(GMP等)を遵守し、適切な製造プロセスを維持しなければなりません。無許可での製造・販売は厳しく処罰されるため、企業側は許認可手続や製造管理体制の整備が不可欠です。
■広告規制
医薬品や医療機器、化粧品などの効能効果を宣伝する際に、誇大広告や虚偽表示が禁じられています。具体的には、「治療効果を保証する」「医師が推奨したかのような誤認を与える」などの表現を行うと薬機法違反に該当し、行政指導や課徴金、刑事罰のリスクが生じます。また、未承認の医薬品等をあたかも有効性が認められているように広告する行為も禁止です。
■取り扱い規制
医薬品や医療機器の販売・流通には、販売できる者や保管・陳列方法などに厳格なルールがあります。たとえば、処方せん医薬品は医師の処方が必要な患者にのみ販売が許可されており、許可なく一般流通させることは違法です。また、表示や添付文書に虚偽の内容を記載することも禁じられており、安全かつ正確な情報を提供する義務が課されています。
薬機法に違反した場合のリスクとペナルティ
薬機法に違反すると、行政指導や業務停止命令などの行政処分から課徴金、さらに刑事罰まで重いペナルティが科されるおそれがあります。
具体的には、広告の中止命令や製品回収、懲役刑・罰金が科されるケースもあり、企業にとっては社会的信用の失墜や経営リスクの増大が不可避です。本章では、薬機法違反に伴う代表的なリスクと各種ペナルティの内容をわかりやすく解説します。違反のリスクを十分に理解し、早期の対策に役立てましょう。
■行政指導・処分(業務停止命令・措置命令など)
薬機法に違反したと認定されると、まずは厚生労働省や都道府県などの行政機関から指摘を受け、必要に応じて業務停止命令や措置命令などの行政処分が下される可能性があります。
たとえば、製造販売業者に対しては一定期間の営業停止が命じられ、同時に問題点の是正や再発防止策の公表を求められることもあります。また、製品の回収や廃棄を指示されるケースもあり、それに伴う追加コストや企業イメージの損失が大きな負担となるでしょう。
行政処分は刑事罰や課徴金より軽い印象を受けがちですが、ビジネスへの影響は深刻なものとなり得るため、早めの対策や専門家への相談が不可欠です。
■課徴金制度の仕組みと金額
課徴金制度は、2021年の薬機法改正で導入された新たな罰則の一つです。
虚偽や誇大広告などの違反行為によって企業が得た不当な利益を回収し、再発を防ぐために設けられました。薬機法の課徴金の金額は「違反期間中の売上高×4.5%」が基本で、一定の条件を満たせば減額や不納付となる場合もあります。
たとえば、発覚前に違反を自己申告した場合は50%の減額が認められることがあるほか、計算した課徴金額が225万円未満であれば課徴金納付は免除される仕組みです。違反行為で得た収益の没収という性格上、企業にとっては経済的打撃が大きく、その結果ブランドイメージの低下や取引先との信頼関係の喪失にもつながる恐れがあります。
■刑事罰の具体例と処罰の対象者
薬機法における刑事罰は、違反の内容が悪質または重大と判断された場合に適用されます。
たとえば、無許可製造・販売を行った企業の代表者や担当者が、3年以下の懲役や300万円以下の罰金刑に処される可能性があります。また、虚偽・誇大広告の禁止に違反すると、2年以下の懲役や200万円以下の罰金刑が科されることも。
さらに法人として違反行為が認められた場合、会社自体も罰金刑の対象となり、社会的信用の失墜につながるリスクが高いです。
一般的に、役職者や実質的な責任者が処罰されるイメージがありますが、場合によっては広告を作成・承認した担当者など、実務レベルの社員が捜査対象になることもあるため、社内でのルール共有やコンプライアンス体制の強化は不可欠です。
●無許可製造・販売の罪
医薬品や医療機器などを製造・販売するには、原則として厚生労働大臣や都道府県知事の許可が必要です。この許可を取得せずに行う行為は、薬機法上「無許可製造・販売の罪」に該当し、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、もしくは併科の対象となります。特に、法人として違反すれば会社自体も罰金刑を科される可能性があり、社会的信用を大きく損ねるリスクがあります。こうした重い処罰を回避するためにも、許認可手続や法的要件を十分に確認することが重要です。
●虚偽・誇大広告の罪
薬機法では、医薬品や医療機器などの広告に関し、虚偽・誇大な表現を行うことを厳しく禁じています。
たとえば「絶対に効く」「医師が推奨」など、根拠が不十分な断定的フレーズを用いた場合、消費者を誤認させる恐れがあるため違反と認定されるリスクが高いです。
もし虚偽・誇大広告が悪質と判断されれば、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその併科といった刑事罰が科されることがあります。また、企業としての組織的な関与が疑われる場合、法人自体も同様の罰金刑を課される可能性があり、社会的信用の喪失という重大なダメージに直結します。
●特定疾病医薬品の広告違反の罪
がんや白血病などの特定疾病向けに使用される医薬品や再生医療等製品については、一般向けに広告することが原則禁止されています。
もしこれに違反する広告を出した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその併科という刑事罰の対象となります。
特に、治療効果や安全性を過度に強調し、不安な患者を誤導するような表現は厳しく追及されるおそれがあります。
企業や広告担当者は、特定疾病医薬品の広告における規制を十分に理解し、適法かつ慎重な情報発信を心がけることが不可欠です。
■薬機法違反で実際に起こりうるリスク
薬機法違反が実際に発生すると、行政処分や刑事罰だけでなく、製品回収や顧客からの返金要求など、経済的なダメージに直結するリスクがあります。
とくに、誇大広告や無許可販売などが報道されると企業イメージが大きく損なわれ、信頼を失った結果、株価の下落や取引先の離脱にまで発展するケースも少なくありません。
さらに、消費者側に健康被害が生じた場合は、損害賠償や集団訴訟など多額の請求が発生するおそれもあります。
医薬品や医療機器といった人体への影響が大きい商材を扱う以上、法令遵守はビジネスの基盤であり、万一トラブルが起きた際には早期に弁護士へ相談することが不可欠です。
薬機法違反と景品表示法違反はどう違う?
薬機法は、医薬品、医療機器、化粧品などの安全性・品質・有効性を確保するための法律であり、製造や販売、広告内容まで幅広く規制します。一方、景品表示法は、主に消費者を誤認させないための表示規制に特化しており、過剰な景品提供や誤解を招く広告表現を取り締まります。
関連記事:薬機法とは?簡単にわかりやすく解説|規制内容・違反事例・対策まとめ
行政から指摘があったら、弁護士にはいつ相談すべき?
行政からの指摘があった段階で、すぐに弁護士にご相談いただくことが最も重要です。早期の対応が、さらなる行政処分や訴訟リスクを回避する鍵となります。
関連記事:薬機法を弁護士に相談するメリットとは?広告チェックから違反対応のポイントを解説
広告チェックを依頼した場合の費用は?
当事務所の広告審査サービスは、A4用紙1枚あたり11,000円(税込)で提供しております。
※webサイトの場合は印刷した場合の枚数
明確な料金設定のもと、丁寧なリーガルチェックを実施し、リスクの低減に貢献します。
>>広告審査のサポートのご紹介はこちら
薬機法違反となった際に弁護士が必要な理由とメリット
■行政指導・捜査への迅速な対応が可能
行政から薬機法違反の指摘や調査が入った場合、企業単独での対応では時間がかかったり、誤った受け答えをしてしまうリスクがあります。しかし薬機法に精通した弁護士を立てれば、法的根拠に基づく説得力のある意見書を作成し、交渉や捜査機関への対応をスムーズに進めることが可能です。結果として、行政からの評価も改善されやすく、事態の早期収束や企業イメージの保護にもつながります。
■医療・ヘルスケア分野への高い専門性
医薬品や医療機器、化粧品、健康食品など、人体に関わる製品やサービスを扱う医療・ヘルスケア分野では、専門的な法的知識だけでなく、業界の最新動向やガイドラインを理解することが不可欠です。薬機法をはじめとした関連法令が複雑であるため、業界に精通した弁護士であれば、実務レベルのアドバイスが可能となります。また、医療従事者や厚生労働省OBなどとのネットワークを持っている場合も多く、より深い見解や実績を基にした戦略的なサポートを提供できる点が大きな強みです。
■被害を最小限に抑える豊富な経験と実績
薬機法違反の疑いが浮上した際、実務経験が豊富な弁護士が関わることで、行政対応や捜査手続き、さらには報道リスクまで含め、企業へのダメージを最小限に食い止められます。たとえば、迅速かつ的確な証拠収集や説得力のある意見書の作成によって、厳しい行政処分や刑事罰の回避を目指すことが可能です。また、交渉能力や業界知識を活かして関係者との折衝をスムーズに進められるため、早期解決と企業イメージの保全につながります。豊富な解決実績をもつ弁護士であれば、想定外のリスクにも柔軟に対応できるでしょう。
薬機法違反を防ぐために弁護士ができるサポート

■広告表現・表示のリーガルチェック
医薬品や化粧品、健康食品などの広告表現は、誇大広告や虚偽表示と判断されないか、きわどいケースも少なくありません。薬機法を熟知した弁護士に広告表現のリーガルチェックを依頼すれば、違法になりかねない文言や根拠の不十分な効能効果の記載を指摘し、適法な表現へ修正するサポートを受けられます。たとえば、「絶対に効く」「医師が推奨」などのフレーズは、消費者を誤認させる恐れがあるため注意が必要です。あらかじめ弁護士にチェックを依頼しておくことで、後から行政指導や刑事罰、課徴金などの重大リスクを回避し、安全かつ効率的にビジネスを展開することが可能です。
関連記事:リーガルチェックとは?やり方や注意点・弁護士に依頼する費用を徹底解説
■行政指摘時の対応支援(意見書・見解書の作成)
行政から広告の表現や製造販売手続きなどで指摘を受けた場合、弁護士は法的根拠に基づいた意見書や見解書を作成し、説得力のある主張を展開できます。企業が単独で対応すると、どの点が問題視されているかを的確に把握できず、不要な譲歩をしてしまう恐れもあるでしょう。しかし、薬機法に精通した弁護士が支援に入ることで、根拠条文や過去の事例を踏まえたロジカルな反論や是正策の提案が可能です。これにより、行政側の理解を得ながらリスクを最小限に抑え、業務停止命令などの重い処分を回避できる可能性が高まります。
■薬機法に関する社内研修やセミナーの提供
薬機法の専門知識を社内に根付かせるためには、弁護士による研修やセミナーが効果的です。改正点や最新のガイドライン、実際に処分を受けた事例などをわかりやすく解説し、日頃の業務で陥りがちな注意点を明確にできるからです。また、質疑応答やケーススタディを交えることで、現場の実態に即した理解が深まり、社員一人ひとりが薬機法を遵守する意識を高められます。特に広告・販売部門など法令リスクの高い部門には、定期的な研修を行うことでトラブル発生の未然防止に大きく貢献します。
■継続的な顧問契約でリスク回避をサポート
薬機法リスクは一度の対策だけでは十分に防ぎきれないことも多く、日々の業務や新商品開発のなかで新たな課題が生じることがあります。継続的な顧問契約を締結すれば、広告表現のチェックや社内規定の見直し、問題が起こりそうな段階での即時相談など、常に弁護士のサポートを受けられるため、違反リスクを大幅に低減できます。経営方針やビジネスモデルを深く理解した弁護士による伴走型のサポートが、企業活動をより安全かつスムーズに進める鍵となるでしょう。
>>サービス・料金のご紹介はこちら
丸の内ソレイユが薬機法に強い理由

薬機法は度重なる改正や新制度(課徴金制度など)によって、常にアップデートされている法律の一つです。さらに、医療法や景品表示法などの関連法令とも密接に関わるため、総合的な知識が求められます。薬機法トラブルに強い弁護士は、厚生労働省の通知やガイドライン、判例の傾向などを日々チェックし、最新動向を掴んだうえで依頼者に最適な戦略を提案します。改正点をいち早く把握していることで、リスクの早期発見や事前対策が可能となり、結果として企業や個人が被るダメージを最小限に食い止めることにつながるのです。
■美容・健康・医療業界に精通した専門的知見
医薬品や医療機器のほか、化粧品や健康食品など、美容に関連する商材を扱う分野では、薬機法だけでなく医療法や景品表示法、さらには消費者庁・厚生労働省などの通達やガイドラインを横断的に理解する必要があります。
美容・医療業界に精通した弁護士であれば、広告表現や製品表示の改善点を的確に指摘できるだけでなく、市場のトレンドや業界特有の商習慣にも深い理解をもってサポートを行います。その結果、法令順守と企業のブランディング戦略を両立させるバランスのよいアドバイスが可能になるのです。
■行政対応や裁判実績が豊富
薬機法違反が疑われると、厚生労働省や都道府県の担当部局、警察・検察といった行政・捜査機関が調査に乗り出す場合があります。
こうした場面では、裁判経験豊富で実際に何度も折衝や対応を行ってきた弁護士がいると、手続きの進め方や必要書類の準備などを的確に把握し、早期解決を目指しやすくなります。
豊富な実績があれば、相手方機関とのコミュニケーションもスムーズになり、行政処分や刑事罰といった重大リスクを最小限に抑える可能性が高まるでしょう。
■事例紹介やコラム発信など、豊富な情報発信
数々の広告審査や企業顧問をしてきた実績を基に、専門的なコラムや解説記事を発信している弁護士は、業界の動向や法改正にも常にアンテナを張っています。
具体的な事例紹介は、どのような手順で問題を解決したのか、どれだけの期間や費用がかかったのかなど、依頼者が最も気になるポイントを知るうえで非常に参考になります。また、コラムや専門記事では最新のガイドライン情報や判例などもフォローされており、安心して依頼できるかどうかの判断材料にもなるでしょう。
>>薬機法・景表法・特商法違反事例
■顧問社数100社以上の薬機法関連のサポート実績多数
当法律事務所は、100社以上※の企業と顧問契約を結び、薬機法関連のサポート実績を多数積み重ねてきました。医療・美容分野に特化した豊富な事例に基づく的確なリスク評価、広告表現のチェック、行政対応など、各社のニーズに合わせたカスタマイズサポートを提供しています。その結果、多くのクライアントから高い信頼を獲得し、安心して事業運営に集中できる環境作りに貢献。実績と経験に裏打ちされた継続的なサポート体制が、企業の法令遵守とブランド保護を強力に支えます。
※顧問数は2025年4月現在の契約数
薬機法トラブルの無料相談はこちら

丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法、広告表現に関するご相談を30分無料でご利用いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせフォームからご連絡ください。
専門弁護士が現状の問題点を丁寧にヒアリングし、最適な対策や今後の対応方法について迅速かつ的確なアドバイスを提供いたします。法令遵守と安心のビジネス運営をサポートするため、まずは無料相談からご一報ください。


