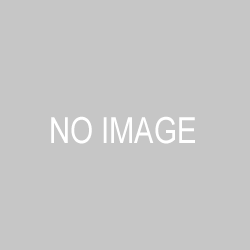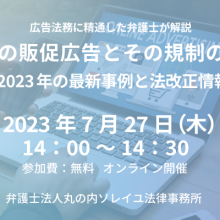「この表現、シワ“改善”って書いて大丈夫ですか?」
化粧品の広告やパッケージを検討する中で、こんなやりとりを経験した方も多いのではないでしょうか。
近年、消費者の「エイジングケア」ニーズの高まりに伴い、「シワ」に関する訴求表現はますます注目されています。しかし、薬機法上、化粧品広告には明確なルールがありますし、場合によっては景表法にも反してしまうリスクも存在します。
なかでも根拠として重視されるのが、昭和62年11月25日厚生省通知。
この通知は、現在でも広告実務の基準とされる重要な指針です。
本記事では、「シワ改善」という表現がなぜ問題になるのか、この通知の内容とともに、企業担当者が実務で押さえるべきポイントをわかりやすく解説します。
はじめに:化粧品広告と薬機法の関係性
化粧品の広告は、単なる販売促進手段にとどまらず、法的規制の下で慎重に管理されるべき情報発信行為です。
中でも薬機法は、「何を・どこまで表現してよいか」を判断する際の最も重要な法的基準となります。特に効能効果に関する表現は、医薬品と誤認されるリスクが高く、たとえ科学的根拠があったとしても、表示できないケースが多々存在します。
広告担当者や薬事・法務部門がこのルールを正しく理解しないと、知らず知らずのうちに違反行為をしてしまう可能性もあります。そこで本記事では、「シワ」を切り口に、化粧品広告における薬機法の実務上の要点を明らかにしていきます。
昭和62年11月25日 厚生省通知とは何か?
厚生省通知の背景と目的
昭和62年11月25日に出された本通知は、しわ取り効果を標榜する化粧品と医薬品の線引きを明確にすることを目的に発出されました。
化粧品の中でも訴求力の高いしわ取り効果を標榜する商品に関する広告や表示において、消費者が医薬品的な効果を誤認しないよう、化粧品に許される効能効果を具体的に定めたものです。
通知が示すNG表現とは

昭和62年の厚生省通知では、化粧品を使用することにより、①シワを解消する効果、②シワを予防する効果、③その他効果がある旨を標榜することは、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するもので認められないとしています。
①シワを解消する効果については、シワを解消、改善、シワの悩みを解消といった、要するにシワが消滅することを指し示す表現はNGとされています。
②シワを予防する効果についても、予防する効果又は防ぐ効果というそのままの表現や、肌をなめらかにする効果があるという表現もNGとされています。
③その他については、洗顔効果の二次的、三次的効果によって結局はシワが解消されることを暗示することや、「シワが気になる方」などとして悩みを具体化し、解消するかのような表現がNGとされています。
現在認められているシワに関する表現
化粧品の効能効果については、上記通知を含め、その他化粧品の効能効果に関する通知等を踏まえ、そののち日本化粧品工業連合会が、「化粧品等の適正広告ガイドライン」というものを策定しました。
同ガイドラインによれば、化粧品の効能効果として謳えるものは56項目のみであり、そのうちシワに関する表現は、「乾燥による小ジワを目立たなくする」のみとなっております。
「目立たなくする」とは、視覚的な印象の変化にとどまるため、化粧品として許容されるものと考えられています。一方で「改善」は、皮膚状態そのものが治癒・回復するニュアンスを含むため、医薬品的効能と解される可能性が高く、薬機法第68条(未承認医薬品の広告の禁止)違反のリスク等があります。
近年の行政指導や指摘事例
近年も、「シワを改善」「年齢肌を治す」といった表現が不適切とされ、自治体や消費者庁からの行政指導につながったケースが報告されています(例:ECサイトやパンフレットでの違反表現に対する指摘)。
やはりシワに関する効果は訴求力が高いため、行政側のチェックの目も厳しくなる傾向にあり、企業側の「改善」の語句使用に対して、厳しい目が向けられている現状があります。
表現審査フローにおける弁護士・法務の役割
社内で広告表現を審査する際、薬事やマーケティング部門だけで判断せず、法務部や外部弁護士が関与するフローを構築することが望まれます。
特にグレーな表現や新しい訴求を検討する場合は、薬機法・景表法双方の観点からリスクを精査することが重要です。広告審査に法的視点を組み込むことで、トラブルを未然に防ぐことが可能になります。
監督官庁・外部薬事顧問との連携の重要性
不明確な表現については、都道府県の薬務課など監督官庁に事前相談を行うことで、行政の考え方を把握し、対応を誤らないようにすることが有効です。また、社内に十分な薬事リソースがない場合は、薬事に精通した外部顧問との連携を通じて実務判断を下す体制の整備が求められます。法務・薬事・経営層が連携し、継続的にリスクマネジメントを行うことが広告コンプライアンス強化の鍵です。
おわりに:法律事務所として企業をどう支援できるか

広告・表示におけるコンプライアンス対応は、企業のブランド価値や信頼性を守るうえで欠かせない要素です。特に薬機法や景品表示法は専門性が高く、法令の条文だけでなく、通知や行政運用まで踏まえた判断が求められます。
こうした背景から、弁護士による表現審査のサポート、薬機法・景表法に関する社内研修の実施、リスクの事前調査・是正提案など、継続的かつ実務に即したリーガルサポートが重要です。特に新商品の訴求ポイントを検討する際には、企画段階から弁護士が関与することで、法的リスクを最小限に抑えることが可能になります。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景表法に精通した弁護士が、化粧品・健康食品・医療機器等の広告審査や社内体制整備をトータルに支援しています。表現に不安を感じたときや、広告方針の見直しを検討されている際は、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の信頼ある情報発信を、法務の側面からしっかりと支援いたします。
弁護士による化粧品・薬用化粧品相談はこちらでお受けしておりますので、ぜひご確認ください。

弁護士と薬剤師のダブルライセンスを持ち、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制など、ヘルスケア領域の法規制に精通。大手調剤薬局企業での企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応などに従事した経験をベースに、法律と医療的知識の双方から実務的なアドバイスを提供している。
健康食品・化粧品・医療機器・クリニック広告・EC領域における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、企業のコンプライアンス体制構築などを幅広く担当。多数のセミナー・講演実績を有し、最新の規制動向にも通じている。