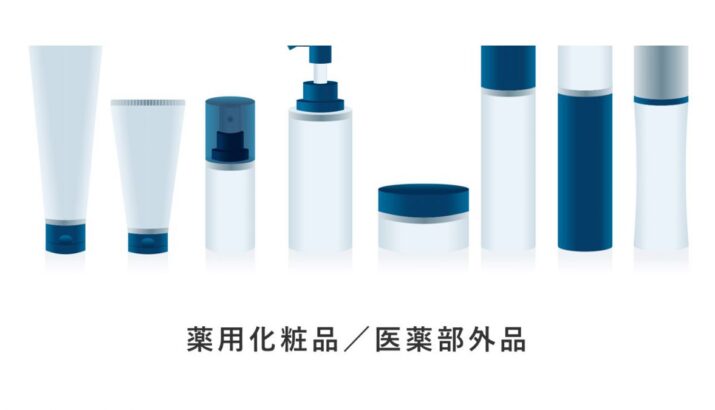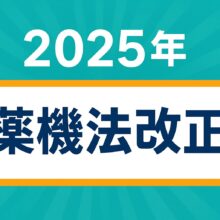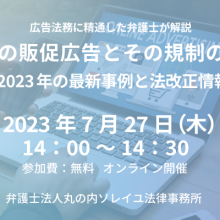「新商品の広告を作ることになったけど、薬機法って何から勉強すればいいのだろう?」
「うっかり薬機法に違反して、罰金や業務停止になったらどうしよう…」
広告や商品の販売に携わっていると、薬機法という言葉は避けて通れません。しかし、その内容は複雑で、どこから手をつければ良いか分からず、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、薬機法の基本から、規制対象となる製品カテゴリ、広告や表示に関する具体的なルールを解説します。さらに違反した場合の罰則まで、初めて学ぶ方にも分かりやすくまとめました。
この記事を読むことで、薬機法の違反リスクを避け、自信を持って広告・販売活動に取り組めるようになります。薬機法はビジネスの制約ではなく、消費者の信頼を得て、企業の成長を後押しする重要なツールと考えてもらった方が良いでしょう。
薬機法に関する広告表現や事業運営に不安がある方は、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。専門知識を持つ弁護士が、貴社のビジネスを法的な側面から強力にサポートします。
薬機法とは?初めて学ぶ人向けに基本を解説
薬機法(やっきほう)は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。薬機法の目的は、①医薬品等の品質、有効性、安全性の確保、②保健衛生上の危害の防止、③指定薬物の規制、④研究開発の促進にあります。
事業者や広告担当者は、製品の製造から販売、広告に至るまで、この法律に定められたルールを遵守しなければなりません。消費者が安心して製品を使える社会の基盤となる、極めて重要な法律です。
薬機法が定められている目的とは?
薬機法の最も重要な目的は、国民の保健衛生の向上です。具体的には、以下の4つの柱を掲げています。
| 品質・有効性・安全性の確保 | 市場に出回る医薬品等が、定められた基準を満たしていることを保証します。 |
| 使用による保健衛生上の危害の発生・拡大防止 | 拡大防止:万が一、製品に問題があった場合に迅速な対応(回収など)を可能にし、健康被害を防ぎます。 |
| 指定薬物の規制 | 毒薬や劇薬など、保健衛生上の危害を生む可能性がある薬物を規制します。 |
| 研究開発の促進 | 必要な医薬品や医療機器が、より早く医療現場で使われるように研究開発をサポートします。 |
薬機法は単なる規制ではなく、国民の命と健康を守るためのセーフティーネットとしての役割を担っています。
薬事法から薬機法へ|改正で何が変わったのか
薬機法は、もともと「薬事法」という名称でした。2014年11月25日に法律が改正・施行され、現在の名称に変更されています。この改正は、単なる名称変更にとどまらず、時代の変化に対応するための重要なアップデートでした。
主な変更点は以下の通りです。
| 医薬品、医療機器等に係る安全対策の強化 | ⑴法律の目的に、保健衛生上の危害発生・拡大防止のため必要な規制を行うことを明示。⑵医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保等に係る責務を関係者に課す。⑶医薬品等の製造販売業者は、最新の知見に基づき添付文書を作成し、厚生労働大臣に届出る。 |
| 医療機器の特性を踏まえた規制の構築 | ⑴医療機器の製造販売業・製造業について、医薬品等と章を区分して規定する。⑵医療機器の民間の第三者機関による認証制度を、基準を定めて高度管理医療機器にも拡大する。⑶診断等に用いる単体プログラムについて、医療機器として製造販売の承認・認証等の対象とする。⑷医療機器の製造業について、許可制から登録制に簡素化する。⑸医療機器の製造・品質管理方法の基準適合性調査について、合理化を図る。 |
| 再生医療等製品の特性を踏まえた規制の構築 | ⑴「再生医療等製品」を新たに定義するとともに、その特性を踏まえた安全対策等の規制を設ける。⑵均質でない再生医療等製品について、有効性が推定され、安全性が認められれば、特別に早期に、条件及び期限を付して製造販売承認を与えることを可能とする。 |
薬機法の改正により、より安全で効果的な製品が提供される環境が整備されています。事業者の責任がより一層、明確になったといえるでしょう。
関連記事:2025年の薬機法改正とは?改正ポイントと対応策をわかりやすく解説
薬機法の規制対象になる製品カテゴリ
薬機法が規制する対象は「医薬品等」と総称され、大きく6つのカテゴリに分類されます。自社で取り扱う製品がどれに該当するのかを正確に把握することが、薬機法を遵守する第一歩です。カテゴリによって、広告で表現できる効果・効能の範囲や、販売に必要な許可が異なります。それぞれの定義と具体例を理解しておきましょう。
医薬品
病気の診断、治療、予防を目的として使用されるもので、厚生労働大臣から有効成分の効果が認められた製品です。医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」と、ドラッグストアなどで購入できる「要指導医薬品」「一般用医薬品」(要指導医薬品と一般用医薬品を合わせて「OTC医薬品」と呼びます。)に分かれます。具体例:風邪薬、鎮痛剤、胃腸薬、抗生物質、高血圧治療薬など
関連記事:薬機法における医薬品とは?定義・販売規制・広告ルールを徹底解説
医薬部外品
治療よりも「予防・衛生」を目的とし、人体に対する作用が緩和なものです。「医薬品」と「化粧品」の中間のような位置づけです。医薬品のような治療効果はうたえませんが、厚生労働省に承認された範囲内での効果・効能(例:「ニキビを防ぐ」「口臭の防止」など)を表示することが可能です。
具体例:薬用歯磨き粉、薬用石鹸、制汗剤、育毛剤、染毛剤、入浴剤など
化粧品
身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を整えるなど、皮膚や毛髪を健やかに保つことを目的とする製品です。医薬部外品よりもさらに作用が緩和で、定められた56項目の効果・効能しか広告で表現できません。「シミが消える」「シワが改善する」といった表現は、医薬品的な効果とみなされ薬機法に違反する可能性が高いです。
具体例:スキンケア用品(化粧水、乳液)、メイクアップ用品(ファンデーション、口紅)、シャンプー、リンスなど
関連記事:薬機法と化粧品の広告規制とは?正しい表現ルールをわかりやすく解説
医療機器
病気の診断、治療、予防に使用し、身体の構造や機能に影響を与えることを目的とした機械器具です。人体へのリスクの高さに応じて、一般医療機器(クラスⅠ)、管理医療機器(クラスⅡ)、高度管理医療機器(クラスⅢ・Ⅳ)に分類され、それぞれ販売に必要な許可や資格が異なります。
具体例
- 一般医療機器:絆創膏、メス、ピンセット
- 管理医療機器:家庭用マッサージ器、電子体温計、コンタクトレンズ
- 高度管理医療機器:ペースメーカー、人工呼吸器
関連記事:薬機法と医療機器の規制範囲とは?定義・分類・該非判定までわかりやすく解説
再生医療等製品
身体の構造・機能を再建、修復、形成し、病気を治療・予防することを目的として、人や動物の細胞に培養などの加工を施したものです。2014年の法改正で新たに追加されたカテゴリで、先端医療技術の実用化を促進するための規制が設けられています。
具体例:人工培養皮膚、軟骨細胞シートなど
体外診断用医薬品
病気の診断に使用されることを目的とした医薬品のうち、直接人の身体に使用されないものです。主に、血液や尿などの検体から病気の兆候などを調べるために使われます。
具体例:妊娠検査薬、インフルエンザウイルス検出キット、血糖自己測定器など
薬機法で規制されている主なルール
薬機法は、製品が消費者の手に届くまでの各段階で、事業者が守るべきルールを定めています。製造・販売に必要な「許可」、消費者の誤認を防ぐ「広告」、安全な流通を保つ「販売」、そして製品情報を正しく伝える「表示」の4つが主要な規制の柱です。これらのルールを理解し、遵守することが事業の根幹を支えます。
事業者に必要な許可・登録制度
医薬品等を製造・販売するためには、製品カテゴリや業態に応じて、厚生労働大臣または都道府県知事から「許可」や「登録」を受ける必要があります。事業者が製品の品質や安全性を管理できる体制を持っていることを公的に認めるための制度です。無許可で製造や販売を行うことは、厳しく禁じられています。
主な許可の種類
- 製造販売業許可:製造(委託して製造した場合を含む)または輸入した医薬品などの製品を市場に出荷・流通させるために必要
- 製造業許可:製品を実際に製造(包装・表示・保管のみも含む)する施設ごとに必要
- 販売業許可:医薬品などを店舗などで販売するために必要
広告に関する薬機法ルール
薬機法第66条では、医薬品等の虚偽・誇大広告が禁止されています。これは、広告担当者が最も注意すべきルールの一つです。たとえ事実であっても、承認されていない効果・効能をうたう、安全性を過度に保証する表現などは違反とみなされます。消費者の適切な製品選択を妨げ、健康被害につながる恐れがあるためです。
禁止される広告の例
- 承認外の効果・効能の標榜:「このサプリでがんが治る」(未承認医薬品の広告とみなされる)
- 効果・安全性の最大級表現・保証表現:「絶対に効く」「副作用は一切ない」
- 他社製品の誹謗中傷:「A社の製品よりB社の製品が優れている」
- 医師・専門家の推薦:適切な根拠がない「医師も推薦」といった表現
販売・流通での取り扱いルール
製品が製造されてから消費者に届くまでの品質を保つため、販売や流通の方法にもルールが定められています。例えば、処方箋が必要な医療用医薬品を処方箋なしで販売することはできません。また、医薬品を販売する際には、薬剤師などの専門家が情報提供を行う義務があります。これにより、消費者が製品を正しく、安全に使用できる環境が確保されています。
ラベル・外箱表示のルール
消費者が製品を手に取った際に、必要な情報を正確に得られるよう、容器や外箱への表示(ラベリング)が義務付けられています。記載すべき内容は製品カテゴリごとに細かく定められており、成分の名称、製造販売業者の氏名・住所、用法・用量、使用期限などが含まれます。不適切な表示は、消費者の誤用や健康被害の原因となるため、厳しく規制されています。
薬機法違反の罰則と行政処分
| 処分の種類 | 内容 | 具体例・影響 |
| 刑事罰 (拘禁刑・罰金) | 違反が悪質な場合に科される刑事責任 | ・無許可で医薬品を製造・販売→5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金・虚偽・誇大広告→2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金・法人も対象となる「両罰規定」あり |
| 行政処分 (業務停止・改善命令など) | 厚生労働省や都道府県による監督処分 | ・改善命令:違反行為の是正を求める・業務停止命令:事業の一部または全部の停止・許可取り消し:市場からの退場に直結 |
| 課徴金 (虚偽・誇大広告への金銭的ペナルティ) | 違反広告で得た利益を国が徴収する制度 | ・課徴金額:対象商品の売上の4.5%・意図的でなくても課される可能性がある・広告表現一つで大きな金銭的リスクに発展 |
薬機法に違反した場合、事業者には厳しいペナルティが科せられます。罰則は、「刑事罰」、「行政処分」、そして「課徴金制度」の3つに大別されます。これらの罰則は、違反の抑止力として機能するとともに、市場の健全性を保つ上で重要な役割を果たしています。
刑事罰により拘禁刑や罰金が科される
薬機法違反の内容が悪質であると判断された場合、刑事罰の対象となります。例えば、無許可で医薬品を製造・販売した場合には「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金」、虚偽・誇大広告を行った場合には「2年以下の拘禁刑もしくは200万円以下の罰金」が科される可能性があります。また、法人に対しても罰金が科される「両罰規定」が設けられています。
特に注意すべきは、この両罰規定により法人だけでなく役員や広告担当者など“個人”も処罰対象となる点です。「会社の指示で作った広告だから」という理由では免責されず、刑事罰によって個人のキャリアや信用を大きく失うリスクがあります。事業停止や取引先の信頼喪失といった法人への影響に加え、個人にも直接的な責任が及ぶため、日常業務レベルから法令遵守を徹底する必要があります。
業務停止や改善命令などの行政処分
刑事罰とは別に、監督官庁(厚生労働省や都道府県)から行政処分が下されることもあります。これには、違反行為の是正を求める「改善命令」や、事業の一部または全部の停止を命じる「業務停止命令」が含まれます。
最も重い処分としては、事業の「許可取り消し」があり、これは事実上、市場からの退場を意味します。行政処分は企業の存続に直接影響を与える重大な措置です。
行政処分が下されると、単に業務が一時的に停止するだけでなく、消費者の信頼喪失やブランドイメージの毀損、株主や取引先からの信用低下といった二次的な損失も避けられません。特にEC事業者やスタートアップにとっては、短期間の業務停止でも売上が途絶し、経営に致命的なダメージとなる可能性があります。そのため、法令遵守の徹底は「処分を避ける」だけでなく、事業を継続するための必須条件といえます。
虚偽・誇大広告に対する金銭的ペナルティ
2021年の法改正で、虚偽・誇大広告に対する「課徴金制度」が導入されました。これは、違反広告によって得た不当な利益を国が徴収する制度です。課徴金の額は、原則として違反を行っていた期間中の対象商品の売上額の4.5%と定められています。
シミュレーション例
| 違反期間中の売上額 | 課徴金(売上の4.5%) |
| 1,000万円 | 45万円※課徴金が225万円未満の場合には課徴金納付命令は出されません。 |
| 5,000万円 | 225万円 |
| 1億円 | 450万円 |
違反していた期間の売上規模が大きければ、その分ペナルティも跳ね上がり、経営を直撃する負担となります。“知らなかった”では免責されないため、日常的に広告表現を法務・専門家と二重チェックする仕組みを導入することが、最も現実的なリスク回避策です。
薬機法違反を防ぐためのチェックポイント
薬機法違反は、意図せず起こしてしまうケースも少なくありません。日々の業務の中で、違反のリスクを未然に防ぐための仕組みを構築することが重要です。
ここでは、広告や販売に携わる担当者が実践すべき4つの基本的なチェックポイントを紹介します。違反を防ぐためのポイントを押さえておくことで、コンプライアンス意識の高い組織体制を築くことができます。
1.自社の商品が「医薬品等」に該当するか確認する
まず基本となるのが、取り扱う商品が薬機法の規制対象である「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器」のいずれかに該当するかを正確に把握することです。
特に、健康食品や雑貨として販売しているつもりが、効果や効能のうたい方によっては「未承認医薬品」とみなされるケースがあります。商品のカテゴリ認識を誤ると、広告表現や必要な許可の有無など、全ての前提が崩れてしまうため、慎重な確認が必要です。
2.広告・表示にNGワードが含まれていないかチェックする
広告やパッケージを作成する際には、薬機法で禁止されている表現が含まれていないか、細心の注意を払って確認しましょう。例えば、「治る」「再生」「アンチエイジング」といった医薬品的な効果を示唆する言葉や、「安全」「完璧」といった効果や安全性を保証する表現は原則として使用できません。
厚生労働省が公表している「医薬品等適正広告基準」などを参考に、社内で使用可能な表現とNG表現のリストを作成し、共有することが有効です。
(参照:厚生労働省|医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について)
関連記事:薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法
3.社内で薬機法を理解する体制を整える
薬機法への対応は、法務部門や特定の担当者だけが行うものではありません。商品企画、マーケティング、営業など、商品に関わる全ての従業員が基本的な知識を持つことが不可欠です。
具体的には「ワークフロー承認制」を導入するのが有効です。これは、広告や販促資料を公開する前に、必ず担当者 → 上長 → 法務担当といった承認ルートを通す仕組みのことを指します。承認の記録が残るため、誰がどの段階でチェックしたかが明確になり、担当者の独断による違反広告を防げます。
4.薬機法で表記に迷ったら専門家や弁護士に相談する
広告表現の可否判断は、非常に微妙で専門的な知識を要する場合があります。「この表現は大丈夫だろうか」と少しでも迷ったら、自己判断で進めずに専門家の意見を求めることが賢明です。
管轄の都道府県の薬務課に相談するほか、薬機法に詳しい弁護士などの外部の専門家を活用することで、より安全かつ効果的な広告表現を見出すことができます。
特に専門家に相談するメリットは、単に「NG表現を指摘される」ことにとどまらず、「どう言い換えれば安全かつ魅力的に訴求できるか」を具体的に提案してもらえる点にあります。攻めた広告戦略を取りたい場合ほど、禁止されるリスクを避けつつ訴求力を維持するために、専門家の知見を積極的に活用することが有効です。
薬機法に関する弁護士へのご相談はこちらまでお寄せください。
薬機法に関するよくある質問
薬機法は誰が規制対象になりますか?
薬機法の規制対象は、医薬品等の製造販売業者や販売業者に限りません。広告に関しては、広告主はもちろん、広告代理店、アフィリエイター、インフルエンサーなど、広告に実質的に関与する全ての人や法人が対象となり得ます。「依頼されただけ」という言い訳は通用しないため、誰もが当事者意識を持つ必要があります。
さらに注意すべきは、SNSにおける発信です。たとえ社員が自社製品を個人アカウントで紹介した場合でも、企業広告とみなされ規制対象となる可能性があります。同様に、インフルエンサーによるタイアップ投稿も、企業が責任を免れられるものではありません。公式広告だけでなく、個人によるPR投稿も含めて、社内でルールを徹底することが重要です。
薬機法違反になりやすい広告表現は?
特に違反となりやすいのは、以下のような表現です。
- 医薬品的な効果・効能の暗示:(化粧品で)「シミが消える」、(健康食品で)「血液サラサラ」
- 安全性の保証:「副作用が一切ない」「100%安全」
- 著名人の推薦:科学的根拠なく「〇〇医師も推薦」とうたうこと
- 使用前後の写真(ビフォーアフター):事実であっても、効果を過度に演出・保証していると見なされる可能性があります。
ネット広告やSNS投稿も薬機法の対象ですか?
はい、対象です。薬機法の広告規制は、テレビCMや新聞広告といった従来のメディアに限りません。ウェブサイト、バナー広告、リスティング広告、メールマガジン、SNS(Instagram、X、Facebookなど)の投稿、YouTube動画など、媒体の種類を問わず全ての表示・表現が対象となります。
違反してしまった場合どうすればいい?
万が一、行政から指導を受け、違反の可能性に気づいた場合は、速やかに誠実に対応することが重要です。
まずは、管轄の保健所や都道府県の薬務課に相談し、指示を仰ぎましょう。指摘された広告や表示を直ちに修正・削除するとともに、再発防止策を策定し、社内体制を見直す必要があります。隠蔽や放置をしてしまうと、事態がさらに悪化する可能性があるため、絶対にしてはいけません。
特に初動対応のスピードは非常に重要です。指摘を受けたら、まずは速やかに問題となる広告を修正・削除することを目安にしてください。対応が遅れるほど「悪質」と判断され、行政処分や信用失墜につながるリスクが高まります。迅速に対応する姿勢そのものが、企業の誠実さを示すことにも繋がります。
まとめ|薬機法を正しく理解し違反を防ごう
この記事では、薬機法の目的から規制対象、主なルール、そして違反を防ぐための対策までを網羅的に解説しました。
薬機法は、一見するとビジネス上の厳しい制約に感じられるかもしれません。しかし、その本質は、消費者の安全を守り、健全な市場を維持するための重要なルールです。この法律を正しく理解し遵守することは、企業の社会的責任を果たすだけでなく、消費者の信頼を獲得し、自社のブランド価値を高めることにも直結します。
この記事で得た知識を基に、まずは自社の商品カテゴリと広告表現を改めて見直すことから始めてみてください。そして、判断に迷うことがあれば、決して自己判断せず、専門家へ相談する習慣をつけましょう。それが、持続可能なビジネス成長への確実な一歩となります。
薬機法に関する広告表現のリーガルチェックや、事業運営に関する法的なご相談は、専門知識を有する弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にお任せください。貴社のビジネスが健全に発展できるよう、的確なアドバイスでサポートします。

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。