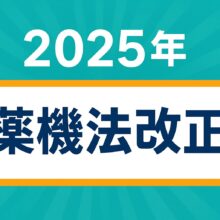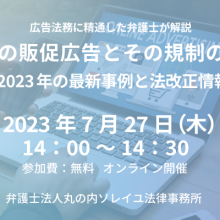「この広告表現、薬機法に引っかからないかな?」
「どこからが薬機法違反になるのか、基準がわからなくて不安…」
商品の魅力を伝えたいのに、法律の壁に悩むことは多いはずです。この記事では、薬機法違反の対象となる行為から、具体的な広告表現のNGパターン、そして厳しい罰則の内容までを網羅的に解説します。
この記事を読むことで、薬機法違反のリスクを正確に理解し、自信を持って広告・販売活動を行うための具体的な防止策を身につけることができます。コンプライアンス遵守と事業成長を両立させる知識を習得しましょう。
薬機法に関する広告表現や法務リスクでお悩みの際は、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。専門知識を持つ弁護士が、貴社の事業を守るための最適なサポートを提供します。
薬機法規制の対象とは?
薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品や化粧品などの品質・有効性・安全性を守るための法律です。
薬機法は、製品そのものだけでなく、販売や広告といった事業活動に関わるすべての人と行為に及びます。自分が「関係ない」と思っていても、気づかぬうちに違反しているケースは少なくありません。
まずは、どのような範囲が規制の対象となるのか、その全体像を正確に把握することが重要です。
(参考:厚生労働省|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
医薬品・医薬部外品・化粧品が規制対象
| 区分 | 概要 | 表現の注意点 |
| 医薬品 | 診断・治療・予防に使う | 効能効果を謳えるが承認範囲内のみ |
| 医薬部外品 | 承認を得た効能効果を発揮する有効成分が含まれている | 特定の効能効果の表現は認められるが限定的 |
| 化粧品 | 美化・清潔・外見を整える目的 | 56効能の範囲内のみ、治療表現はNG |
薬機法の規制対象として最も代表的なのが、医薬品、医薬部外品、化粧品です。これらは人の健康や美容に直接影響を与えるため、厳格なルールが定められています。
医療機器・再生医療等製品も規制対象
薬機法の規制は、医薬品や化粧品だけに留まりません。医療機器や再生医療等製品も重要な対象です。
- 医療機器:病気の診断や治療、予防に使われる機械器具などを指します。家庭用のマッサージ器やコンタクトレンズから、手術で使うメスやペースメーカーまで、リスクの度合いに応じてクラス分類され、それぞれ異なる規制が適用されます。例えば、未承認の海外製コンタクトレンズを広告・販売する行為は、明確な薬機法違反となります。
- 再生医療等製品:細胞培養などの技術を用いて人の体の構造や機能を修復・形成するものです。iPS細胞を使った治療などがこれにあたり、最先端の医療分野であるため、特に厳格な安全管理が求められます。
これらの製品を扱う事業者は、製造から販売、広告に至るまで、薬機法の規制を遵守する義務を負います。
関連記事:薬機法と医療機器の規制範囲とは?定義・分類・該非判定までわかりやすく解説
販売・製造・輸入などの事業行為が対象
薬機法は製品だけでなく、それらを取り扱う「事業行為」そのものを規制の対象としています。具体的には、製造、輸入、販売、授与、貸与といった一連のプロセスが該当します。
例えば、医薬品や医療機器を製造・販売するには、厚生労働大臣や都道府県知事からの許可が必要です。許可なく海外から化粧品を輸入し、フリマアプリで販売するような個人レベルの行為も、規制対象となり得ます。
重要なのは、製品が市場に出回るまでのすべてのステップが、薬機法の監視下にあるという認識です。製造業者は品質管理を、販売業者は適切な情報提供を、それぞれ求められます。
自社がどの段階の事業行為に関わっているのかを明確にし、必要な許可や遵守すべきルールを確認することが、違反を防ぐ第一歩となります。
広告・表示など表現活動も規制対象
薬機法違反で特に問題となりやすいのが、広告や表示といった表現活動です。消費者が製品を選ぶ際の重要な情報源となるため、虚偽・誇大な表現は厳しく禁じられています。
規制対象となる広告の範囲は非常に広く、テレビCMや新聞広告はもちろん、Webサイト、SNSの投稿、アフィリエイト広告、メールマガジン、さらには個人のブログや動画配信まで含まれます。製品の容器やパッケージに記載される表示も同様です。
薬機法第66条では、医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、虚偽または誇大な記事を広告し、記述し、または流布してはならないと定められています。
たとえ悪意がなくても、結果的に消費者に誤解を与える表現をしてしまえば、違反と見なされる可能性があるため、細心の注意が求められます。
(参考:厚生労働省|薬機法における広告規制)
関連記事:薬機法の広告規制とは?広告の定義・3要件・違反事例まとめ
薬機法違反を招きやすい広告パターン
商品の魅力を最大限に伝えたいという思いが、結果として薬機法違反につながるケースは後を絶ちません。
特に、健康や美容に関する商品は消費者の期待や不安に直接訴えかけるため、表現がエスカレートしがちです。ここでは、多くの事業者が陥りやすい典型的な広告のNGパターンを3つ紹介します。自社の広告がこれらに該当していないか、客観的な視点でチェックしてみてください。
「治る」「絶対安全」などの誇張表現
薬機法違反の典型例が、化粧品の効能効果の範囲を逸脱する表現や、安全性を保証するような誇張表現です。「がんが治る」という治療効果は化粧品の効能効果の範囲を逸脱しておりますし、「飲むだけで痩せる」といった表現も、身体に変化を生じさせる効果を表すものであり、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するものとなります。
また、「誰でも」「100%」「絶対」といった言葉を用いて効果を保証すること、また「副作用は一切なし」「絶対に安全」などと安全性を過度に強調することも、消費者に誤解を与えるため認められていません。
| 表現カテゴリ | NG例 | 理由 | 言い換えの工夫 (OK表現例) |
| 治療効果 | 「治る」 「完治する」 | 医薬品でしか標榜できない効能効果 | 言い換え表現はありません |
| 安全性の断定 | 「絶対安全」 「副作用なし」 | 科学的に完全保証できないため誤認リスク | 「安全性に配慮して開発された」「多くの方に安心して利用いただいている実績」 |
| 効果保証 | 「100%効く」「誰でも痩せる」 | 個人差を無視した断定で虚偽・誇大に該当 | 「食事制限や運動と組み合わせましょう」 |
| 根拠不明のNo.1 | 「日本一」 「世界一」 | 客観的データがない場合は誇大広告に該当 | 調査主体、調査期間、調査対象等の根拠を明示 |
たとえ事実であったとしても、最大級の表現は避けるべきです。逆に、公的な調査データや論文などの裏付けがある場合は“根拠を明示したうえで限定的に表現”することが可能です。広告担当者は「断定」から「期待・可能性」へ言い換える視点を持つことが重要です。
口コミ・体験談の誤用
消費者からの口コミや体験談は、信頼性の高い情報として広告に活用されがちですが、その内容には注意が必要です。たとえ個人の感想であっても、事業者が広告として掲載した場合、その内容は事業者の責任となります。
例えば、化粧品の体験談で「このクリームを塗ったらシミが完全に消えました」といった内容を掲載すると、化粧品として認められていない治療的な効果を謳ったと見なされ、薬機法違反に問われます。体験談の内容が、製品の承認された効能効果の範囲を逸脱していないか、慎重に確認しなくてはなりません。
個人の感想であることを示すために「※個人の感想です」といった注釈(打ち消し表示)を付ければ良いと考えるかもしれませんが、それだけで違反を免れることはできないので注意が必要です。
| 利用方法 | NG例 | OK例 |
| 効果効能を断定する口コミ | 「このサプリを飲んだら10kg痩せた」「シミが完全に消えた」 | ✕ 違反リスク大 |
| 使用感・個人の感想に留める口コミ | 「爽やかな香りで気分がリフレッシュする」「肌がしっとりしたように感じる」 | ○ 許容されやすい |
| 打ち消し表示 | 「※個人の感想です」 | × 免責されない |
つまり、口コミを違反なく使用するためには、“効能効果”ではなく“使用感・印象”に留めることが重要です。事業者は広告制作の段階で「NG表現を事前に削る」体制を整えることが安全策となります。
ビフォーアフター画像の使用
ビフォーアフターの画像やイラストは、変化を視覚的に伝えやすく、非常に訴求力の高い表現方法ですが、薬機法においては使用に厳しい制限があります。
ビフォーアフターの表現は、誰でも同じような効果が得られるかのような誤解を与えやすく、効能効果の保証につながるからです。特に、化粧品や健康食品の広告で、シワやシミが消えるような表現や、体型が劇的に変化するような画像を使用することは、そもそも化粧品の効能効果の範囲を逸脱した表現として認められませんし、変化を表す手法として原則として認められていません。
例外的に、ヘアカラーによる髪色の変化や、メイクアップ効果による見た目の変化など、製品の物理的な効果を示す場合は使用が認められることもあります。しかし、その場合でも過度な加工や演出はNGです。安易なビフォーアフター表現はリスクが高いと認識し、使用する際は慎重な判断が求められます。
薬機法違反に課される罰則
薬機法に違反した場合、単なる注意喚起で済まされるわけではありません。事業の存続を揺るがしかねない厳しい罰則が科される可能性があります。罰則は大きく分けて「刑事罰」「行政処分」「課徴金」の3種類があり、これらが併科されることもあります。どのようなペナルティがあるのかを具体的に理解し、違反のリスクを正しく認識しましょう。
懲役や罰金などの刑事罰
薬機法違反が悪質と判断された場合、懲役や罰金といった刑事罰の対象となります。
例えば、承認前の医薬品を広告・販売した場合や、虚偽・誇大な広告を行った場合、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方」が科される可能性があります(薬機法第85条)。
実際に、未承認のコンタクトレンズや健康食品を販売して摘発された業者が、責任者に懲役刑を科された事例もあります。法人はブランド毀損・取引停止といった経営リスクを負い、個人事業主は直接収入や生活に直結する刑罰を受ける可能性があります。
法人が違反した場合は、行為者を罰するだけでなく、その法人に対しても罰金が科される「両罰規定」が設けられています。企業の代表者が処罰されるだけでなく、個人事業主は直接生活に直結する罰を受けるリスクがあります。社会的信用の失墜は避けられません。刑事罰は、薬機法違反の中でも特に重い処分であることを覚えておきましょう。
業務停止などの行政処分
刑事罰とは別に、監督官庁である厚生労働省や都道府県から下されるのが行政処分です。これは、事業運営に直接的な影響を与える処分です。
代表的な行政処分には、違反行為の是正を求める「改善命令」や、一定期間の営業を禁じる「業務停止命令」があります。業務停止命令が出されれば、その期間中は製品の製造や販売が一切できなくなり、売上に深刻なダメージを与えます。
さらに、違反が重大である場合や改善が見られない場合には、事業を行うために必要な「許可の取り消し」という最も重い処分が下されることもあります。これは事実上の廃業を意味し、事業の継続が不可能になります。
誇大広告に対する課徴金
2021年8月の法改正で、虚偽・誇大広告に対する課徴金制度が導入されました。これは、違反によって得た不当な利益を徴収することで、違反行為の抑止力とすることを目的としています。「違反しても儲かる」という不公平をなくし、企業にコンプライアンス意識を徹底させる狙いがあります。
課徴金の額は、原則として違反していた期間中の対象商品の売上額の4.5%です。例えば、1億円の売上があった場合、450万円の課徴金が課される計算になります。売上規模に比例して数百万円単位の課徴金が発生することもあり、大企業に限らず中小企業や個人事業主でも、経営に深刻な打撃を与える可能性がある制度です。
この制度のポイントは、事業者に故意や過失がなかったとしても、売上が発生していれば課徴金の対象となる点です。つまり「知らなかった」では済まされません。売上が大きいほど課徴金の額も高額になるため、特に大規模に事業を展開している企業にとっては大きな脅威となります。
薬機法違反の発覚から処分に至るまでの流れ
薬機法違反は、どのようにして発覚し、処分へと至るのでしょうか。多くの場合、突然刑事告発されるわけではなく、行政指導から段階的に進んでいきます。しかし、悪質な場合等、いきなり刑事罰や行政処分を下されることもあります。下記では、行政指導から段階的に進んだ場合のプロセスを示し、万が一指摘を受けた場合にも冷静に対応できるようにしつつ、そもそも薬機法違反をしないようにしましょう。
1.行政調査・消費者からの通報により発覚
薬機法違反が発覚するきっかけは様々です。代表的なのは、都道府県の薬務課などによる行政の定期的な監視(サイバーパトロールなど)です。行政は、不適切な広告表現がないか、インターネット上などを常にチェックしています。
また、競合他社からの告発や、広告を見た消費者からの通報によって調査が開始されるケースも少なくありません。実際には、競合他社や消費者からの通報が発端となることも多く、厚生労働省の公式HPでは、消費者から薬機法違反の疑いがあるサイトを手軽に通報できる仕組みが整備されています。
(参考:厚生労働省|医薬品医療機器等法違反の疑いがあるインターネットサイトの情報をお寄せください!)
特に、健康被害につながるような悪質なケースでは、消費者からの情報提供が重要な端緒となります。些細な表現であっても、誰かに見られているという意識を持つことが大切です。
2.行政による調査・指導
違反の疑いが発覚すると、まず行政(保健所や都道府県の薬務課)による調査が行われます。担当者が事業所に立ち入り調査を行い、広告表現に関する資料の提出を求めます。行政指導では、広告の即時停止、表示内容の修正、再発防止策の提出といった具体的な対応を求められるのが一般的です。
この段階で違反が確認された場合、多くはまず「行政指導」という形での改善要請が行われます。法的な強制力を持つ処分ではありませんが、改善されない場合はより重い行政処分に移行する可能性が一般的です。具体的には、広告表現の修正や、ウェブサイトの一時的な閉鎖などを求められます。この段階で誠実に対応すれば、刑事告発まで発展する可能性を減らせます。
3.改善命令・業務停止などの行政処分の決定
行政指導に従わない、または違反内容が重大であると判断された場合、法的な強制力を持つ行政処分が下されます。
前述の通り、違反広告の中止や回収を命じる「措置命令」、業務運営の改善を求める「改善命令」、そして一定期間の営業を禁じる「業務停止命令」などがあります。最も重い処分としては「許可取消」があり、事実上の市場撤退を意味するものです。
処分の重さは、違反の悪質性・継続性・改善姿勢などを総合的に判断して決まります。初回の違反で速やかに対処すれば軽い処分にとどまることもありますが、繰り返し違反した場合は許可取消に直結するリスクがあります。
これらの処分は原則として公開されるため、企業のブランドイメージや社会的信用に大きなダメージを与えかねません。処分の内容は、違反の程度や悪質性、是正への対応状況などを総合的に考慮して決定されます。
4.悪質な場合は刑事事件として送致される
行政処分に従わない、健康被害を引き起こすなど、極めて悪質性が高いと判断されたケースでは、行政は警察に告発し、刑事事件として立件されることになります。
告発が行われると、警察による捜査が開始され、最終的には検察が起訴・不起訴を判断します。起訴されれば刑事裁判となり、有罪判決が下されれば懲役刑や罰金刑が科されることになります。
特に、未承認医薬品を大量に販売した場合や、広告を原因として消費者に健康被害が発生した場合は刑事事件化されやすく、逮捕や起訴に至るケースもあります。行政処分と刑事罰は別手続きのため、両方が科される可能性もある点には注意が必要です。
行政処分と刑事罰は別の手続きであるため、両方が科されることもあります。ここまで至るケースはまれですが、最悪のシナリオとして常に念頭に置くべきです。
薬機法違反を防ぐためにできること
薬機法違反は、意図せず起こしてしまうケースも少なくありません。しかし「知らなかった」では済まされないのが法律の厳しいところです。違反を未然に防ぎ、健全な事業活動を続けるためには、日頃からの対策が不可欠です。ここでは、今日から実践できる具体的な防止策を3つ紹介します。
1.薬機法チェックリストや専門ツールを活用する
広告を作成する際に、薬機法違反のリスクがないかを客観的に確認する仕組みを導入することが有効です。厚生労働省や自治体が公表しているガイドラインを参考に、自社独自の広告表現チェックリストを作成しましょう。
例えば、「断定的な表現を使っていないか」「承認されていない効能効果を暗示していないか」「ビフォーアフター表現が不適切でないか」といった項目を設けることで、担当者がセルフチェックできます。
最近では、AIを活用して広告文案の薬機法リスクを自動で判定する専門ツールも登場しています。これらのツールを導入することで、チェック作業の効率化と精度の向上が期待できます。
2.自社の商品が規制対象かを確認する
薬機法違反を防ぐための第一歩は、取り扱っている商品が薬機法のどのカテゴリ(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器など)に該当するのかを正確に把握することです。
例えば、海外から輸入した雑貨を化粧品として販売する場合、日本の薬機法に基づく成分規制や表示義務などをクリアする必要があります。また、健康食品(サプリメント)は、原則として医薬品的な効能効果を謳うことはできません。
商品のカテゴリによって、広告で表現できる効能効果の範囲は厳密に定められています。自社商品の位置づけを正しく理解し、認められた範囲内での訴求を徹底することが、コンプライアンスの基本です。
3.社内で薬機法を学び、運用体制を整える
薬機法に関する知識は、法務担当者だけでなく、商品開発、マーケティング、広告運用など、事業に関わるすべての従業員が共有すべきです。
定期的に社内研修会を実施し、薬機法の基本や最新の法改正、違反事例などを学ぶ機会を設けましょう。これにより、社内全体のコンプライアンス意識を高めることができます。
さらに、広告を公開する前に、法務部門や専門知識を持つ担当者が必ず内容をレビューするダブルチェック体制を構築することも重要です。担当者一人に判断を委ねるのではなく、組織としてリスクを管理する運用体制を整えることで、ヒューマンエラーによる違反を効果的に防ぐことができます。
薬機法違反を避けるには専門家・弁護士への相談が安心
社内での対策を徹底しても、広告表現が薬機法に抵触するかどうかの判断は、非常に専門的で難しいケースが多く存在します。
特に、新しいタイプの商品やサービス、斬新なマーケティング手法を用いる場合、過去の事例だけでは判断できないグレーゾーンが生じがちです。
判断が難しい場面で頼りになるのが、薬機法に精通した弁護士などの専門家です。専門家に相談することで、法的リスクを事前に回避し、安心して事業を推進できます。
関連記事:薬機法を弁護士に相談するメリットとは?広告チェックから違反対応のポイントを解説
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法や景品表示法に関する豊富な実務経験を活かし、広告やパッケージ表現のリーガルチェックから、万が一の行政対応まで幅広くサポートしています。事業者が安心してマーケティングに取り組める体制づくりをサポートしてくれるため、コンプライアンスと事業成長を両立させたい方に最適です。
薬機法に関する弁護士へのご相談はこちらまでお寄せください。
薬機法違反に関するよくある質問
薬機法違反は誰に責任が及ぶ?
薬機法の規制対象は「何人も」とされています。
そのため、広告主(販売事業者)のみならず、広告の企画・制作に関わった広告代理店や、商品を自身のメディアで紹介したアフィリエイター、インフルエンサーなども、内容によっては責任を問われる可能性があります。関与したすべての人が当事者意識を持つことが重要です。
薬機法違反は消費者からの通報でも調査される?
はい、調査されます。消費者や競合他社からの通報は、行政が薬機法違反の端緒を掴むための重要な情報源です。保健所や各都道府県の薬務課には相談窓口が設けられており、寄せられた情報は精査され、違反の疑いがあれば調査が開始されます。不適切な広告は常に監視されていると考えるべきです。
違反してしまったときはどう対応すべき?
万が一、行政から薬機法違反の指摘を受けた場合は、誠実かつ迅速に対応することが何よりも重要です。まずは指摘内容を正確に把握し、問題となった広告の掲載を直ちに中止するなど、速やかに是正措置を講じましょう。
その上で、行政の指示に従い、改善計画などを提出します。対応に不安がある場合は、速やかに弁護士に相談し、専門的な助言を仰ぐことを強く推奨します。
個人事業主・副業でも薬機法違反になる可能性
薬機法は、広告の発信主体が「法人か個人か」を区別していません。つまり、企業の広告であれ、個人が運営するブログ・SNSであれ、内容が「販売を目的とした広告」と判断されれば同じ規制が適用されます。
なぜなら、薬機法が規制しているのは「広告表現そのもの」であり、発信者の規模や立場ではなく、消費者に与える影響の有無だからです。例えば、個人が「このサプリで必ず痩せます」と投稿し、それを見た消費者が誤解して購入すれば、企業広告と同じリスクが発生します。
そのため、副業アフィリエイトやインフルエンサーの投稿であっても、「効果を断定する表現」「安全性を保証する表現」をすれば薬機法違反に問われる可能性があります。消費者庁や厚労省は、規模の小さな事業者や個人に対しても指導・処分を行った事例を公表しているため、「個人だから大丈夫」「プライベートのSNSだから安心」という油断は禁物です。
まとめ|薬機法違反を防ぎ正しい広告・販売を実現しよう
この記事では、薬機法違反の対象から具体的なNG広告パターン、罰則、そして防止策までを解説しました。薬機法は、消費者の健康と安全を守るための重要な法律であり、その規制は製品だけでなく、広告や販売に関わるすべての人に及びます。
違反すると、懲役や罰金、業務停止、高額な課徴金といった厳しいペナルティが科され、企業の存続を脅かす事態になりかねません。特に「治る」といった化粧品の効能効果を逸脱した表現や、体験談の誤用、安易なビフォーアフター画像の使用は、違反につながりやすい典型的なパターンです。
薬機法違反を防ぐためには、自社商品の法的な位置づけを正確に理解し、社内でのチェック体制を整えることが不可欠です。しかし、最終的な判断が難しいグレーゾーンも多く存在します。決して自己判断せず、薬機法に詳しい弁護士などの専門家に相談することが、最も確実なリスク回避策となります。
薬機法に関する手続きや広告表現のリーガルチェックにお悩みの方は、企業法務に強い弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。60分の無料相談も実施しています。

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。