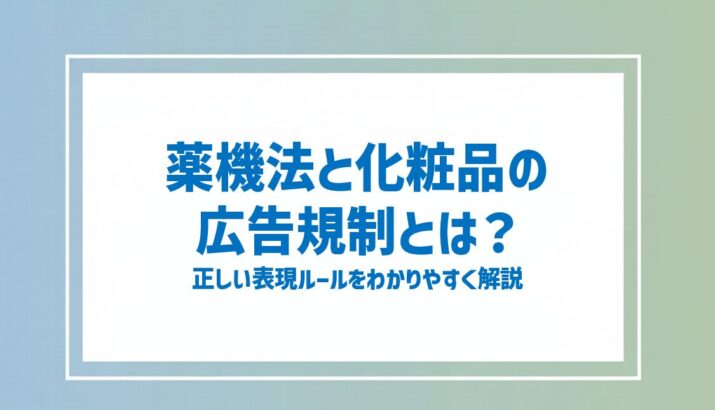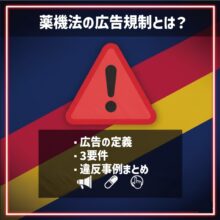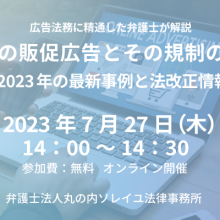「このキャッチコピー、化粧品の広告で薬機法に引っかからないかな?」
「シミやシワに効くって書きたいけど、どこまでがOKでどこからがNGなのか分からない…」
化粧品や美容商品の広告を担当していると、こうした悩みを抱えることが多いですよね?化粧品は医薬部外品や医薬品と境界があいまいな部分も多く、判断を誤ると薬機法違反となり、行政処分や課徴金、最悪の場合は刑事罰につながるリスクがあります。
この記事では、薬機法における化粧品の定義から、医薬部外品や医薬品との違い、そして広告で使える表現とNG表現の線引きまで具体的に解説します。
この記事を読むことで「薬機法を守りながらも魅力的に化粧品を訴求する方法」が分かり、広告担当者として安心してクリエイティブを制作できるようになります。
薬機法に関する広告表現のリーガルチェックや、社内の広告体制づくりに不安がある場合は、専門知識を持つ弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 にご相談ください。豊富な実績をもとに、貴社のビジネスを法的リスクから守り、安心して発展できるようサポートします。
薬機法における化粧品の定義とは?
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)における化粧品の定義については下記で解説します。
化粧品とみなされる条件
薬機法第2条第3項では、化粧品は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。
具体例としては、洗顔料・シャンプー・化粧水・乳液・口紅・ファンデーションなどが該当します。
具体的に化粧品とみなされるには、以下の条件を満たす必要があります。
- 使用目的:清潔、美化、魅力向上、健やかさの保持など
- 使用部位:皮膚、毛髪、爪、口唇など身体の外表部分
- 作用の程度:人体に対して緩和であること(強い作用は医薬部外品・医薬品に分類される)
たとえば「肌をしっとりさせる」「毛髪にツヤを与える」といった表現は化粧品の範囲ですが、「ニキビを治す」「シミを消す」などは治療効果にあたり、化粧品ではなく医薬部外品や医薬品として扱われます。
化粧品と医薬部外品・医薬品の違い
化粧品広告で最も混同されやすいのが「医薬部外品」との違いです。違いを理解せずに「シミが消える」「ニキビが治る」と広告すると、本来「医薬品」にしか認められない効能をうたったことになり、薬機法違反の対象になります。
| 区分 | 定義 | 例 | 認められる効能効果の範囲 |
| 化粧品 | 身体を清潔・美化・健やかに保つ作用が緩和なもの | 化粧水、口紅、シャンプー | 肌を整える、潤いを与える、清浄にする、毛髪にハリを与える など |
| 医薬部外品 | 厚生労働大臣が指定。人体への作用は化粧品より強いが医薬品ほどではない | 薬用化粧水、薬用シャンプー、育毛剤、制汗剤 | 「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」「ふけ・かゆみを防ぐ」など限定的な効能が認められる |
| 医薬品 | 疾病の診断・治療・予防に使用されるもの | ニキビ治療薬、シミ治療薬、抗真菌薬 | 治療や改善を目的とした効能効果をうたえる |
つまり、広告表現を考える際には「これは本当に化粧品の範囲に収まっているか?」を意識する必要があります。違いを理解せずに「シミが消える」「ニキビが治る」と広告すると、本来「医薬品」にしか認められない効能をうたったことになり、薬機法違反の対象になります。線引きを誤れば薬機法違反に直結するため、商品設計段階から定義を理解しておくことが重要です。
関連記事:薬機法における医薬品とは?定義・販売規制・広告ルールを徹底解説
薬機法が化粧品に適用される対象範囲
薬機法は「製品そのもの」だけでなく、広告やパッケージ表示など消費者が商品を選ぶためのあらゆる情報に適用されます。化粧品の担当者は「製造・流通」だけでなく「広告・表記」まで幅広く規制対象になることを理解しておく必要があります。
薬機法上の広告は「顧客を誘引し」「特定の商品を対象とし」「一般消費者が認知できるもの」という3要件(顧客誘引性・特定性・認知可能性)で定義されています。 このため、広告は必ずしも企業が制作するものに限られません。インフルエンサーのSNS投稿も、金銭や商品提供といった対価があれば広告とみなされ、薬機法の規制対象となります。
つまり「誰が発信するか」ではなく「消費者にどのように認知されるか」が重要であり、販促のあらゆる場面で薬機法を意識することが求められます。
広告やキャッチコピーなどの販促表現
化粧品を販促するための広告、チラシ、店頭ポップ、SNS投稿、インフルエンサーによる紹介まで、すべて薬機法の対象です。特にキャッチコピーは、訴求力を高めようとしてNG表現に陥りやすい領域と言われています。
- OK例:「肌にうるおいを与える」「髪にツヤを与える」
- NG例:「シミが消える」「抜け毛を治す」「ニキビを改善」
ポイントは「誰が発信するか」ではなく、「商品を販売促進する意図があるかどうか」です。たとえ個人のSNS投稿であっても、企業から金銭や商品提供を受けて紹介している場合は「広告」とみなされ、薬機法が適用されます。
こうした表現は、消費者に「医薬品的な効能がある」と誤認させるため、薬機法第66条(誇大広告の禁止)に抵触します。規制が入る理由は、誤解を与える広告が 医師の診察機会を奪い、健康被害につながる恐れがある からです。
つまり、広告を制作するときは「美容目的で使えるかどうか」ではなく「医薬品的な効能を暗示していないか」を基準に確認することが大切です。
(参考:厚生労働省|医薬品等の広告規制について)
原材料や使用期限など商品の表記
パッケージやラベルに記載される情報も薬機法で定められています。これは、消費者が成分の安全性を確認したり、正しい使用方法を理解したりするために不可欠な情報だからです。具体的には「化粧品基準」に基づき、以下の項目を必ず表示しなければなりません。
- 全成分表示(配合量の多い順に列記)
- 使用期限(未開封で3年を超えて安定する製品は省略可)
- 使用上の注意(アレルギーや誤用を防ぐための記載)
- 販売名・製造販売業者の氏名又は名称・住所
商品表記を怠った場合も薬機法違反となり、行政指導や回収命令の対象になることがあります。重大なケースでは 製品の回収命令や販売停止処分 に至ることもあります。特に成分表示の誤りは、アレルギー事故や消費者トラブルにつながりやすく、企業の信頼失墜にも直結します。
そのため、 商品設計の初期段階から弁護士や薬事の専門家に確認してもらうフローを設けること が、安全性確保とブランド維持の両面で欠かせません。
薬機法で認められている化粧品広告の表現
薬機法のもと、化粧品が広告で訴求できる効能効果は 「化粧品基準」 によって明確に定められています。これは厚生労働省が定めた56項目に限定されており、それ以外の表現を用いると薬機法違反に該当する可能性があります。広告担当者は「NGワードを避ける」だけでなく「どこまでならOKか」を正しく理解することが重要です。
広告で使える効能効果の56項目
厚生労働省の通知で定められた56項目の範囲内であれば、化粧品広告として効果効能を表示できます。化粧品基準の56項目は、「人体に影響がない範囲で、日常の美容目的として一般的に認められる効果」 のみを列挙したものです。
例えば「肌や髪にうるおいを与える」「日やけを防ぐ」「毛髪にハリやコシを与える」といった表現はOKですが、「病気を治す」「身体機能を改善する」といった医薬品的な効能は含まれていません。たとえば以下のような表現です。
- 肌や髪にうるおいを与える
- 日やけを防ぐ
毛髪にハリやコシを与える - 肌を清浄にする
この線引きにより、消費者が誤って化粧品を「薬の代替」と誤認しないようにしています。化粧品基準の56項目は厚生労働省が公開しており、広告担当者は必ず確認しておく必要があります。
「乾燥による小ジワ」など特定の表現
「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現は、化粧品基準の56項目に含まれるものの、条件付きでのみ認められています。これは日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行い、その効果を確認した場合に限定的に認められた表現です。
ただし使用する際には以下の注意点があります。
- 「乾燥による」と必ず原因を限定すること
- 客観的な試験データを保持しておくこと
- 単に「シワが改善」とは書けない
化粧品基準の特例表現は条件付きでのみ認められるため、広告で使用する場合はガイドラインを遵守しなければなりません。
(参考:日本香粧品学会|抗シワ製品評価ガイドライン)
【2025年改正】化粧品における特定成分の特記表示について
2025年(令和7年3月10日)、化粧品の特定成分に関する特記表示制度が約40年ぶりに見直されました。その改正では、従来認められていた曖昧な成分強調表現を見直し、「客観的実証」「統括的成分にもルール適用」などの新たな規制が導入されました。 (参考:石川県公式ホームページ)
主な変更点とその意味
| 変更項目 | 改正前 | 改正後 |
| 特記表示の定義 | 訴求したい成分を目立たせて表示すること | 成分を表示する行為すべてを「特記表示」とみなす可能性 |
| 配合目的の扱い | 特記表示をするなら必ず必要。 | 特記表示するなら必ず配合目的を併記。効能/技術に基づくかつ客観的に実証された内容でなければならない |
| 写真・デザイン表示 | 成分絵・写真での強調表示も緩く扱われがち | これも配合目的併記必須。たとえば、写真・英文表現中でも「成分名 + 配合目的」を明示 |
| 統括的成分表現 | 「植物成分」「植物抽出物」等で配合目的不要とされていた例外あり | 例外規定が削除され、統括的成分でも配合目的併記が基本義務化 |
| 禁止対象の成分名称 | 「薬」「薬用」「漢方」など含む名称 | 依然として名称中に「薬」の字が含まれるものは原則的に特記表示不可 |
運用上の注意と対応策
- 配合目的を併記する際の表現自由度:効能効果・製剤技術に基づくもので「客観的に実証されている」ことが求められます。自社データでも客観性が担保されていれば許容されうるとの通知もあり
表示位置・視認性の制御:成分名の前後・フォント・色・配置などで配合目的との関係性が読み取れない場合は不適切扱いとなる可能性あり。 - 広告表現との整合性:広告LPや宣伝文で特記成分を強調する際、「あたかも有効成分かのような誤認表示」が生じないよう、広告全体の調整が必須
- 旧通知の取り扱い廃止:昭和60年の旧通知(薬監第53号)は改正により原則廃止され、改正後ルール優先と扱われます
今回の改正を踏まえると、「特定の成分を表示するなら必ず配合目的を添える」「科学的根拠のある範囲でのみ表現する」「広告とパッケージの整合性を取る」という3点を徹底することが重要です。とくに「従来OKだった表現がNGになる」ケースもあるため、過去の表示や広告も一度棚卸しして見直す必要があります。
薬機法における化粧品広告で禁止されるNG表現
化粧品は「人体を清潔にし、美化し、魅力を増し、皮膚や毛髪を健やかに保つもの」と薬機法で定義されています。そのため「治療・予防」といった医薬品的な効能や、絶対性を保証する表現は使用できません。ここでは、化粧品広告で特に注意すべき5つの表現カテゴリを解説します。
関連記事:薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法
「治る・改善する」など医薬品的な表現
「ニキビが治る」「シミを改善」「抜け毛を治す」といった治療・予防を意味する表現はすべてNGです。薬機法では、これらは医薬品にしか認められていない効能に該当し、消費者を誤認させるリスクがあります。
| NG表現例 | 禁止される理由 | OK表現例 |
| ニキビが治る | 医薬品的効能を示すため化粧品では不可 | ニキビを防ぐ、肌を清浄にする |
| シミが改善する | 治療を暗示するため誤認リスクが高い | 肌を保護する |
| 抜け毛を治す | 身体機能改善を示すためNG | 毛髪・頭皮を健やかに保つ |
| 肌再生・細胞修復 | 組織の治療を意味するためNG | 肌にハリを与える、キメを整える |
例えば、化粧品のパッケージやLPに「ニキビを改善」と書いてしまえば、行政指導や広告差し止めの対象になる可能性があります。正しくは「ニキビを防ぐ」「肌を清浄にする」「フケやかゆみを防ぐ」といった緩やかな表現にとどめましょう。広告を制作する際は「治療目的の言葉になっていないか?」を基準にチェックしていくのが重要です。
(参考:厚生労働省|医薬品等の広告規制について)
「安心・安全」「永久」など保証を示す表現
「絶対に安全」「副作用はない」「永久に効果が続く」など、効果や安全性を保証する表現はNGです。どんな化粧品でも、体質によってアレルギーや肌トラブルを起こす可能性はゼロではなく、保証表現は虚偽や誇大広告と判断されます。
もし広告に「安心・安全」と書き、実際にトラブルが起きれば、企業の信頼失墜だけでなく行政処分のリスクも高まります。
| NG表現例 | 禁止される理由 | OK表現例 |
| 絶対に安全 | 100%保証は誇大広告に該当 | アレルギーテスト済み(全ての方に刺激がないわけではありません) |
| 副作用はない | 副作用ゼロは断定できないためNG | 成分や製造工程の情報を開示 |
| 永久に効果が続く | 永久性は保証できないためNG | 継続使用で肌をすこやかに保つ |
| 完全に安心 | 全員に適用できる保証は不可 | 使用上の注意を明記してリスクを案内 |
安全を保証するような表現を行いたい場合は、代わりに「パッチテスト済み(すべての方に刺激が起きないわけではありません)」など注意文を併記する表現が必要です。つまり「保証」ではなく「配慮・検証の事実」を伝えるのが正しい広告表現となります。
(参考:東京都福祉保健局|医薬品等適正広告基準)
「No.1」「最高」など最大級表現
「世界一」「業界No.1」「最高の化粧水」といった最大級表現も原則禁止です。これらは客観的な調査データに基づき、調査機関名・調査年・範囲を明示しなければ景品表示法や薬機法違反とされるリスクがあります。
| NG表現例 | 禁止される理由 | OK表現例 |
| 世界一の化粧水 | 根拠なき最大級表現はNG | 「2023年〇〇調査に基づく売上1位(調査機関・期間を明記)」 |
| 業界No.1 | 客観的根拠がなければ違反 | 「〇〇ランキングで金賞受賞(主催団体・年を記載)」 |
| 最高の美容液 | 主観的表現は誤認を招く | 自社従来品比で浸透力が向上 |
例えば「売上No.1」と広告する場合は「2023年〇〇調査に基づく国内売上データ」と明記する必要があります。根拠がなければ虚偽・誇大広告とみなされ、行政指導や課徴金の対象になります。
比較表現を用いる場合は「自社従来品との比較」に限定し、他社を直接的に貶める表現は避けましょう。実務では「No.1表記に根拠資料を添付しているか」を社内のチェックリストに組み込むのが有効です。
医師や専門家による推薦コメントや体験談の禁止
「医師が推奨」「皮膚科医も愛用」といった専門家推薦は、消費者に過度な信頼を与えるため薬機法違反となる可能性があります。さらに「著名人の体験談」も、個人の感想であっても「効果が必ず得られる」と誤認させればNGです。たとえば「使って3日でシミが消えた」という体験談を広告に載せると、医薬品的効能を暗示してしまいます。
| NG表現例 | 禁止される理由 | OK表現例 |
| 医師が推奨 | 消費者に過度な信頼を与える | 根拠ある学術データを提示しつつ、中立的に記載 |
| 皮膚科医も愛用 | 使用事実だけでは誤認を招く | 「専門家監修のもと開発」など実態を明示 |
| ○日で効果を実感 | 即効性の保証は誇大広告にあたる | 「継続使用で肌にうるおいを与える」 |
OKな例は「個人の感想であり、効果を保証するものではありません」と明記しつつ、効能に踏み込みすぎない範囲に限定することです。インフルエンサーマーケティングが主流の今、特に注意が必要な領域です。
使用前後の写真やビフォーアフター表現
「使用前はシワだらけ → 使用後はシワが消える」といったビフォーアフター写真は、効果を誇大に伝える典型的なNG表現です。消費者は写真の変化を「誰でも必ず効果がある」と受け止めてしまうため、薬機法第66条の誇大広告禁止に抵触します。
| NG表現例 | 禁止される理由 | OK表現例 |
| 使用前:シワだらけ → 使用後:シワが消える | 効果を断定的に示し誤認を招く | メイクアップ効果による変化として注記 |
| たるみ改善の比較写真 | 治療効果を暗示するためNG | 「肌を引き締める印象を与える」 |
| シミが薄くなった画像 | 医薬品的効能を示すためNG | 「透明感のある肌に見せるメイクアップ効果」 |
どうしても写真を使用する場合は「メイクアップ効果による表現です」といった注記が必要ですが、根本的な改善を示す表現は避けましょう。特に通販やSNS広告では誤認を招きやすいため、実務的には「ビフォーアフターは使わない」という形を取るのが安全策です。
ユーザーの不安を煽る表現
「放っておくと肌が老化する」「この化粧水を使わないと将来シワだらけに」といった不安を過度に煽る広告表現は、薬機法や景品表示法で問題となります。消費者に「使わないと危険」と誤認させ、過度な期待や恐怖感を与える点が問題視されるためです。
特に化粧品はあくまで「美化・清潔・魅力を増す」ためのものであり、医薬品のように「病気を防ぐ/治す」目的を持たないため、不安を根拠に訴求することは認められていません。
| NG表現例 | 禁止される理由 | OK表現例 |
| 「このままではシミがどんどん広がります」 | 恐怖心を煽り、使用を強制する印象を与える | 「紫外線による乾燥を防ぎ、肌を守ります」 |
| 「放置すると将来シワだらけに」 | 医薬品的な予防効果を暗示するためNG | 「乾燥小ジワを目立たなくする(効能効果56項目に基づく)」 |
| 「これを使わないと老化が進行します」 | 不安を利用した断定的表現で誤認を招く | 「肌にハリを与え、若々しい印象へ」 |
| 「毛穴を放置すると肌荒れが悪化」 | 治療効果を暗示する医薬品的効能に該当 | 「肌を引き締めてなめらかな肌へ導きます」 |
ユーザーの不安や恐怖を直接煽る表現はNGであるため、代わりに「乾燥から守る」「肌を整える」といった前向きな美容効果に置き換えるのが適切です。特にSNSやLPのキャッチコピーでは「煽り表現」が好まれがちですが、薬機法チェックの観点ではリスクが高いため注意しましょう。
化粧品の薬機法チェックは弁護士に相談するのが確実
薬機法は化粧品広告の表現からパッケージ記載、販売方法に至るまで広く規制しています。違反が発覚すれば、広告差し止めや行政指導、悪質な場合は業務停止や刑事罰にまで発展するリスクがあります。
過去には美容液などを販売するEC事業者に対し、特定商取引法に基づき9か月間の業務停止となった事例もあります。広告で「シミが99.9%消える」「シミが完全に消滅!」「どんな人でも3日でシミが消える」などと表示し、行政処置が行われました。(参考:消費者庁|通信販売業者【HappyLifeBio】に対する行政処分について)
社内でチェックリストを整備することも大切ですが、最も確実なのは薬機法に精通した弁護士によるリーガルチェックを受けることです。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、実際の審査例を公式HPにて公開しており、下記のような具体的な審査を行ってくれます。リスクの度合いと、修正案、さらに修正理由までフィードバックしてもらえるため、再発防止にもなり安心です。
“「美容液が肌の奥まで浸透します」
リスク度:★★
修正案:「美容液が肌の角質層まで浸透します」
修正理由:肌への浸透表現をする場合には、角質層までであることを明記する必要があります。「肌の奥」という表現は、角質層の範囲を越えて浸透する印象を与えるため不適切となります。(引用:2022年7月コラム紹介メルマガでご紹介した薬機法広告表現NG例と言い換え表現例をご紹介します。)”
薬機法は年々規制が厳しくなっているため、上記のような事前の広告チェックから事後対応まで一貫して任せられる体制を整えることが重要です。丸の内ソレイユのような薬機法に強い法律事務所に依頼すれば、安心して販促活動を進められ、ビジネスの成長も守ることができます。
弁護士への広告審査のご相談はこちらでお受けしておりますので、ぜひご確認ください。
化粧品関連で薬機法違反となった場合のリスク
化粧品の広告で薬機法に違反すると、単なる修正指導にとどまらず、企業活動全体に大きな影響を及ぼします。行政処分や罰則だけでなく、ブランド毀損や顧客離れといった長期的なダメージも避けられません。特に近年は消費者庁や厚労省がウェブ広告・SNS投稿を重点的に監視しているため、小規模事業者や個人でも摘発されるリスクがあります。
違反によって発生する主なリスクを以下にまとめました。
| リスクの種類 | 具体的な内容 | 想定される影響 |
| 行政処分 | 改善指導、課徴金、業務停止命令、販売禁止 | 一定期間販売できず売上が大幅減少 |
| 刑事罰 | 悪質なケースでは罰金刑や拘禁刑 | 経営者・責任者個人の責任追及 |
| 返金・回収 | 消費者への返金対応や商品回収命令 | 多額のコスト負担、在庫廃棄 |
| ブランド毀損 | 違反事例として報道・拡散される | 信頼失墜、長期的な売上低下 |
| 取引停止 | 取引先や広告代理店から契約解除 | 販売チャネル喪失、再構築に時間がかかる |
(参考:厚生労働省|課徴金制度の導入について)
例えば、過去には美容液の誇大広告で「シミが消える」とうたったEC事業者が業務停止命令を受けた事例があります。行政処分の事実は公表されるため、顧客だけでなく業界関係者からの信頼も大きく損なわれます。
つまり、薬機法違反は「一時的な広告の問題」ではなく、企業経営そのものに直結する重大リスクです。違反を未然に防ぐためには、社内ガイドラインの整備や弁護士によるリーガルチェックを日常的に取り入れることが欠かせません。
薬機法と化粧品広告に関するよくある質問
天然成分100%は広告で使っても大丈夫?
「天然成分100%」「完全無添加」といった表現は、消費者に誤認を与えるおそれがあるため慎重に扱う必要があります。100%を証明できる客観的データがなければ誇大広告とみなされるリスクがあり、景品表示法違反にもつながります。使う場合は、具体的に「防腐剤無添加」「植物由来成分を配合」と限定的に記載するのが安全です。
”商品に配合している成分中、特に訴求したい成分のみを目立つように表示すること。
①「植物成分」「植物抽出物」「天然植物エキス」等は OK。
②「生薬エキス」「薬草抽出物」「薬用植物エキス」の様に「薬」のつくものや、「漢方成分抽出物」のように医薬品という印象をあたえるものは禁止。(引用:一般財団法人ニッセンケン品質評価センター|化粧品の定義・広告表現に関する規制)”
海外化粧品を輸入して販売するときの注意点は?
海外で販売されている化粧品をそのまま日本で売ることはできません。輸入化粧品は日本の薬機法に基づき「化粧品製造販売業許可」を取得した業者が輸入し、成分や表示を日本の基準に合わせて確認・修正する必要があります。
“化粧品を輸入し販売するには、化粧品製造販売業許可が必要です。製造販売業許可は、販売しようとする事業所(総括製造販売責任者の所在する事務所)所在地の都道府県薬務主管課に申請します(法第12条)。(引用:ジェトロ 日本貿易振興機構『化粧品の輸入手続き:日本』)”
さらに、広告表現も日本の薬機法に準拠することが必須です。海外で使われている「美白効果」「しわ改善」などの表現は、日本ではNGとなるケースが多いため、必ず国内向けにリーガルチェックを行いましょう。
化粧品の製造基準や使用期限も薬機法の対象になる?
化粧品は「化粧品基準」に従って製造されなければならず、成分配合の規制や製造管理方法も薬機法の対象です。また、パッケージに全成分表示・販売名・製造販売業者情報を記載する義務があります。使用期限についても、未開封で3年を超えて品質が安定する製品以外は必ず表示が必要です。これらを怠れば表示違反として行政指導や回収命令の対象になります。
(参考:化粧品工業会|化粧品と医薬品医療機器等法)
まとめ|薬機法を理解して安全な化粧品広告を目指そう
化粧品の広告は、ちょっとした言葉選びが薬機法違反につながる非常にデリケートな領域です。「治る」「改善」といった医薬品的な表現や、「絶対安全」「No.1」といった誇大な表現は、消費者を誤認させるリスクがあるため厳しく規制されています。違反すれば、広告差し止めや行政処分だけでなく、企業の信頼やブランド価値を損なう結果にもつながります。
安全で効果的な広告を実現するには、薬機法のルールを正しく理解し、NG表現を避けるだけでなく、承認された範囲内で魅力を伝える工夫が欠かせません。社内チェックリストやAIツールも有効ですが、最も確実なのは弁護士によるリーガルチェックを取り入れることです。
薬機法に関する広告表現のチェックや運用体制づくりに不安がある方は、専門知識を有する弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。実際の行政処分事例を踏まえた具体的な改善提案を行い、貴社のビジネスを安心して成長させるための強力なサポートを提供します。

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。