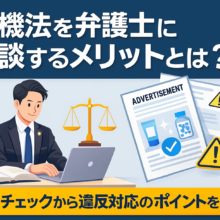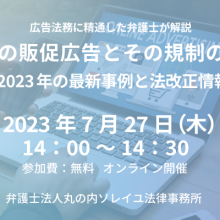「健康食品をネットで販売しているけれど、薬機法に違反していないか不安…」
「商品LP(ランディングページ)やブログ記事で“効能”をうたってしまっていないか心配…」
健康食品の広告や販売を行っていると、薬機法の規制がどこまで及ぶのか分かりづらく、不安になることがあります。特に医薬品的な効能・効果の宣伝ではないと思って書いた表現が、実は医薬品的効能の宣伝とみなされ、行政指導や販売停止につながるケースもありうるところです。
本記事では、薬機法における健康食品の定義と、広告で注意すべきNGワード・表現ルールを分かりやすく解説します。この記事を読むことで、健康食品の広告表現で避けるべきキーワードや、医薬品的効果効能の表現の境界線を理解し、法令違反によるリスクを未然に防ぐ方法が身につくはずです。
もし、薬機法対応の広告チェックやコンテンツ監修を安心して任せたい場合は、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所へご相談ください。医薬品・健康食品・化粧品業界に特化した法務支援を行っています。
広告表現の事前チェック、LPや記事コンテンツの監修、行政対応のアドバイスなどを一貫してサポートし、薬機法違反による販売停止やブランド毀損のリスクを回避します。
薬機法における健康食品の定義
健康食品という言葉は私たちの生活に浸透していますが、実は法律上の明確な定義は存在しません。
薬機法は医薬品・医薬部外品・化粧品などを規定していますが、「健康食品」という区分はなく、販売や広告を行う際には食品としてのルール、あるいは医薬品の規制が適用されるかどうかを個別に判断する必要があります。
「健康食品」という名称は便宜的な呼び方にすぎず、実際の商品は、法的には「食品」または「保健機能食品」に含まれます。そのため「健康食品だから薬機法の対象外」とは限らず、広告表現によっては医薬品とみなされる場合があります。
特に「治療」「予防」「改善」といった効能をうたった場合、薬機法上は医薬品扱いとなり、行政指導や販売停止命令、罰則(懲役・罰金)の対象となる可能性がある点に注意が必要です。
ここでは、健康食品の位置づけを理解するために、以下の3つの観点を押さえておきましょう。
- 「いわゆる健康食品」とは何か
- 医薬品・医薬部外品・食品との違い
- 健康食品の中で法的に認められている保健機能食品の種類
「いわゆる健康食品」とは?
一般的に「健康食品」と呼ばれるものは、健康の保持増進に役立つとされる食品全般を指す通称です。
“「いわゆる健康食品」と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指しているものです。(引用:厚生労働省|いわゆる「健康食品」のホームページ)”
法律上は統一された定義がなく、サプリメント・青汁・酵素ドリンク・プロテイン・ビタミン剤・ハーブティーなど幅広い商品が含まれます。
健康食品の具体例
- サプリメント(ビタミン・ミネラル)
- 青汁・酵素ドリンク
- プロテイン
- ハーブティー
- コラーゲンドリンク
ただし、健康食品であっても、「血圧を下げる」「糖尿病を改善する」など疾病への効能を表示した場合、薬機法上の医薬品扱いになります。表現ひとつで法的区分が変わるため、広告・パッケージの文言には注意が必要です。
(参考:厚生労働省|医薬品の範囲に関する基準の一部改正について)
医薬品・医薬部外品・食品との違い
薬機法では、製品を「医薬品/医薬部外品/化粧品/食品」のいずれかに分類して管理します。健康食品は法律上「食品」に含まれますが、広告や表示内容によっては医薬品扱いになる場合があります。
| 区分 | 主な目的 | 効能効果の範囲 | 承認・届出 |
| 医薬品 | 疾病の診断・治療・予防 | 体の構造・機能に直接作用し、治療・改善を目的とする | 厚生労働省の承認必須 |
| 医薬部外品 | 医薬品ほど強くないが、特定の予防・衛生効果を持つ | 美白・育毛・防臭・抗炎症など限定的な効能 | 厚労省の承認 |
| 化粧品 | 清潔・美化・外観保持 | 効果はごく限定的(保湿・整肌など) | 届出 |
| 食品(健康食品を含む) | 栄養補給・健康維持 | 基本的に効能効果を表示できない | 食品表示法に従う |
健康食品は本来「食品」扱いのため、医薬品レベルの効能効果を表示すると、薬機法違反になる可能性が高くなるため注意が必要です。
さらに、健康食品は制度上の「保健機能食品(特定保健用食品(トクホ)・機能性表示食品・栄養機能食品)」か、単なる「いわゆる健康食品」かを区別したうえで、表現の許容範囲を把握することが重要です。特定保健用食品(トクホ)は国が安全性・有効性を個別に審査し、「おなかの調子を整える」「コレステロールの吸収を抑える」など、特定の効能・効果を表示できるようになります。
(参考:消費者庁|保健機能食品について)
関連記事:薬機法における医薬品とは?定義・販売規制・広告ルールを徹底解説
関連記事:薬機法と医薬部外品の規制範囲とは?定義・効能効果・広告表現のポイントを解説
健康食品の中に含まれる保健機能食品の種類
「健康食品」のうち、一定の科学的根拠や国の審査を経て表示が認められるものを保健機能食品と呼びます。保健機能食品には以下の3つの種類があります。
| 区分 | 概要 | 表示できる内容 | 届出・許可 |
| 特定保健用食品 | 国が個別に有効性・安全性を審査し許可 | 「コレステロールの吸収を抑える」「おなかの調子を整える」など | 消費者庁長官の許可 |
| 機能性表示食品 | 事業者が科学的根拠を示して届出 | 「目のピント調節を助ける」「肌の弾力を保つ」など | 消費者庁への届出 |
| 栄養機能食品 | 一定のビタミン・ミネラルを含む食品 | 「ビタミンCは皮膚や粘膜の健康維持に役立つ」など | 基準を満たせば届出不要 |
薬機法上この3種類を把握する必要がある理由としては、広告やパッケージの表現を検討する際に、制度ごとに許容される範囲が大きく異なるからです。
たとえば同じ「コレステロール」に関する訴求でも、消費者庁長官の許可を得ている場合、トクホは「吸収を抑える」と表示できますが、一般の健康食品では「下げる」「改善する」といった表現は薬機法違反になります。機能性表示食品では届出通りの効果効能以外は表現できません。
薬機法と健康食品広告の規制ルール
健康食品は「食品」に分類されるため、基本的には薬機法の医薬品広告規制を受けません。
しかし、広告表現や商品説明が医薬品的な効能効果をうたっていると判断される場合、薬機法の規制対象となり、違反として行政指導や業務停止などの処分を受ける可能性があります。薬機法違反にならないために、以下の規制ルールを把握しておきましょう。
医薬品的効能を示す表現の禁止
薬機法では、医薬品でない製品に対して疾病の治療・予防・改善を目的とする表現を広告することを禁止しています。健康食品の広告で以下のような文言を使うと、医薬品と判断されるリスクがあります。
| 禁止される表現の例 | 理由 |
| 「糖尿病を改善する」 | 疾病の治療を連想させる |
| 「血圧を下げる」「コレステロールを減らす」 | 身体機能に直接作用する医薬品効能 |
| 「花粉症を予防する」「風邪を治す」 | 疾病予防をうたっている |
| 「関節痛をなくす」「がんを治す」 | 医薬品的治療効果を断定 |
特に「改善」「治す」「予防」などの表現は、医薬品効能とみなされる典型例です。
健康食品でこれらを使用すると薬機法違反と判断される可能性が非常に高いため、広告では避ける必要があります。
一方で、「機能をサポートする」「健康を維持する」程度の表現なら基本的に食品として許容されやすいため、言い換え表現のチェックリストを作成しておくのが賢明です。
(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について)
関連記事:薬機法における医薬品とは?定義・販売規制・広告ルールを徹底解説
誇大広告やNGワードの禁止
薬機法第66条では、医薬品等の広告において虚偽・誇大な広告を禁止しています。健康食品でも、あたかも医薬品のような効果を保証するかのような表現はNGです。
NGとなる代表的な広告パターン
- 効果を断定する表現:「必ず痩せる」「飲むだけで改善する」
- 科学的根拠がないデータや比較表現:「医師が推薦」「学会が認めた」など、実態がない主張
- 消費者を誤解させる体験談の強調:「これを飲んだだけで糖尿病が治りました!」などの体験談を広告目的で利用する
- 極端なビフォーアフター写真:医薬品的効果を印象づける写真や加工画像
実際に消費者庁は健康食品等の表示監視を行っており、改善指導が入った事例もあります。
“108事業者が販売する157商品について、健康増進法に違反するおそれのある虚偽・誇大な表現が確認されたとして、表示の改善指導を行ったとしている。対象となった表示には、「がん予防」「認知症予防」「高血圧対策」「美白効果」など、科学的根拠が乏しい健康保持増進効果をうたうものが多数含まれていたという。(引用:消費者庁、157商品で虚偽・誇大表示か 健康食品のネット広告に改善指導)”
虚偽・誇大な広告は薬機法だけでなく、複数の法律に同時に抵触する可能性があります。虚偽・誇大な広告は、景品表示法や健康増進法にも反する可能性があるため、注意が必要です。
薬機法と健康食品広告のNGワードと言い換え一覧
健康食品の広告では、医薬品的な効能や安全性を断定する表現が薬機法に抵触する恐れがあります。
特にネット広告やLP、記事コンテンツは監視が強化されており、「気づかずに使った言葉」で違反になるケースが増えています。
ここでは、健康食品広告で避けるべき代表的なNGワードと、安全な代替表現(言い換え)を一覧で解説します。広告や記事作成時のチェックリストとして活用してください。
関連記事:薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法
疾病の治療や予防を示す禁止表現
薬機法では、食品に病気の治療・予防を目的とする表現を一切認めていません。健康食品において「病気を治す」「○○を予防する」といった文言を使うと、たとえ成分が食品レベルであっても医薬品とみなされ、薬機法違反となります。
広告制作時には、「健康維持」「体調サポート」など食品として許される範囲の表現にとどめることが重要です。近年はネット広告やLP、SNS投稿まで監視が広がっており、無意識のうちに使った表現でも違反に問われるケースがあります。
身体の機能改善を強調しすぎる危険なフレーズ
食品が人体の機能を直接改善するかのような断定的な表現も、薬機法では医薬品の効能とみなされる可能性があります。特に血圧・血糖値・免疫など、医療的な数値や体内機能の変化を想起させる表現は要注意です。
安全な表現としては「健康サポート」など、あくまで生活習慣や体調管理を支えるサポートの位置付けであることを明示するのがポイントです。
効果を断定する言葉
健康食品で「必ず」「劇的に」などの効果保証を断定する表現は、薬機法第66条の誇大広告禁止に抵触します。特にユーザーの期待を過剰にあおるワードは行政から指摘されやすく、特定保健用食品のように科学的根拠があっても、効果を保証する言い回しはNGです。
| NGワード例 | 言い換え例 |
| 「絶対に痩せる」 | 「ダイエットをサポート」 |
| 「飲むだけで改善」 | 「健康習慣の一部として役立つ」 |
| 「劇的に若返る」 | 「エイジングケアをサポート」 |
広告作成時は、「サポートする」「健康習慣の一部として」など、効果を保証しない言い回しに置き換えることが必須です。実感の差や生活習慣の影響を示すことで、誇大広告と判断されるリスクを減らせます。
安全性を過度に保証する表現
安全性に関しても、「副作用ゼロ」「絶対に安全」などの断定表現は違反とされることがあります。特に健康被害のリスクを軽視させるような表現は消費者保護の観点からも厳しく監視されています。
| NGワード例 | 言い換え例 |
| 「副作用が一切ない」 | 「安全性に配慮して製造」 |
| 「100%安全」 | 「品質管理を徹底」 |
| 「赤ちゃんでも安心」 | 「幅広い世代の方にご利用いただけます(※使用前に医師へ相談推奨)または (※使用前に医師へ相談してください)」 |
| 「どれだけ飲んでも大丈夫」 | 「用量を守ってお使いください」 |
特に「赤ちゃんでも安心」「どれだけ飲んでも大丈夫」といった表現は、摂取量や体質によりリスクがある可能性を無視していると判断されます。
安全な代替表現としては「品質管理を徹底」「安全性に配慮して製造」「幅広い世代に向けた商品(使用前に医師相談を推奨)」など、過度な安心感を与えない工夫が求められます。
権威づけに頼った誤認リスクのある表現
医師・専門家・公的機関の名前を使って権威づけを行う広告も、消費者を誤解させるためNGとなる場合があります。とくに根拠なく「医師推奨」「厚生労働省認可」などと記載するのは危険です。
| NGワード例 | 言い換え例 |
| 「医師が絶賛」 | 「専門家の知見を参考に開発」 |
| 「厚生労働省認可」 | 「品質管理基準に沿って製造」 |
| 「学会が推薦」 | 「研究成果をもとに開発」 |
| 「テレビで紹介された」 | 「メディアで取り上げられました(番組名・放送日を明記)」 |
また「テレビで紹介された」という表現も、放送内容や番組名を明示しなければ誤認を招く恐れがあります。安全な代替としては「専門家の知見を参考に開発」「品質管理基準に沿って製造」「メディアで紹介されました(番組名・放送日を記載)」のように、事実ベースで透明性を担保する表現を心がけましょう。
健康食品の広告で薬機法違反を防ぐチェック方法
健康食品の広告は、医薬品的な効能表現を避けることが基本ですが、実際には「どこまでがOKか」の判断が難しいケースが多くあります。
ここでは、薬機法違反を防ぐために広告担当者が自社で行えるチェック方法と、最終的に専門家へ相談すべきポイントを整理します。
1.保健機能食品と「いわゆる健康食品」でルールを分けて確認する
まず広告を作る前に、自社の商品が「保健機能食品」か、それとも一般的な「いわゆる健康食品」かを明確に分けて考えることが重要です。
| 区分 | 制度の有無・根拠 | 表示できる内容 | 広告時の注意点 |
| 保健機能食品(特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品) | 国や消費者庁が定める制度に基づき、審査・届出が必要 | ・特定保健用食品:国の許可を得た範囲で「コレステロールの吸収を抑える」などの機能表示が可能 ・機能性表示食品:事業者が科学的根拠を示して届出した範囲の機能を表示できる ・栄養機能食品:所定のビタミン・ミネラルに関する定型文の表示が可能 | ・制度で認められた範囲を逸脱しない ・「治療・予防」など医薬品的効能は表示不可 ・届出や許可内容と異なる文言の使用はNG |
| いわゆる健康食品 | 法的な制度なし(一般食品扱い) | 「健康を維持する」「栄養補給をサポートする」など一般的な健康サポート表現のみ | ・効能効果を直接的にうたうと薬機法違反 ・「改善」「予防」「治す」など医薬品的表現は禁止 ・過剰な期待を与えない表現を心がける |
(参考:厚生労働省|1) 健康食品やサプリメントの名称について)
保健機能食品(特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品)は、国や消費者庁が定める制度に基づき、一定の範囲内で機能表示が許可または届出されています。たとえば特定保健用食品は「コレステロールの吸収を抑える」などの機能をうたうことが可能ですが、疾病の治療・予防を目的とする表現は認められません。
一方、制度に属さない「いわゆる健康食品」は、基本的に効能効果を直接的に示すことができず、「健康を維持する」「栄養補給をサポートする」などの範囲にとどめる必要があります。
まずは自社商品がどちらに属するかを整理し、それに応じて広告表現を判断することが、薬機法違反を防ぐ第一歩です。
2.薬機法と食品表示法の二重チェックを行う
広告表現を考える際は、薬機法だけでなく食品表示法の観点からもダブルチェックを行うことが必須です。
広告作成時の推奨フロー
- 薬機法チェック:医薬品的効能・効果の表現がないかを確認
- 食品表示法チェック:原材料や成分表示が正確であるかを確認
薬機法は広告の観点からすると「医薬品的な効能効果をうたっていないか」を監視していますが、食品表示法は「原材料や栄養成分の表示」などを規制しています。
たとえば、薬機法的には問題がなくても、食品表示法のルールを守らないと「表示の虚偽・誤解を招く表現」として行政指導の対象になることがあります。機能性表示食品では、事前届出した範囲外の表現を広告に記載することはNGです。
広告を作成したら、まず薬機法の観点(効能・効果表現の有無)、次に食品表示法の観点(届出内容・原材料表示との整合性)を順番にチェックする習慣をつけましょう。二重の視点で確認することで、リスクを大幅に減らせます。
3.不安な点は専門家や弁護士に依頼して審査を受ける
最終的に、判断が難しい表現やグレーゾーンの文言がある場合は、薬機法に精通した専門家や弁護士に確認を依頼するのが安全です。特に以下のようなケースでは、専門的な審査を受けることをおすすめします。
- 効能表現をどこまで使えるか迷っている
- 新商品の広告やLPを初めて作成する
- ネット広告(リスティング・SNS)で大規模に出稿する予定がある
- 消費者庁や厚生労働省からの行政指導を受けた経験がある
弁護士に依頼すれば、薬機法だけでなく景品表示法や食品表示法も含めて総合的な観点からチェックしてもらえます。行政処分や販売停止によるダメージは非常に大きいため、事前に専門家のレビューを受けておくことがリスク回避の近道です。
関連記事:薬機法を弁護士に相談するメリットとは?広告チェックから違反対応のポイントを解説
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法対応の広告チェック・コンテンツ監修について、健康食品・化粧品・医薬品業界の広告に精通した弁護士が、事前の表現チェックから行政対応のアドバイスまで一貫してサポートしています。
公式HPでは実際の違反事例も紹介しています。
グレーな表現や新しい広告企画に不安がある場合も、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。
薬機法に関する弁護士へのご相談はこちらまでお寄せください。
薬機法以外に健康食品で守るべき広告規制
健康食品の広告を適法に展開するためには、薬機法のみならず、景品表示法や健康増進法(虚偽・誇大表示の禁止)といった法律も規制対象になります。
これらはそれぞれ規制の複数法規が同時に適用されるため、「薬機法さえ守っていれば安全」というわけではありません。
| 法律 | 規制の対象 | 主な目的・ポイント | 違反時の主なリスク |
| 薬機法 | 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの製造・販売・広告 | 医薬品的な効能・効果の標榜を禁止。食品が「治療・予防・改善」をうたうと違反 | 行政指導・業務停止命令・許可の取消し・課徴金納付命令(売り上げの4.5%相当)・刑事罰(2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金など) |
| 景品表示法 | 商品・サービスの表示や広告全般 | 優良誤認・有利誤認を防止。実際より著しく優良・有利に見せる広告を禁止 | 措置命令・課徴金納付命令(売上の3%相当)・公表による信用失墜 |
| 健康増進法 | 食品の表示や広告(特に健康効果に関する表示) | 健康保持増進効果の虚偽・誇大表示を禁止。科学的根拠がない健康効果の主張を規制 | 行政指導・勧告・公表。刑事罰(6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
広告担当者は、薬機法との整合性だけでなく、景品表示法や健康増進法に抵触しないかどうか、広告文言・構成内容・訴求の仕方についてもチェックを行わなければなりません。以下でそれぞれの法律の目的・定義・適用範囲を確認しておきましょう。
関連記事:薬機法の広告規制とは?広告の定義・3要件・違反事例まとめ
景品表示法のルール
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、商品・サービスの表示や景品提供を通じて、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する行為を規制することを目的としています。
具体的には、景品表示法は「不当表示(虚偽表示・誇大表示など)」と「景品類の過大提供」を禁止します。
「表示」については、法律第2条4項において、“「顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う広告その他の表示」(引用:e-Gov 法令検索|不当景品類及び不当表示防止法)”と定義されており、チラシ・パンフレット・ウェブ広告・SNS投稿などが含まれます。
つまり、健康食品の広告で「実際より優良である」「有利である」と消費者に誤認させる表示(優良誤認・有利誤認表示)は禁止されます。その場合、事業者に対して措置命令や課徴金が科される可能性があります。
健康食品広告では、商品の効能や価格面で誤認を誘うような訴求をせず、事実に即した説明と根拠の提示が不可欠です。
健康増進法のルール
健康増進法は、国民の健康保持・増進を目的とし、その枠内で虚偽・誇大な表示を抑制する規定を持っています。広告として表示される健康保持効果に関して、著しく事実に相違する表示、または著しく人を誤認させる表示をしてはならないと定められています。
特に、健康増進法第65条第1項には以下の条文があります。
“何人も、食品として販売するものに関し、健康の保持増進効果等について、著しく事実に相違する表示を行い、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。(引用:誇大表示の禁止(健康増進法第65条第1項))”
この規定により、広告で「血圧を大きく下げる」「がんを予防する」など誇張された訴求を行うことは禁止されます。また、健康食品におけるインターネット広告やLPもその「広告その他の表示」に含まれるため、オンライン上での過剰な効能・表示は監視対象となります。
さらに、消費者庁は、これらの虚偽誇大表示について、事業者に対する指導を行っています。
健康食品の広告を出す際には、薬機法のみならず、景品表示法・健康増進法の規制枠内で表現をコントロールすることが必須です。誤った表現は、行政指導、改善命令、最悪の場合は罰則や課徴金の対象となるリスクがあります。
薬機法と健康食品に関する質問
ビフォーアフターの写真は使える?
ビフォーアフター写真は基本的にリスクが高く、注意が必要です。薬機法では医薬品でない製品に対して「効能・効果を示す広告」を禁止しており、写真によって体の変化を暗示する場合も効能効果の訴求と判断されることがあります。
厚生労働省は「医薬品等の広告においては、使用前、使用後の対比により効果があるように誤認させる表示をしてはならない。」と定めています。
特に健康食品の場合、体重減少・シワ改善・肌質変化などを写真で表現すると「医薬品的効能の暗示」とみなされやすくなります。
たとえば、美容やダイエット系の広告では、写真の使用自体を避けるか、効果を断定しないナチュラルなイメージ写真にとどめるのが安全です。仮に「個人の感想」「効果には個人差があります」と添えても、誇大広告や誤認を与えると判断されれば違反とされることがあります。
(参考:東京都保健医療局|医薬品的な効能効果について – 健康食品)
「個人の感想です」を付ければ広告規制を回避できる?
「個人の感想です」と明記しても、薬機法・景品表示法の規制は回避できません。消費者が誤認する可能性のある表現を広告として用いた場合、たとえ体験談やレビューの形式であっても規制対象となります。
消費者庁の「打消し表示に関する実態調査報告書」より、「『個人の感想です』『効果には個人差があります』等の表示を行っても、表示全体から消費者が受ける印象によっては不当表示と判断される場合がある」との内容記述があります。
そのため、こうした注意書きを付けても免責にはならず、薬機法や景品表示法の違反リスクは残ります。体験談を広告に使う際は、科学的根拠がない効果を断定しない・医薬品的効能をうたわないように注意する必要があります。
海外論文を根拠に広告で訴求できる?
海外の論文を根拠に広告で効能を訴求することは基本的に認められていません。
日本の薬機法や健康増進法では、広告の根拠となるデータは「国内で流通する商品に対して、信頼性の高い科学的根拠があること」が求められます。海外論文の情報をそのまま製品の効果として宣伝するのは不当表示と判断されるリスクがあります。
消費者庁の「機能性表示食品の届出ガイドライン」より、「海外の研究結果を根拠とする場合であっても、当該製品と同一性が確認できない場合や、日本人を対象とした科学的根拠がない場合は、表示の根拠として不十分である」との内容が記載されています。
特に健康食品の広告では、「海外では〇〇に効くとされている」などの文言をそのまま使用すると、事実と異なる印象を与えかねず薬機法違反・景品表示法違反のリスクがあります。
どうしても科学的データを示す場合は、国内外の論文を参考にしつつ、自社商品の成分・用量に即した根拠があるかどうかを確認したうえで、専門家にレビューを依頼することが安全です。
まとめ|薬機法のチェックは弁護士に相談しよう
健康食品の広告は、単に「医薬品的な効能をうたわない」だけでは安全とはいえません。薬機法をはじめ、景品表示法や健康増進法など、複数の法律が同時に適用される可能性があります。
さらに、保健機能食品・いわゆる健康食品・一般食品といった区分ごとに許容される表現が異なり、ルールを誤ると行政指導や販売停止、最悪の場合は罰則の対象になることもあります。
特にネット広告やLP、SNSは監視が強化されており、知らないうちに使った「改善」「予防」「必ず」などの表現が違反と判断されるケースも増えています。広告担当者や事業者自身が全ての法律を把握してリスクを管理するのは容易ではありません。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景品表示法・健康増進法を横断的にチェックし、健康食品の広告表現が違反とならないかを事前に確認するサービスを提供しています。商品コンセプトやキャッチコピーの段階から相談することで、後からの修正コストや行政指導のリスクを減らすことが可能です。

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。