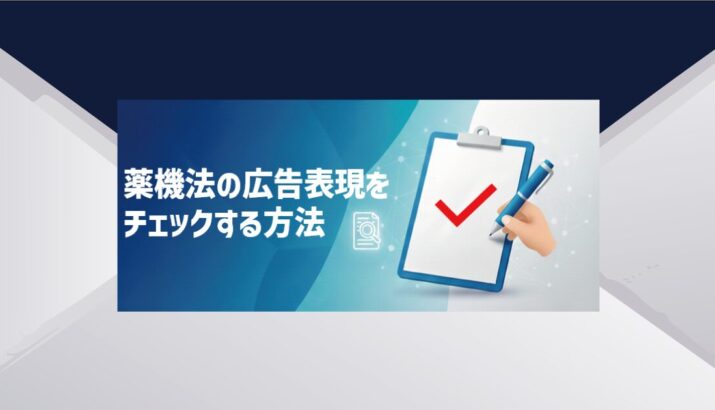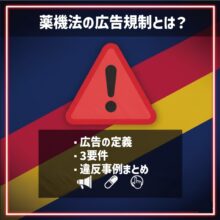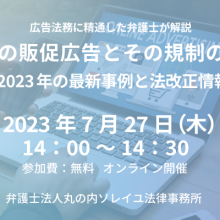「この広告コピーって薬機法的に大丈夫なのかな?」
「化粧品やサプリの説明文で、どこまで表現していいのか分からない…」
化粧品・健康食品・医薬部外品などを扱う広告担当者やライターにとって、薬機法における広告表現チェックは避けて通れないテーマです。
もしも誤った表現を掲載してしまえば、行政処分や売上の最大4.5%に相当する課徴金、さらに広告アカウント停止やブランドイメージ失墜といった経営上のリスクにつながります。
この記事では、薬機法で広告表現をチェックすべき理由をはじめ、NG例・言い換え方・便利なチェック方法までを徹底解説します。読了後には、「どうすれば違反を避けながら魅力的な表現ができるか」が明確になるはずです。
表現のチェックで判断が難しいケースや法的リスクが懸念される場合は、美容・健康分野に精通した弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所に相談するのがおすすめです。広告審査を1ページ単位から依頼でき、行政対応や契約書作成まで幅広くサポートしています。
薬機法で広告表現のチェックが必要な理由
薬機法の広告規制は単なるルールではなく、事業の継続やブランドの信頼を左右する重要な基準です。以下の観点から、広告表現チェックを徹底する必要があります。
また行政処分のリスクだけでなく、薬機法違反が疑われる表現は広告審査の段階でECプラットフォーム等から不承認となってしまう恐れがあります。つまり表現チェックを怠ると広告配信自体ができない可能性が高まるため、事前のチェックが必須です。
1.違法広告による罰則や行政指導を防ぐため
薬機法第66条では「虚偽・誇大広告の禁止」が定められており、違反すると業務停止命令・課徴金・刑事罰といった処分が下される可能性があります。たとえば「シワが必ず消える」「がんが治る」といった表現は科学的根拠がないため、厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」でも禁止されている典型例です。
さらに、広告の違反判断は単に言葉単体ではなく全体の印象で評価される点にも注意が必要です。丸の内ソレイユ法律事務所のコラムでも、「広告表現が法律に違反しているかどうかは、個々の表現ではなく、全体から受ける印象で判断されるということです」と解説されています(参考:丸の内ソレイユ法律事務所の|広告表現が法律に違反しているかどうかの判断手法)
たとえば「スッキリ」という言葉自体は曖昧ですが、体重計の写真や「ダイエット」という文脈と組み合わされると、痩身効果を暗示する広告とみなされる可能性があります。
こうした判断を誤ると、単なる注意では済まず、売上の最大4.5%に相当する課徴金や広告停止命令などの重い処分が科される事もありえます。
実際、飲むだけで痩せるかのように誤認させる表示を行った会社が、消費者庁から景品表示法違反により4,893万円の課徴金納付命令を受けています(参考:消費者庁|景品表示法に基づく措置命令・課徴金納付命令。なお、この件は薬機法違反ではなく景品表示法違反に基づくものとなります)。
したがって、表現チェックを徹底することは、法令遵守だけでなく企業の安全運営戦略としても不可欠なのです。
2.消費者を誤認させないため
広告の本来の目的は「商品の魅力を正しく伝えること」であり、消費者に誤解を与えてはなりません。薬機法違反の多くは、過度な効能効果の強調によって消費者を誤認させるケースです。
例えば、化粧品広告で「シミが完全に消える」と断定的に書くと、消費者は医薬品的な効果を期待して購入してしまいます。しかし化粧品は「人体に対する作用が緩和なもの」に限られており、法的に「シミが消える」という効能表現は認められていません。
誤認を防ぐためには、「シミが消える」→「日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ」といった代替表現を選ぶ必要があります。こうしたチェック体制を整えることは、消費者保護の観点からも欠かせません。
3.企業の信頼性・ブランド価値を守るため
薬機法違反は、単に法的処分にとどまらず、企業名が公表されることによるブランド毀損のリスクが大きいのが特徴です。消費者庁等は違反企業名を公式サイトで公開しており、検索すればすぐに企業名がヒットしてしまいます。
一般社団法人 全国公正取引協議会連合会が公開しているサイトでは、具体的な会社名・違反内容・課徴金額が毎週のように公表されています(参考:措置命令・課徴金納付命令・確約データベース)
一度失った信用を取り戻すのは容易ではありません。特に美容・健康業界は競合が多いため、「あの会社は薬機法違反をした」というイメージが付くだけで、消費者や取引先からの信頼を失い、長期的な売上に悪影響を及ぼします。広告表現のチェックは、単なるコンプライアンス対応ではなく、ブランディング戦略の一部として捉えるべきです。
したがって、広告表現のチェックは単なるコンプライアンス対応ではなく、ブランド価値を守るための「戦略的な投資」と捉える必要があります。薬機法を遵守する姿勢を示すことは、「この会社は信頼できる」という安心感につながり、長期的なファンづくりやリピーター獲得にも直結します。
4.広告媒体やプラットフォームの掲載基準に対応するため
Google広告やMeta広告(Facebook/Instagram)は、広告ポリシーの中で「誤解を招く健康効果の主張」を禁止しており、薬機法違反が疑われる表現は広告審査で不承認となります。(参考:Google広告ポリシー|ヘルスケアと医薬品)
たとえば「短期間で必ず痩せる」「シミが消える」といった断定的な効能効果を含む広告は、審査で落ちる典型例です。実際にソーシャルメディア広告でも、「医薬品的な効能を暗示する表現」はリスクが高く、配信停止やアカウント凍結につながることがあります。
また、アフィリエイトサービスプロバイダー(成果報酬型広告)でも薬機法違反が確認されると、即時に広告停止となるケースがあります。つまり、法的リスク回避だけでなく、実際に広告を配信するためにも表現チェックは必須です。
つまり広告表現のチェックは、単に法的リスクを回避するためだけでなく、実際に広告を配信するための前提条件になっています。薬機法を軽視すれば「広告を出すことすらできない」状況に直面することを覚えておきましょう。
関連記事:薬機法の広告規制とは?広告の定義・3要件・違反事例まとめ
薬機法チェックを怠った場合のペナルティとリスク事例
薬機法に違反した広告や販売行為は、行政指導から業務停止命令、課徴金、刑事罰までさまざまな処分を受ける可能性があります。とくに健康・美容領域の商品は消費者への影響が大きいため、監視が強化されているのが実情です。
主なペナルティの種類
- 行政指導・措置命令
表現の修正・広告差し止めだけでなく、再発防止措置を講じることや違反事実を消費者等に周知させるよう命じられる場合があります。 - 課徴金(売上の最大4.5%)
景品表示法違反とあわせて課徴金が科されることがあり、違反した広告による売上の最大4.5%が命じられます。 - 刑事罰
無許可販売や虚偽広告が悪質と判断された場合、拘禁刑や罰金などの刑事罰が科されることもあります。
実際に行政による処分を受けるだけでなく、プレスリリースやニュース報道を通じて企業名と違反内容が公表され、ブランドイメージの大きな毀損につながります。過去の事例では課徴金が1億円を超えた違反事例もあり、ネット上に残り続けるリスクを裏付けています。
“機能性表示食品のサプリメントで、科学的根拠が不十分であるにもかかわらず、「中性脂肪を低下させる機能」などと表示していたことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は3月19日、通販会社のさくらフォレスト(福岡市中央区)に対し、1億円超の課徴金を納付するよう命じたと発表した(引用:さくらフォレストに1億円超の課徴金…機能性表示食品の表示で景表法違反。なお、この件は薬機法違反ではなく景品表示法違反に基づくものとなります。)”
この事例が特に深刻なのは、課徴金の金額規模と行政処分の重さです。消費者庁が命じた課徴金は1億903万円と極めて高額でした。
上記の事例は薬機法の広告規制と直接の同時適用ではありませんが、医薬品的な効能表示は薬機法違反にもなり得るため、景品表示法と合わせて摘発されるリスクがあることを理解しておく必要があります。
【商品別】薬機法でチェックが必要な広告表現
薬機法では、商品ごとに広告表現の規制範囲や注意点が異なります。同じ「美白」や「健康サポート」という言葉であっても、化粧品なのか健康食品なのかによって、適法・違反のラインが変わるため注意が必要です。ここでは代表的な商品カテゴリごとに、チェックすべきポイントを整理します。
化粧品のチェックポイント
化粧品は「人体に対する作用が緩和なもの」と定義されており、医薬品的な効能表現はできません。たとえば「シミが消える」「シワが治る」といった表現はNGです。
チェックポイント例
- 「改善」「治す」など医薬品的な表現は禁止
- 「美白」「エイジングケア」はメークアップ効果等の許された範囲内であれば使用可
- ビフォーアフター写真や過度なイメージ暗示も違反リスクあり
| OK表現例 | NG表現例 |
| 肌にハリを与える | シワを治す |
| うるおいを保つ | 乾燥肌が完治する |
実務では「美白」「エイジングケア」といった人気キーワードで違反が起こりやすい傾向があります。たとえば、美容液や日焼け止めの広告では「シミが消える」という断定表現をしてしまうケースが多く、行政指導の対象になりやすい領域です。
また、まつ毛美容液やスカルプケア商材は「発毛・育毛」を連想させるコピーが出やすく、医薬品と誤解されるリスクが高まります。そのため、これらの商品では特に効能表現を慎重に精査することが重要です。
関連記事:薬機法と化粧品の広告規制とは?正しい表現ルールをわかりやすく解説
健康食品・サプリのチェックポイント
食品である以上、「疾病の治療・予防効果」を標ぼうすることは薬機法で明確に禁止されています。違反した場合は景品表示法や健康増進法とあわせて行政処分や課徴金命令の対象となります。
たとえば「免疫力が上がる」「糖尿病が治る」といった表現はNGです。特に健康食品は、景品表示法や健康増進法とあわせて注意しましょう。
チェックポイント例
- 「病気を治す・予防する」表現は禁止
- 「ダイエット」「免疫力アップ」といった表現も禁止
- 「機能性表示食品」は届出範囲内の表現に限定される
| OK表現例 | NG表現例 |
| 健康維持をサポート | 免疫力が上がる |
| 栄養補給に役立つ | 糖尿病が改善する |
| 健やかな生活のおともに | 飲むだけで痩せる |
健康食品は「ダイエット」「免疫力アップ」といった文言が最も誤解を招きやすく、違反リスクが突出して高いジャンルです。特に青汁・酵素ドリンク・ダイエットサプリは「飲むだけで痩せる」といった表現に発展しやすく、消費者庁からも景品表示法違反による課徴金命令の対象になってきました。
さらに、ビタミンサプリなどの栄養補助食品でも「風邪をひかなくなる」といった予防効果の訴求は薬機法違反に直結します。こうしたケースは「食品なのに医薬品的な効能を標ぼうしていないか」を徹底的にチェックすることが求められます。
薬機法は効能効果の表現を、景品表示法は「優良誤認」を、健康増進法は「虚偽・誇大表示」を規制している法律です。健康食品広告はこれら3法のセットで審査・監視の対象となるため、薬機法だけでなく他法も意識してチェックする必要があります。
医薬部外品のチェックポイント
医薬部外品はいわば、「医薬品と化粧品の中間」に位置する存在で、承認された範囲内の効能表現は可能です。ただし承認されていない効能を広告に使えば、薬機法違反となります。
チェックポイント例
- 薬用化粧品(美白・育毛・制汗など)は承認された効能のみ表示可能
- 承認外の効能を追加して書くのはNG
- 効能表現の強調や誇張表現もリスクあり
| OK表現例 | NG表現例 |
| フケ・かゆみを防ぐ(薬用シャンプー) | 薄毛が治る |
| 肌を清浄にする | ニキビが完全になくなる |
| 体臭・汗臭を防ぐ | 多汗症が治る |
医薬部外品は「薬用」の冠がつくことで広告表現が広がりますが、その分リスクも比例して増します。たとえば薬用美白化粧水では「シミを防ぐ(メラニンの生成を抑えシミそばかすを防ぐ)」は認められていても「シミを消す」はNGです。同様に、薬用育毛剤も「発毛促進」は可能でも「薄毛が治る」は許されません。実務では、この「承認されている効能」と「言い過ぎ表現」の線引きを誤りやすく、パッケージ・LP・チラシなど媒体を問わず違反の温床となりやすい領域です。そのため、必ず承認内容と表現を照合する作業を徹底する必要があります。
医療機器・雑貨のチェックポイント
医療機器は承認・認証を受けた範囲での効能効果表示が可能ですが、承認範囲を超えた表現は違反となります。雑貨については、「肩こりが治る」「疲労回復」など医薬品的な効能を標ぼうした時点で薬機法違反の対象になります。
チェックポイント例
- 医療機器:承認書に記載された効能のみ使用可能
- 家電・美容機器(美顔器・脱毛器など)は「使用感の表現」までが許容範囲
- 雑貨(健康グッズ)は「癒し」「リラックス」表現なら可
| OK表現例 | NG表現例 |
| リラックスできる | 疲労が回復する |
| 肌にうるおいを与える(美顔器) | シミが消える(医薬品的効能) |
| 使用感が心地よい | 肩こりが治る |
医療機器と雑貨の区別を誤るケースが実務で頻発しています。たとえば美顔器や家庭用脱毛器はあくまで「使用感」や「一時的な美容効果」の範囲しか認められませんが、「シミが消える」「永久脱毛」といった医薬品的・医療的な効能をうたってしまうと薬機法違反になります。
また、磁気ネックレスやリラクゼーショングッズなどの雑貨も「肩こり改善」「疲労回復」と表現した途端に規制対象となるため、誤解を招くコピーは特に注意が必要です。こうしたグレーな領域の商品は、弁護士など専門家への事前相談が有効です。
媒体別に見るべき薬機法のチェックポイント一覧
広告表現のリスクは、商品カテゴリだけでなく「どの媒体で発信するか」によっても変わります。同じコピーでも、リスティング広告では不承認になるのに、Webサイトでは掲載されてしまうケースがあるなど、媒体ごとにルールが異なるのです。実務では、媒体特性を理解してチェックすることが違反防止のカギとなります。
| 媒体 | チェックすべきポイント | 注意点・具体例 |
| Webサイト・LP | 効能効果の表現、ビフォーアフター画像、口コミ掲載 | 口コミや体験談に「治る」「痩せる」など医薬品的効能を含めると違反リスク大。全体の印象で判断されるため、画像や文脈の組み合わせにも注意。 |
| リスティング広告(Google・Yahoo!) | 見出し・説明文の一語一句 | 「絶対痩せる」「必ず治る」など誇大表現は即審査落ち。短文で強調しがちな媒体なので、表現を弱める工夫が必要(例:「健康維持をサポート」)。 |
| SNS投稿(Instagram・Xなど) | ハッシュタグ・キャプション、インフルエンサー発信 | 個人アカウントでも広告性がある場合は薬機法の規制対象。ステマ規制も加わり、PR表記なしや誤解を招く効果表現は行政指導のリスクあり。 |
| 紙媒体・チラシ | キャッチコピー、写真、レイアウト | 「医師推奨」「モニター調査で○%改善」などの表現は根拠がなければNG。小スペース広告ほど誇張表現に流れやすいため、特に注意が必要。 |
| 動画広告(YouTube・TVCMなど) | ナレーション、字幕、ビジュアル表現 | 動画は視覚・聴覚の両方から強い印象を与えるため、「効果の保証」に直結するリスクが高い。テロップや音声に「改善」「完治」などの言葉を入れるのは危険。 |
媒体ごとにチェックポイントが違うため、「どの商品を、どの媒体で、どんな表現をするか」を掛け合わせて確認することが重要です。特にWeb・LPは長文で曖昧な表現が積み重なるリスクがあり、リスティング広告は短文の中で断定表現に走りやすいという特徴があります。さらにSNSは個人発信でも規制対象となるため、インフルエンサー施策やUGC投稿を使った広告は必ず事前チェックを徹底しましょう。
薬機法を守るための広告表現チェック方法
薬機法違反を防ぐには「NGワードを避ける」だけでは不十分です。広告全体の印象、写真や図表、体験談の使い方まで含めて総合的にチェックする必要があります。ここでは、実務の現場で取り入れやすい3つのステップを紹介します。
1.社内のチェックリストを作成して確認する
まず最も基本的かつ有効なのが、社内用の薬機法チェックリストを整備することです。制作フローの中に「初稿段階の自己点検」を組み込むだけで、違反リスクを下げられます。
チェックリスト例
- 「治る」「改善する」など医薬品的効能の断定は含まれていないか
- 写真・ビフォーアフター画像で過剰な印象を与えていないか
- 口コミ・体験談が「疾病予防・治療効果」を暗示していないか
- 機能性表示食品や医薬部外品は承認内容と表現が一致しているか
| チェック項目 | 確認内容の具体例 |
| 効能効果表現 | 「治る」「改善する」「再生する」など医薬品的断定表現が入っていないか |
| イメージ画像 | ビフォーアフター写真が「治療・改善の保証」を暗示していないか |
| 口コミ・体験談 | 「飲んだら痩せた」「シミが消えた」など疾病予防・治療を示唆していないか |
| 商品種別ごとの制限 | 機能性表示食品や医薬部外品の効能が届出・承認範囲を超えていないか |
| 根拠資料 | 「○○%改善」と書く際に出典を明示し、根拠が正確か確認できているか |
| 法令対応 | 景品表示法・健康増進法も同時に違反していないかを併せて確認 |
このようなチェックリストを社内に持つことで、初期段階から薬機法違反リスクを削減し、専門家レビューを効率化できます。とくに中小規模の広告チームやフリーランスでは、これがあるだけで「法務がいない環境でも最低限のリスク管理」が可能になります。
2.言い換え表現のパターンを学ぶ
薬機法対策で重要なのは、ただ禁止するだけでなく「どう言い換えるか」を理解することです。表現の幅を知っていれば、企画やデザインを止めずにリスクを回避できます。
なぜ言い換えが重要なのか
- 制作のスピードを落とさずに済む
一度NG判定を受けても、即時に別の表現へ置き換えられると、リリース遅延を防げる。 - コンテンツの魅力を維持できる
消費者に刺さるワードを完全に排除せず、法的に安全な範囲で訴求可能。 - チームの判断力が統一される
ライター・デザイナーが迷わず使える共通基準を持つことで、初稿の精度が向上する。
言い換えの実例
| NG表現 | 言い換え例 |
| シワがなくなる | 肌にハリを与える |
| 免疫力を高める | 健康維持をサポート |
| 疲労が回復する | リフレッシュ感を与える |
| 発毛する | 髪にボリュームを与える |
| 病気を予防する | 健康管理をサポートする |
| ニキビを治す | 肌をすこやかに保つ |
厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」では、医学的効果を断定しない表現にする重要性が解説されています。
NGワードを削るだけでは広告が弱くなるため、自社で訴求になる文言をリストアップしておくことが重要です。例えば「シミが消える」を「シミ対策」だけに置き換えると訴求力も下がりますが、代わりに「肌を明るく見せる」などポジティブな表現を使うと広告として表現が可能になります。
関連記事:薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法
3.専門家や弁護士の監修を受ける
薬機法や景品表示法は条文だけで判断できないケースが多く、最終的な法的判断は弁護士による表現チェックが確実です。社内チェックリストの初期段階で一次的なフィルターをかけても、グレーな表現や行政処分の最新事例までは把握しきれない場合があります。
特に以下のようなケースでは、弁護士監修が非常に有効です
- 新商品発売やブランド立ち上げ時
製品カテゴリや効能範囲を整理し、初期から広告コンセプトを法的に安全な方向へデザインできる。 - 大型キャンペーン・大規模LP公開前
マスメディアやSNSで拡散される前に、違反リスクを減少させられる。 - 行政からの指導・改善要請を受けた後
表現修正だけでなく、再発防止策を示しつつ交渉や回答書の作成をサポートしてもらえる。
実務の判断ポイント
| 方法 | メリット | 向いているケース |
| 社内チェックリスト | コストゼロで始められる | 小規模LP・定常的な記事更新 |
| 言い換えパターン習得 | 制作フローを止めずに改善 | ライター・デザイナーが多い現場 |
| 専門家・弁護士監修 | 最も確実でリスク最小化 | 新商品リリース・広告キャンペーン前 |
社内の初期チェックと外部専門家のダブル体制が理想です。まずは社内で一次的な「フィルタリング」を行い、判断が難しい部分は専門家に相談することで、コストとリスクのバランスを取りながら薬機法を遵守できます。
関連記事:薬機法を弁護士に相談するメリットとは?広告チェックから違反対応のポイントを解説
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景表法に精通した弁護士が広告コピーやパッケージのリーガルチェックを提供しています。表現修正の提案から、行政対応のサポートまで依頼できるため、法務担当がいない中小企業やフリーランスにも有用です。
薬機法に関する弁護士へのご相談はこちらまでお寄せください。
広告制作フローに薬機法チェックを組み込む方法
広告表現の違反を防ぐには、制作の各工程に薬機法チェックを組み込む仕組みづくりが重要です。初稿作成から公開直前までのプロセスに法令確認を入れることで、手戻りや公開後のリスクを大幅に減らせます。
1. 初稿段階でライター自身がチェックリストを活用する
まずは執筆者自身が薬機法チェックリストを用いて一次確認を行いましょう。効能効果をうたっていないか、医薬品的な表現が含まれていないか、景品表示法・健康増進法に抵触しないかをセルフレビューする習慣をつけることが重要です。
2. デザイン・制作段階で写真やビフォーアフターを確認する
広告ビジュアルにビフォーアフター写真や過剰なイメージ訴求が含まれていないかをチェックします。特に美容・ダイエット系の広告では、写真による暗示的な表現も薬機法の規制対象となる可能性があります。
3. 公開前に専門家・弁護士のレビューを受ける
最終確認は、薬機法や景品表示法に精通した専門家・弁護士によるリーガルチェックを推奨します。初稿・デザイン段階のセルフチェックだけでは判断が難しいグレーゾーンも、法的な視点からリスクを回避できるようになります。
薬機法チェックツールの活用方法
薬機法の広告表現を安全に運用するためには、ツールによる一次チェック+人による精査を組み合わせるのが理想です。
すべてを手作業で行うと膨大な時間がかかり、逆にツールだけに頼ると判断の甘さから違反を見落とすリスクがあります。ここでは実務で使える代表的な方法を3つのレイヤーに分けて紹介します。
1.無料で使える薬機法チェックツールを利用する
まずは、無料の自動チェックツールを活用することで、初期段階のリスク発見コストを削減できます。
テキストを入力するだけで、薬機法的にNGの可能性がある単語を抽出してくれるサービスがあります。画像やURLから判断できるサービスも増えており、テキスト以外の判断にもおすすめです。
メリット
- コストをかけずに誰でも使える
- 初稿やライター原稿の一次チェックとしてスピーディー
- 修正箇所の目安を把握できる
デメリット
- 文脈判断ができず、「単語だけで判定」するものだと、誤判定が多い恐れがある
- 最新の行政処分事例や厚労省の改正情報を反映していない場合がある
活用ポイントとしては「まず一次フィルター」として使用し、その後の判断は必ず人が行うのが最適です。広告制作の初稿段階でライターやデザイナーに使ってもらうことで、効率よく表現チェックが可能になります。
2.人力チェック(専門家・弁護士)を依頼する
ツールやAIでは判断できないグレーゾーンの表現や法改正対応は、専門家・弁護士によるチェックが不可欠です。 特に、新商品や新ブランドの立ち上げ時や大規模キャンペーンを行う前など、違反した後のリスクが高くなるタイミングで依頼するといいでしょう。さらに、行政から指導を受けた後の対応は、法的な対処ができる弁護士に相談するのが確実です。
メリット
- 最新の行政処分事例・判例に基づいた具体的なアドバイスが得られる
- NG表現の指摘だけでなく、安全な代替コピー案を提案してくれる
- 行政指導が入った際の対応・交渉までサポート可能
デメリット
- コストがかかる(1件数万円〜、継続監修は月額契約になることも)
依頼までに時間がかかる場合がある
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、美容・健康領域の広告に特化したリーガルチェックを提供しています。広告文・LP・パッケージの監修だけでなく、行政対応サポートや社内向け研修の実施まで一貫して依頼でき、社内に法務部がない企業やフリーランスでも安心して広告展開が可能になります。
関連記事:リーガルチェックとは?やり方や注意点・弁護士に依頼する費用を徹底解説
薬機法チェックで参考にすべき公的ガイドライン・リソース
薬機法や景品表示法の表現判断では、信頼できる一次情報を参照することが不可欠です。公的なガイドラインや行政機関の公開資料を活用することで、誤った解釈によるリスクを最小化できます。
厚生労働省「医薬品等適正広告基準」
厚生労働省が公開している「医薬品等適正広告基準」 は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの広告を行う際に遵守すべきルールをまとめた行政によるガイドラインです。薬機法(医薬品医療機器等法)を実務で運用するうえでの判断基準として、広告担当者・マーケター・ライターは必ず確認しておく必要があります。
とくに以下のような重要ポイントが整理されています。
- 虚偽・誇大広告の禁止(薬機法第66条)
科学的根拠のない効果効能や、誤認を招く過剰な表現を禁止。
例:「絶対に治る」「副作用が一切ない」 といった保証的表現はNGです。 - 承認外効能・承認外使用の広告禁止
厚労省の承認を受けていない効能・用法・成分についての宣伝は禁止されています。 - 承認前医薬品の広告禁止(薬機法第68条)
まだ承認を受けていない新薬や輸入医薬品を「まもなく発売」などと告知する行為は違反となります。 - 医師・専門家の推薦表現の制限
「医師が推奨」「大学病院が絶賛」など、権威付けによる誤認を招く表現は禁止です。 - 体験談・ビフォーアフター写真の取扱い
効果を断定的に示す写真・口コミは、科学的根拠がなければ違反になる可能性が高いです。
広告の適法性は単語単体ではなく全体の印象で判断される点に注意が必要です。たとえば「スッキリ」という表現自体は曖昧でも、体重計の写真や「ダイエット」という文脈と組み合わされると、痩身効果を暗示する広告と見なされることがあります。
消費者庁「景品表示法」関連ページ
消費者庁が公開している「景品表示法」関連ページでは、事業者が広告・表示を行う際に守るべき基本ルールや行政処分制度について、公式の一次情報として確認できます。
景品表示法も、薬機法と共に確認をしておきましょう。
特に以下のようなテーマを体系的に学ぶことができます。
- 表示規制の概要
優良誤認表示や有利誤認表示など「実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示」について解説しています。 - 不実証広告規制
「合理的な根拠資料を提出できなければ不当表示とみなす」というルールを定め、健康食品・美容商材などの広告で特に問題となりやすい制度を解説しています。 - 景品表示法への課徴金制度導入について
景品表示法違反時に科される課徴金の計算方法や、実際の命令フローを解説しています。 - 執行状況
表示違反が指摘された措置命令・行政処分など、実際の違反事例が更新されています。
健康食品や美容・ダイエット関連の広告では、「免疫力が上がる」「飲むだけで痩せる」などの表現が合理的根拠の不十分さを理由に課徴金命令の対象となるケースが増えています。こうした最新の制度概要や行政対応の流れを消費者庁公式ページから直接確認できることは、法的リスクを回避するうえで非常に重要です。
措置命令・課徴金納付命令・確約データベース
措置命令・課徴金納付命令・確約データベースは、一般社団法人 全国公正取引協議会連合会(JFFTC) が運営する、広告や表示に関する行政処分を横断的に検索できるデータベースです。
このデータベースには、以下のような情報がまとめられています。
- 消費者庁が実施した景品表示法違反に関する課徴金命令・措置命令
- その他、地方自治体などによる表示規制関連の行政処分
これらの事例をキーワードや業種ごとに検索できるため、同業種や類似商品でどのような表現が問題視されたのかを具体的に把握することが可能です。
たとえば、健康食品や化粧品の分野では「飲むだけで痩せる」「医薬品的な効果がある」などの表現がしばしば景品表示法や薬機法の観点から問題視され、課徴金命令や行政処分が科された実例を確認できます。
自社の商品・サービスの広告を作成する際、どの表現がリスクになるかを具体例から学べるため、広告担当者やライターの研修・内部チェックにも有用です。
薬機法の広告表現チェックでよくある質問
SNSやインフルエンサー投稿も規制対象になる?
インフルエンサーや個人アカウントでの発信も「広告」と判断されれば薬機法の規制対象になります。広告かどうかは 「表示内容・媒体の性質・事業者の意図」 などにより総合的に判断されるとされています。
企業から商品提供や報酬がある場合はもちろん、PRであることを明記していないと ステルスマーケティング規制(景品表示法)にも抵触する可能性があります。
”企業がインフルエンサーに報酬を支払い、商品のInstagram投稿を依頼。その投稿を広告であることを明示せずに、自社サイト上に掲載していました。
これは、「一般消費者が広告だと気付けない表示」として、景品表示法違反(第5条第3号)に該当します。(引用:【令和7年3月】東京都が初のステマ摘発!SNS活用広告に潜む落とし穴と企業が守るべきルール)”
これらは事業者から商品提供・報酬があれば広告と判断され、薬機法の対象となります。薬機法だけでなく、景品表示法にも接触する可能性が高くなるため、PR表記など広告だとわかる記載が必須です。
OK表現とNG表現を簡単に見分ける方法は?
基本的な考え方は、「人体の構造や機能を直接改善・回復すると断定していないか」で判断することです。厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」では、単語だけでなく広告全体の印象で判断されると明記されています。
1. 動詞をチェックする:「治す」「改善する」「予防する」は危険サイン
広告文に「治る」「改善する」「再生する」「予防する」といった医薬品的な動詞が入っていないかを確認します。たとえばスキンケア商品の広告で「シミを改善する」「シワを治す」という表現はNGですが、「肌にハリを与える」ならOKです。
2. 効果の確実性を断定していないか:「必ず」「100%」「絶対」もNG
確実性を示す表現も危険です。「必ず痩せる」「100%発毛する」などはNGですが、「サポートする」「〜を整える」といった柔らかい表現に変えると適法になりえます。
3. ビジュアル・文脈の印象を確認する
たとえば「スッキリ」という単語自体はグレーですが、体重計の写真や「ダイエット成功」の口コミと組み合わされると 「痩身効果を保証する印象」と判断される可能性があります。
上記3つのポイントを押さえることで、単語だけでなく広告全体でNG表現かどうかが判断できます。特に「動詞・断定表現・ビジュアルの印象」を意識することが、薬機法チェックの基本です。
チェックを怠った場合は誰に責任が及ぶ?
薬機法違反の責任は、広告主(メーカー・販売事業者)が第一義的に負うのが原則です。ただし、広告代理店や制作会社も 共同責任を問われる可能性があることを理解しておく必要があります。
厚生労働省や消費者庁の行政処分事例では、広告主に対する課徴金命令や業務停止命令が中心ですが、制作側も一定の関与が認定されると、損害賠償や取引停止のリスクが発生します。
特に次のような場合は注意が必要です。
- 広告代理店が「違反リスクを指摘せず、積極的にコピーを提案した」場合
- 制作会社が「専門的判断を装って適法と助言した」場合
- フリーランスライターが「薬機法に詳しい」として依頼を受けた場合
制作現場の一次判断はあくまで補助的であり、最終的な法的判断は弁護士に依頼することが安全です。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所のような薬機法・景表法に精通した専門家に依頼すれば、行政指導の対応や万一の係争リスクを最小化できる体制を整えられます(参考:弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所|広告リーガルチェック)
まとめ|薬機法で広告表現をチェックし違反しないよう注意しよう
薬機法は、美容・健康業界の広告表現を取り締まるうえで最も重要な法律のひとつです。違反が発覚すれば 業務停止命令や課徴金(数千万円〜数億円規模) が科されるだけでなく、行政庁等により企業名が公表される可能性もあるため、ブランドの信用失墜にも直結します。
広告表現を守るためには次の3ステップを組み合わせるのが効果的です。
- 社内のチェックリストを整備し、初稿段階でNGを除外する
- 言い換え表現を体系的に学び、魅力を損なわずに安全なコピーへ修正する
- グレーな表現や大規模キャンペーン前には、専門家や弁護士の監修を受ける
特に美容・健康分野は、消費者庁や厚生労働省が厳しく監視しており、SNS・インフルエンサー投稿やLPの印象まで含めて規制対象になります。「単語だけをNGにする」のではなく、写真・レビュー・全体の雰囲気を含めた印象でリスクを判断することが重要です。
もし判断が難しいグレーゾーンの表現や、新商品ローンチ・大規模広告を予定している場合は、早めに専門家を活用することが安心です。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所は、美容・健康分野の広告に豊富な知見を持つ法律事務所です。
「自社の広告が本当に安全か分からない」「グレーな表現をどこまで使えるか判断がつかない」という方は、制作フローの早い段階から弁護士に相談しておくことで、後からの大規模修正や行政対応のリスクを大幅に減らせます。

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。