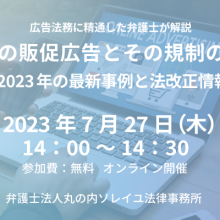「この化粧品、いつまで使えるの?」
消費者からこう聞かれて、使用期限の記載がなく困った経験はありませんか? 実は、日本ではすべての化粧品に使用期限の表示が義務づけられているわけではありません。では、どんなときに表示が必要で、どんな場合は不要なのか?――その基準を明確にしたのが、昭和55年9月26日付厚生省告示(告示第166号)、及び、昭和55年10月9日付の厚生省薬務局長通知(薬発第1330号)です。
この告示及び通知は、薬機法上の化粧品表示ルールの根拠の一つとして、現在でも広告審査や品質管理の実務に直結する重要な文書です。本記事では、告示及び通知の概要や実務での活用ポイントを整理し、表示義務の判断に迷わないための実務的な視点を提供します。
はじめに:なぜ今「使用期限表示」が注目されるのか
▶消費者の安全意識と品質保証ニーズの高まり
近年、化粧品に対する消費者の関心は「機能性」だけでなく「安全性」や「品質の持続性」にも広がっています。特にナチュラル処方や防腐剤フリー製品の人気が高まる中で、「使用期限はいつか」「いつまで使っていいのか」という疑問が購入後に生じやすくなっています。消費者トラブルや返品リスクを未然に防ぐためにも、企業側が期限表示をどう扱うべきかを正しく理解することが求められています。
▶使用期限表示の有無に差がある理由とは?
市販の化粧品には、使用期限が書かれている商品とそうでない商品が混在していることに気づいた方も多いはずです。この違いは企業の判断によるものではなく、厚生省が昭和55年に発出した通知に基づいたルールによるものです。一定の条件を満たす化粧品には表示義務がなく、逆に条件を満たさない場合には表示が必要となります。
▶本記事の目的
本記事では、化粧品における使用期限表示の制度的背景と実務運用の基準を、昭和55年厚生省告示及び通知の内容に沿ってわかりやすく整理します。特に、薬事・品質管理・マーケティング・法務に携わる実務担当者に向けて、表示の要否判断・適切な記載方法・表示しない場合のリスクまで、実務で必要な情報を網羅的に提供することを目的としています。
昭和55年厚生省告示及び通知とは?
▶告示及び通知の標題と発出背景
昭和55年告示の標題は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十四号等の規定に基づき使用の期限を記載しなければならない医薬品等」で、昭和55年9月26日付の厚生省(現・厚生労働省)告示となります。
また、それに続く昭和55年通知の標題は、「薬事法の一部を改正する法律の施行について」であり、昭和55年10月9日付で厚生省薬務局長から発出されました。
当時、化粧品の使用期限表示に統一的な基準がなく、品質の保持期間に不安のある製品が市場に流通していたことが背景にあります。告示及び通知は、消費者の安全確保と製品品質の信頼性向上を目的に、使用期限の表示が必要となる条件を明確に示しました。
▶使用期限表示が義務付けられる条件とは?
告示及び通知の最大のポイントは、すべての化粧品に期限表示を義務づけているのではなく、ある条件を満たした製品のみ表示を必要とするという点です。具体的には、
一 アスコルビン酸、そのエステル若しくはそれらの塩類又は酵素を含有する化粧品
二 前号に掲げるもののほか、製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年以内に性状及び品質が変化するおそれのある化粧品
に対して、使用期限を表示する義務があるとされています。この判断は、単に含有する特定成分の変化に着目するだけではなく、化粧品全体の性状及び品質が損なわれるか否かを目安とすべきであるとされています。
表示義務のあるケースとないケースの違い
▶防腐剤無添加・オーガニック系など
昭和55年の告示及び通知により、使用期限の表示が義務付けられる化粧品は、「適切な保存条件で3年以内に品質の変化が起こるおそれがある製品」と定められています。防腐剤や酸化防止剤を添加していないナチュラル処方・オーガニック化粧品、開封後劣化しやすいクリームや液体製剤等で、3年以内に品質の変化が起こるおそれがあるものについては、使用期限を表示する必要があります。使い切りタイプではない長期保存が前提となる容器形状の製品についても、3年以内に品質の変化が起こるおそれがあるかに注意して下さい。
▶表示が不要なケースとその根拠
一方、適切な保存条件のもと3年以上品質の安定が確認されている製品については、使用期限表示は原則不要とされています。たとえば、防腐剤が十分に配合されており、遮光性・密閉性の高い容器に充填された一般的なローションや乳液などで、3年以上品質が安定するものは表示義務がありません。このような製品は、製造販売業者が品質安定性を十分に確認したうえで(昭和55年通知では、「関係製造(輸入販売)業者が安定性試験データ等に基づき合理的な使用期限の設定を行うこと」とされています。)表示省略を選択することが認められています。
▶「表示なし=期限なし」ではないという注意点
もちろん、使用期限の記載がない化粧品は「ずっと使える」という意味ではありません。通知において表示が免除されているだけです。消費者の中には表示がないことで誤解が生じることもあるため、企業としてはFAQ・パッケージ・公式サイトなどで適切な保存方法や使用目安を補足説明することが望ましいといえます。
表示方法と記載の注意点
▶表示すべき内容
昭和55年通知では、使用期限の表示が必要な場合、「月単位まで」記載することとされています。日まで含める義務はありません。年月の表示につき、「令和8年12月」を、「08.12」のように簡略化することは差し支えないとされています。ただし、当該年月の意味が分かるように、「使用期限」等の文字を併せて記載する必要があるとされています。
▶実務で用いられる表示例(「使用期限:○年○月」など)
表示方法に関して法定のフォーマットは定められていませんが、以下のような実務的な記載例が一般的です
- 「使用期限:2027年6月」
- 「EXP: 2027/06」(輸出・輸入製品に多い形式)
- 「製造年月:2024年6月/開封後6か月以内に使用」
上記のような表示を行うことで、消費者にとって視認性が高く、誤認を避けやすいメリットがあります。輸出対応がある場合は、海外基準(EU、米国など)との整合性も意識することが重要です。
表示しない場合に起こり得るリスク
▶クレーム・返品・信用失墜などの実務リスク
使用期限が表示されていないことで最も多いのが、「この製品、いつまで使っていいのか分からない」といった消費者からの不安の声や問い合わせです。これが転じて、「品質に不信感を持った」「開封後に異常があった」といったクレームや返品の要因になることがあります。特にSNSやレビューサイトを通じたネガティブな拡散は、ブランドイメージの毀損に直結しかねません。使用期限表示が法的に不要なケースであっても、企業の説明責任が問われる時代になっています。そのため、使用期限を記載する義務がある場合は当然として、義務がない場合でも、使用期限を任意的に記載するということがあり得ます。
▶誤認表示や景品表示法違反とみなされる可能性
表示がない、あるいは曖昧な表現の場合、景品表示法上の「不実証広告(打消し不十分表示)」や「優良誤認表示」として問題視される可能性もあります。たとえば、「品質に問題なし」と訴求しながら、実際には短期間で変質する処方であった場合、根拠資料の提示が求められ、それが不十分であれば違反認定の対象となります。意図せずとも、表示不足が不当表示につながるリスクを常に意識しておく必要があります。
また、化粧品につき、使用期限の表示義務があるにもかかわらず使用期限を記載しなかった場合、薬機法61条5号に反することになります。
▶海外向け表示との整合性(特にEU・米国基準との比較)
国内では一定条件下で使用期限表示が不要とされていますが、EUや米国ではより厳格な表示義務が課されている場合があります。たとえばEUでは「開封後使用期限(PAO: Period After Opening)」の表示が推奨・義務化される製品も多く、輸出や越境ECを行う企業にとっては、表示の不統一が輸出先規制や現地トラブルの要因になりかねません。こうした事情をふまえ、グローバルな視点で表示方針を統一しておくことが、今後さらに重要になってきます。
実務担当者が取るべき対応と判断基準
▶商品設計・品質データに基づいた判断プロセス
化粧品の使用期限表示が必要か否かは、製品ごとの安定性・保存性データに基づいて判断する必要があります。防腐剤の種類や濃度、製剤の性質(クリーム、液体など)、容器の密閉性、光や湿度への耐性などが判断材料です。製品設計段階から、「未開封で3年以上品質が維持できるかどうか」を検証し、データとして保管しておくことが、表示省略の根拠になります。開発・品質・薬事部門が連携して早い段階で方向性を決めることが重要です。
▶自社基準書・表示マニュアルの整備
製造販売業者は、社内での表示ルールを明文化しておくことが望まれます。たとえば、「以下の条件に当てはまる製品は使用期限を表示する」「安定性試験で〇ヶ月未満と判断された場合は表示義務あり」といった社内判断基準書・表示マニュアルを整備し、各部署で共有することで、表示判断のブレやリスクを軽減できます。また、表示省略を選択した場合も、その判断根拠を文書化して保管しておくことで、外部監査や行政対応にも備えることができます。
▶弁護士・薬事顧問との連携の重要性
使用期限表示の可否判断は、薬機法や景品表示法など複数の法的リスクが交差する領域です。判断に迷うグレーなケースや、広告との整合性が懸念される場合は、薬機法・景品表示法に詳しい弁護士や薬事顧問に早めに相談することが、リスク回避につながります。製品の販売戦略に影響するテーマだからこそ、法的な裏付けを持った意思決定が企業の信頼性確保と安全性の担保に直結します。
弁護士による化粧品・薬用化粧品相談はこちらでお受けしておりますので、ぜひご確認ください。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所によるサポート

▶使用期限表示に関する法的レビュー・ガイドライン整備
使用期限表示は単なる記載事項ではなく、薬機法・景品表示法・消費者保護の観点が複雑に絡む法的領域です。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、化粧品の製造販売業者やマーケティング企業に対し、表示義務の有無に関する判断支援、社内判断基準・表示ガイドラインの作成、法令レビューなどを実施しています。とくに、厚生省通知の解釈やグレーゾーンへの対応において、実務的かつ合理的なサポートを提供しています。
▶表示をめぐるリスク対応・行政対応の支援実績
当事務所は、表示の不備に起因するクレーム対応・景品表示法違反のリスク評価・行政対応の経験も豊富です。
たとえば、使用期限の表示不備に関する消費者庁からの問い合わせ対応、回収要否の検討、Web広告と製品表示との整合性チェックなど、企業が直面しがちな問題に対する実務的な対応に強みを持ちます。社内だけでは判断が難しいケースも、法的リスクを可視化し、事前の是正提案を行うことが可能です。
▶薬機法・景品表示法に強いパートナーとしての伴走体制
化粧品表示の分野では、法的要件とビジネスニーズのバランスを取ることが何より重要です。
丸の内ソレイユ法律事務所では、月額顧問やプロジェクト単位での支援も含め、初期相談から商品発売後の広告運用支援まで一貫して対応しています。広告表示等に詳しい弁護士との連携により、企業のブランド価値を守りながら、法令遵守と安全性を両立するための「攻めと守り」の両面支援が可能です。
化粧品の使用期限表示に関してお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。貴社のリスクを最小限に抑え、信頼される商品展開をご支援いたします。
薬機法に関する弁護士へのご相談はこちらまでお寄せください。

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。