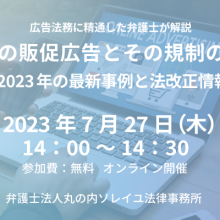近年、リポソームやナノカプセル技術を採用した高機能化粧品が増え、「浸透力」や「成分を奥まで届ける」といった広告表現が注目を集めています。こうした表現は消費者に強く訴求できる一方で、薬機法や景品表示法との関係で「違法表現」に該当するおそれがあることをご存じでしょうか?
とくに、リポソームは「肌の奥に効く」という印象を与えやすく、医薬品的効能の誤認を招きやすいワードとして、行政の注視対象にもなりつつあります。この記事では、リポソーム配合化粧品に関する広告規制の考え方と、企業が取るべき実務的な対応策を、厚生省通知や近年の広告指導事例をもとに詳しく解説します。
はじめに:リポソーム技術が広告リスクになりうる理由
▶技術としての魅力と法規制とのギャップ
リポソームは、成分の安定性向上や肌なじみの向上といった技術的メリットがあり、高機能化粧品の差別化要素として多くの企業が採用しています。近年では「浸透型」「高濃度浸透技術」「ナノサイズで届ける」など、機能性を訴求するコピーが増加傾向にあります。しかし、その表現の中には、薬機法上の「医薬品的効能」を想起させるものや、消費者に誤認を与えかねない表現が含まれていることも少なくありません。
▶なぜリポソーム表現が問題視されるのか?
リポソームの広告表現が問題とされるのは、「浸透」「深く届ける」といった言葉が、肌の奥=真皮や血管への効果を連想させるためです。これは、薬機法上で化粧品に許容される浸透は「角層まで」という制限を逸脱する可能性があり、実際に都道府県から指導を受けたケースも報告されています。
また、景品表示法の観点からも、根拠のない技術表現は優良誤認とみなされるリスクがあるため、法令対応は薬機法と景表法の両方を見据えた多角的な判断が必要です。
▶本記事の目的と対象読者
本記事では、リポソーム配合化粧品における広告表現の適法範囲を明確にし、どのような言い回しが問題となり得るのかを、行政通知・ガイドライン・実際の表現例を用いて解説します。対象は、化粧品メーカー・OEM企業・広告代理店などで表現判断を担う薬事・広告・法務・広報のご担当者様です。
リポソームとは?技術的特徴と化粧品分野での応用
▶リポソームの定義と構造
リポソームとは、リン脂質などで構成される「脂質二重膜」構造を持つ微小なカプセル状の粒子です。構造的には、細胞膜に似た膜で成分を内包することで、水溶性・油溶性いずれの成分も安定して封入できるのが特徴です。粒子の大きさは数十〜数百ナノメートル単位であり、「ナノ化技術」「カプセル化技術」などとも表現されることがあります。
この技術は、医薬品分野では薬物送達システム(DDS)としても利用されてきた歴史があり、化粧品においても機能性の高い製品設計に応用されています。
▶化粧品での配合目的と期待される効果
化粧品におけるリポソーム技術の主な目的は、次のような機能の実現です:
- 有効成分の安定化(酸化・分解の防止)
- 成分の肌表面へのなじみやすさの向上
- 角層への浸透感の演出
- 保湿・感触の改善(なめらかさ・べたつきの軽減)
ただし、リポソーム自体が「真皮に成分を届ける」「体内に吸収させる」といった医薬品的効果を持つわけではないため、その表現方法には法的な制限が生じます。特に、技術を強調しすぎることで医薬品的効能を暗示するおそれがある表現は、薬機法違反として指摘される可能性があります。
▶ナノ化・マイクロカプセルとの違い
リポソームはナノ粒子の一種ですが、他のナノ化技術(例:ナノエマルジョン、マイクロカプセル)とは構造や機能が異なります。リポソーム=より生体類似構造で、薬機法違反のリスクが高まる表現になりやすい点が、広告で表現する際にも注意する必要があります。
昭和62年厚生省通知に見る「浸透」表現の制限と背景
▶「表皮内への浸透」表現はなぜNGなのか?
昭和62年11月25日付の厚生省通知(薬務局長通知)は、化粧品の効能効果表示の「範囲」と「表現例」を明示した極めて重要な文書です。この通知では、化粧品に許される表現は「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、皮膚や毛髪を健やかに保つ範囲内」に限られるとされ、医薬品的な効能効果の表現、つまり疾病・疾患の治療や予防的な表現は禁止されています。
中でも、「浸透」や「届ける」といった文言は、皮膚の奥=真皮や血管領域まで作用するような印象を与えるため、医薬品的な解釈につながりやすいとされています。実際、通知では「表皮内に成分が浸透する」といった表現は認められないと明記されています。
▶「角層まで」はOK、「深く届ける」はNG?行政解釈のポイント
化粧品で許容される最大の深度は、「角層まで」とされており、「角層への浸透」「角層にうるおいを与える」などの表現は認められています。一方で、「肌の奥まで届ける」「細胞レベルで届く」などの表現は、角層を超えた作用を連想させることからNGとされるケースが多く、実際に行政指導の対象になった例も存在します。
特にリポソーム技術を用いた商品では、科学的な浸透力の高さを示したくなる場面もありますが、“技術的事実”であっても、広告表現では消費者の受け取り方=誤認可能性が基準になることを忘れてはなりません。
▶通知に明記されていない技術用語の取扱い
通知では「リポソーム」や「ナノ化」などの最新技術用語は明記されていませんが、通知の趣旨(医薬品的効能の排除)に基づいて類推的に判断されるのが実務の現状です。そのため、リポソームを活用する場合は、表現の技術的根拠だけでなく、行政の運用スタンスも踏まえた広告判断が求められます。
リポソーム配合化粧品に関する広告NG例と許容表現
▶NG例:「肌の奥まで」「細胞に届く」などの過剰表現
リポソームの効果を訴求する広告文には、消費者にとって魅力的な表現が多く見られますが、中には薬機法上NGとされる文言も少なくありません。たとえば以下のような表現は、医薬品的効能を暗示するおそれがあり、行政指導の対象となり得ます:
- 「有効成分を肌の奥深くまで届ける」
- 「細胞レベルでアプローチ」
- 「真皮層まで浸透して効く」
- 「ナノカプセルが体内に届いて働く」
これらは、角層を超えた効果を暗示するため、化粧品の効能効果の範囲を逸脱していると判断される可能性が高いです。リポソームの構造自体が高度な技術であるため、訴求がエスカレートしやすい点に注意が必要です。
▶許容される表現例とその根拠
一方で、行政通知や実務運用上、一定の技術表現は化粧品でも使用可能とされています。以下は一般的に許容されるとされる例です:
- 「角層まで浸透」
- 「うるおいを与える」「なめらかに整える」
- 「リポソーム技術で成分を包み込む」
- 「肌なじみのよい使用感」
これらの表現は、肌の表面(角層)への作用や感触などに限定されたもので、医薬品的効果を想起させないことがポイントです。また、「リポソーム技術」という文言そのものは使用可能ですが、それに伴う効能表現が誇大にならないよう注意が必要です。
▶表現の評価ポイントとチェックの視点
表現が許容されるかどうかの判断では、単語そのものだけでなく、文脈全体・受け手の印象・科学的根拠の有無も重要視されます。特に「技術名称+効果訴求」が組み合わさる場合は、意図せず薬機法・景表法の違反となるリスクがあるため、事前のチェック体制が不可欠です。
違反リスクと企業への影響:指導・措置命令・信頼毀損
▶行政指導のリスク:自治体・厚労省による是正要請
リポソーム技術に限らず、薬機法上の広告違反が疑われる場合、まず都道府県の薬務主管部局から行政指導が入るのが一般的です。
「浸透」や「奥まで届ける」などの表現については、過去にも複数の自治体が注意喚起や是正指導を行った事例があります。初期段階では「自主的な修正」が求められますが、対応が不十分であれば公表・報告命令に至るケースもあるため、軽視はできません。
▶景表法違反による措置命令・課徴金リスク
リポソームに関する誇大広告は、景品表示法上の「優良誤認表示」に該当する可能性もあります。実際、過去には「肌の奥に届く」「細胞を修復する」などの文言を用いた広告が消費者庁により措置命令の対象となった例もあります。
さらに、2023年以降は景表法違反に対する課徴金制度の適用範囲が拡大され、違反による経済的損失は無視できない規模となっています。
▶信頼失墜とレピュテーションリスク
行政処分が公表された場合、企業の信頼性やブランド価値に直接的な悪影響を及ぼすのは言うまでもありません。特にリポソーム技術を差別化要素として採用している場合、その機能性に対する疑念が広がることで市場競争力の低下につながる恐れもあります。
さらに、SNSや口コミで「この会社は誇大広告をしている」といった二次的炎上が拡大することも想定され、適切な広告管理体制が企業のリスク対策に直結すると言えるでしょう。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所による支援内容

▶表現審査・広告チェックに強い法務支援
リポソームやカプセル化技術などの広告は、魅力的である一方、薬機法や景品表示法に抵触するリスクが高いため、事前に法的観点からの審査が極めて重要です。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、医薬品的効能と誤認されるおそれのある表現の見直しや、厚生省通知に照らした表現許容範囲の整理など、法令に基づいた広告チェックを提供しています。
▶技術的訴求を含む表現への法的観点からの評価
当事務所では、企業が用意した広告文案や訴求資料に対し、消費者がどのように受け取るかという観点を重視しつつ、薬機法上の「効能・効果」の範囲を逸脱していないかを判断します。
たとえ製品開発に科学的根拠があっても、広告表現として許されるかどうかは別問題であるため、開発部門・マーケティング部門と連携したアドバイスが可能です。
必要に応じて、行政対応に備えた記録整備や、判断根拠となる通知・ガイドラインに基づいた社内説明資料の作成支援も行っています。
▶広告運用から社内体制整備まで一貫して対応可能
さらに当事務所では、月額顧問契約やプロジェクト単位でのスポット相談にも対応し、広告表現の事前審査、契約文書の作成・修正、社内規程・ガイドラインの整備まで、広告活動を継続的に支える体制をご提供しています。
薬機法・景表法に準拠した広告運用を企業の内部に根付かせることで、ブランドの信頼性維持とリスク最小化を両立する支援が可能です。
リポソーム配合化粧品の表現に不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。
現場での判断に迷ったとき、法的な裏付けを持って意思決定できる環境を整えることが、企業にとって最大の防衛策となります。
弁護士への広告審査のご相談はこちらでお受けしておりますので、ぜひご確認ください。
関連記事
薬機法違反をチェック!弁護士が健康食品・化粧品等の広告違反事例を解説
薬機法において、医療機器の製造・販売・輸入で注意すべき点は?弁護士が解説
医薬品ビジネスに関する主な契約類型とポイント その1(研究・開発)

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。