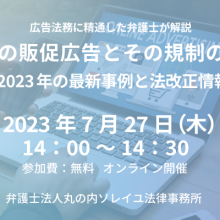「自社で開発したヘルスケア機器が医療機器にあたるかどうか判断できない」
「広告表現が薬機法に抵触するか不安で、製品リリース前にチェックしたい」
医療機器の開発・販売・広告を担当していると、このような不安を感じる場面は少なくありませんよね。薬機法は製薬業界だけのものと思われがちですが、家庭用美容機器やウェアラブル端末、スマホアプリまで規制対象になる可能性があるため、誤った判断をすると販売停止・課徴金・ブランド毀損などの大きなリスクを抱えることになります。
この記事では、薬機法における医療機器の定義・分類・該非判定の考え方と、広告表現を安全にチェックするための基礎知識を徹底解説します。特に、医療機器広告は薬機法だけでなく景品表示法・プラットフォーム広告ポリシーとも密接に関わるため、事前に正しく判断しておくことが不可欠です。
もし判断に迷うグレーゾーンの表現や、新製品ローンチ前のリーガルチェックが必要な場合は、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。薬機法・景表法に精通した弁護士に相談しておくことで、後の修正コストや行政対応リスクを大きく減らせます。
薬機法における医療機器の定義
医療機器の規制は、製品の「形状」や「性能」だけではなく、使用目的と広告等の外部に表示する表現によって決まるのが最大の特徴です。
「ただの美容家電だと思っていたのに医療機器に該当した」「アプリを健康管理用と説明していたが、医療機器と判断された」というケースが近年増えています。
まずは法律上の定義を確認し、具体的な例と、特に判断が難しいプログラム医療機器(SaMD)の考え方を押さえましょう。
医療機器の法的な定義(薬機法第2条)
薬機法第2条第4項は、医療機器を次のように定めています。
“人又は動物の疾病の診断、治療又は予防、身体の構造又は機能に影響を及ぼすことを目的とし、政令で定めるもの(引用:薬機法|e-Gov法令検索)”
医療機器だと判断するための重要なポイントは以下の3つです。
- 目的で判断される
製品がどんな形態であっても、「治療・予防」などの目的があれば医療機器とみなされます。 - 広告・付随する文書も判断材料になる
パッケージやLPに「改善」「治る」といった表現があれば、製品自体が医療機器扱いとなる可能性があります。 - リスクによって規制の厳しさが変わる
クラス分類(Ⅰ〜Ⅳ)に応じて、届出・認証・承認が必要になります。
たとえば美容機器や健康管理をうたっているデバイスでも、「血流を改善」「筋肉のコリを治療」といった効能をうたえば医療機器と見なされる可能性があります。また、判断材料は製品だけでなく、パッケージ・LP・取扱説明書など広告表現も対象となり、「改善」「治る」といった医薬品的な表現を使うと医療機器扱いになるリスクがあります。
関連記事:薬機法とは?簡単にわかりやすく解説|規制内容・違反事例・対策まとめ
医療機器に該当する製品の具体例
実務でよく混同される「雑貨」「美容家電」「健康機器」のうち、薬機法上は以下のように分類されます。患者へのリスクの高さに応じてクラス分類され、届出や規制の要件が異なります。
| リスク分類 | 製品例 | 規制の特徴 |
| クラスⅠ(一般医療機器) | 低周波治療器、体外診断用機器、鋼物小物(メス・ピンセット等) | 製造販売届出のみで販売可能 |
| クラスⅡ(管理医療機器) | コンタクトレンズ、パルスオキシメータ、家庭用血圧計、美容レーザー | 認証(第三者機関による審査)が必要 |
| クラスⅢ(高度管理医療機器) | 人工呼吸器、人工関節 | 原則としてPMDA承認(治験が必要となる)が必要 |
| クラスⅣ(最もリスクが高い) | 人工心臓弁、体外式膜型人工肺(ECMO)ペースメーカー、 |
(参考:厚生労働省|医療機器の分類と規制)
医療機器のクラス分類(Ⅰ〜Ⅳ)はリスクレベルに応じて承認・認証の厳しさを決める仕組みですが、これとは別に「特定保守管理医療機器」という追加区分が存在します。
この指定を受けると、クラスⅡ〜Ⅳの規制に加えて、定期点検・修理体制の整備、安全使用情報の提供など、薬機法の厳守だけでなく二重の管理体制が必要になります(参考:厚生労働省|特定保守管理医療機器)
プログラム(SaMD)の医療機器としての判断基準
近年はスマホアプリやソフトウェア単体が医療機器に該当するケースが急増しています。これをSaMD(Software as a Medical Device)と呼びます。
“疾患を治療したり、服薬を管理したり、健康を維持したりするためのデジタル技術(アプリなど)が続々と開発されている。そうしたデジタル技術はデジタルヘルスと総称されているが、流通・販売に当たって薬事承認が必要となるものは「プログラム医療機器(Software as a Medical Device:SaMD、サムディー)」と呼ばれている。(引用:日経バイオテク|SaMD(Software as a Medical Device)ってなんと読む?)”
具体例
- 医療機器に該当する例
- 不整脈を検知し、医師に診断支援データを提供するアプリ
- 糖尿病管理アプリで、血糖値データを解析して治療方針を提案するもの
- 該当しない例
- 一般的なダイエット管理アプリ
- 睡眠の質を可視化するだけの活動量計
プログラム医療機器(SaMD)は、ソフトウェアやアプリであっても医療目的があるか、人体の機能に影響を与えるかで医療機器と判定されます。健康管理系アプリやウェアラブル機器でも、広告や説明書に「治療」「診断」「改善」と書けば規制対象になるリスクが高まります。
| 判断基準 | 内容 |
| 医療目的 | 疾病の診断・治療・予防を目的としているか |
| 機能・作用 | 身体機能への影響や診断補助があるか |
| 使用者 | 医療従事者の診断支援か、一般向けか |
一度医療機器とみなされると、PMDAへの認証・承認申請、品質管理体制の整備などコストもスケジュールも大きく変わるため、開発初期からの判断が重要です。
医療機器と雑貨・美容機器の違いと判断ポイント
美容機器や健康グッズは、一見すると雑貨や家電のように見えても、広告表現や使用目的によっては医療機器に該当する可能性があります。
美容家電や健康グッズを扱うときに最も迷いやすいのが、「この製品は医療機器にあたるのか?」という判断です。薬機法第2条で医療機器の定義は示されていますが、実務では単に法律文を読むだけでは判定しづらいケースがあります。そこで、雑貨か医療機器かを見分ける際の実務的なチェック手順をまとめました。
- 効能・目的を確認する
「治療・予防・診断」といった医療的な目的が広告やパッケージに書かれていないかを最初にチェックします。
例:✕「肩こりを治療」「血流を改善」 → 医療機器に該当する可能性あり。 - 表示・広告物を精査する
製品そのものの機能だけでなく、LP・SNS・取扱説明書の文言やビジュアルも判断対象です。
例:ビフォーアフター写真や体験談で「改善した」と表現していると医療機器扱いになるリスクあり。 - 公的リソースで分類を確認する
厚生労働省の医療機器クラス分類・承認制度や
医療機器プログラム指針で、類似製品がどのクラスかを確認。 - 迷ったら専門家レビューを受ける
法的な最終判断は薬事法管理者や弁護士の領域です。特に健康・美容機器は表現次第で医療機器扱いになりやすいため、販売前に確認を受けるのが安全です。
判断に迷った場合は、厚生労働省の医療機器のクラス分類と承認制度や、医療機器プログラムに関する取扱い指針などの公的資料を参照し、最終的には薬事法管理者や弁護士など専門家の確認を受けることが推奨されます。
薬機法で求められる医療機器の該非判定とは?
医療機器を開発・販売する際、最初に重要なのが「その製品が医療機器に該当するかどうか(該非判定)」です。薬機法は、単なる製品の形や機能だけでなく、広告や表示の目的によって医療機器と判断される場合があります。そのため、開発・販売・広告のどの段階でも該非判定を理解しておくことが不可欠です。
以下のような「治療・改善・診断・予防」といった医療目的を示す表現があるかどうかが最大の判断ポイントです。
| 医療機器に該当する例 | 医療機器に該当しない例 |
| 肩こりを治療する低周波治療器 | リラックス目的のマッサージ機 |
| 糖尿病治療をサポートするアプリ | 睡眠の質を可視化する健康管理アプリ |
| 不整脈を解析し診断補助を行うウェアラブル | 活動量や歩数を記録する一般的なフィットネストラッカー |
もし美容家電や健康アプリのようなグレーゾーン製品では、広告の一文が「医療機器」とみなされるかどうかを左右し、誤れば販売停止や課徴金、ブランド毀損といった重大リスクを招きます。
実務で注意すべきグレーゾーンとリスク
- 美容家電・美容機器
美顔器やEMS機器はリラクゼーション目的なら雑品扱いですが、「しわ改善」「肌治療」をうたえば医療機器扱いになる可能性があります。 - 健康管理アプリやウェアラブル
データ記録や健康サポートなら雑貨ですが、「診断補助」「治療方針の提案」といった医療目的の表現を含むと、ソフトウェア医療機器(SaMD)として薬機法の規制を受けます。 - 医療現場を想定した機器
医師や看護師が診断・治療判断に使うことを想定していれば、基本的に医療機器として申請が必要です。
薬機法や関連法違反のリスク回避のために、まず医療機器の該非判定は「目的」「機能」「広告表現」を基準に自己判断→PMDAや都道府県の薬務課相談というステップを踏みましょう。クラス分類後に承認・認証された範囲を超えた広告表現は違反になるため、マーケティング担当は承認書の記載を必ず確認する必要があります。
医療機器広告に関する薬機法のルール
医療機器の広告は、薬機法第66条(虚偽・誇大広告の禁止)をはじめとした規制に従う必要があります。特に消費者が誤認するおそれのある表現や、承認を受けていない効能・効果をうたう表現は厳しく制限されています。
また、厚生労働省が定める「医薬品等適正広告基準」は、医療機器の広告にも適用されます。違反した場合、行政指導や業務停止命令、課徴金といった処分だけでなく、企業名が公表されブランド毀損につながるリスクもあります。ここでは、医療機器広告で押さえるべき基本ルールを整理します。
関連記事:薬機法の広告規制とは?広告の定義・3要件・違反事例まとめ
医療機器広告で使える表現
医療機器の広告では、承認・認証を受けた範囲内の効能効果のみを正確に伝えることが大前提です。承認書や添付文書に記載された効果・使用目的の範囲であれば、以下のような表現は使用可能です。
| 承認内容の範囲内で使える例 | 表現可能な理由とポイント |
| 「皮膚表面の汚れを除去します」 | 認証された効能の範囲に限定 |
| 「歯の表面を研磨し、着色を防ぎます」 | 医療機器クラスⅡの歯科用機器など |
| 「血圧の測定をサポートします」 | 計測系機器は測定機能のみ強調可 |
| 「視力矯正を目的としたコンタクトレンズです」 | 製品の適応症を逸脱しない表現 |
特に「承認内容の正確な引用」と「誇張しない説明」が重要です。 例えば「血圧計」は「家庭で血圧を測定できます」と表現できますが、「血圧が改善する」「高血圧が治る」といった医療効果の断定はNGです。
そのため、医療機器の広告表現においては、どのクラス分類にあたるかを踏まえて範囲内での表現に留めましょう。訴求する商品によって範囲や使える文言が変わるため、独自の表現チェックを一覧化しておくのも重要なポイントです。
禁止されている広告表現のNG例
薬機法第66条は、虚偽・誇大な広告を禁止しています。医薬品や化粧品だけでなく、医療機器も該当するため注意が必要です。具体的なNG表現は次のようなものが挙げられます。
| NG表現例 | なぜ違反になるか |
| 「100%治る」「絶対に改善する」 | 断定表現による効能効果保証 |
| 「医師が絶賛」「医療現場で大人気」 | 専門家である医師の推薦 |
| 「薬事承認不要」「厚生労働省も認めた」 | 国等の関係機関の推薦 |
| ビフォーアフター写真で劇的な改善を示す | 「治療効果の保証」を誤認させる恐れ |
| 「副作用ゼロ・完全安全」 | 安全性を断定する表現は禁止 |
薬機法上の判断は、単語ごとではなく広告全体の印象で行われます。具体的なNG表現を使用していない場合でも、画像や説明文にも注意が必要です。
例えば「美肌ケアに最適」という言葉だけでは抽象的ですが、レーザー治療器の写真や“しみが消える”といった説明と一緒になると、医療機器として承認されていない治療効果を暗示する広告とみなされるリスクがあります。
関連記事:薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法
医薬品等適正広告基準に基づく医療機器広告の規定
医療機器広告は、承認前又は未承認医療機器の広告禁止(薬機法68条)と虚偽・誇大広告の禁止(66条)が土台です。さらに厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」が、承認(認証)範囲内での表示や安全性表現の制限を具体化しています。違反すると、行政指導・業務停止命令・課徴金等の対象になります(参考:厚生労働省|課徴金制度の導入について)
よくある違反事例
| 状況 | 適用条文・基準 | 主なリスク | 実務で起きがちなNG例 |
| 承認前なのに一般向けに効能を宣伝 | 68条「承認前広告の禁止」、適正広告基準 | 行政指導、行政処分、出稿停止、商品回収 | オウンドメディアやSNSで「近日発売・〇〇を治療」等の告知を一般消費者向けに行う |
| 展示会で未承認品を承認品のように訴求 | 68条、展示ガイドの運用通達 | 行政指導、処分、配布物回収 | 学会ブースで未承認品をパネル・映像で積極訴求、関連資料の配布(原則不可)(JIRA) |
| 承認機能を超えた“治療・予防”を断定 | 66条、適正広告基準 | 誤認表示として行政指導、行政処分、ブランド毀損、課徴金 | 認証済みの測定器に「高血圧が治る」など“治療効果”を付加する表現 |
| 安全性の断定・過度な優良誤認 | 66条、適正広告基準 | 行政指導、行政処分、ブランド毀損、課徴金 | 「副作用ゼロ」「絶対安全」「メンテ不要」といった断定表現 |
医療機器広告は、承認範囲を超えた表現・効果の断定・安全性の誇張がもっとも違反リスクを高めます。違反すれば行政指導や課徴金だけでなく、企業名公表によるブランド失墜のリスクも無視できません。
広告表現の最終判断は難しく、一つの単語ではなく全体の印象で判断されるため、社内チェックリストだけでなく、薬機法に詳しい弁護士によるリーガルチェックを組み合わせることが安心です。
承認・認証取得後の実務フロー(広告・販売開始まで)
- 承認内容(効能・適応範囲・使用方法)の最終確認
→承認書・添付文書に記載された効能・性能の範囲を超えた表現はNG。 - 広告・販促物の表現チェック
→キャッチコピーやビジュアルが承認範囲内か確認。
→医薬品医療機器等法(薬機法)、景品表示法、健康増進法の観点でもダブルチェック。 - ビフォーアフター写真・体験談の可否判断
→「治った」「改善した」と断定しない。限定解除要件を満たすか確認。 - 販売チャネル別の表現整備
→Webサイト、LP、SNS、ECモール、店頭POPなど媒体ごとにルールを適用。 - 内部体制の整備
→販売後広告媒体を変更する際等のフローを構築。
→取扱説明書・注意書きを承認内容に合わせて更新。 - 専門家によるリーガルレビュー
→最終的に薬事法管理者・弁護士など専門家による広告審査を経てから公開するのが安全。
また、薬機法だけでなく景品表示法などの他法令との重複リスクもあるため、「承認を得た=安全」ではないことを常に意識しておくことが大切です。 適切なチェックフローを運用することで、行政指導や課徴金、ブランド毀損といった重大なトラブルを未然に防ぐことができます。
医療機器で薬機法を遵守するためのチェック方法
医療機器は人体への影響が大きい製品を扱うため、薬機法による規制が非常に厳格です。承認範囲を逸脱した広告や、未登録のまま販売する行為は、業務停止や課徴金だけでなくブランドの信用失墜にも直結します。
ここでは、開発・販売・広告の各フェーズで違反リスクを下げるために有効なチェック方法を3つの観点から解説します。
関連記事:薬機法の広告表現をチェックする方法|NG例・言い換え・便利ツール
1.社内ガイドライン・チェックリストを整備する
まず基本となるのは、社内で薬機法遵守のルールを文書化し、チェックリストを運用することです。制作初期の段階から自社で最低限のフィルターをかけるだけで、後工程の修正コストを大きく削減できます。
チェックリスト例(医療機器向け)
- 製品が承認・認証済みであるか、承認番号を確認しているか
- 効能効果が承認範囲内かを添付文書と照らし合わせて確認
- 「治る」「改善する」など治療効果の断定表現が含まれていないか
- 「副作用ゼロ」「完全安全」など安全性を保証していないか
- 医療従事者・学会の権威付けを根拠なく使っていないか
- 未承認製品を一般向けに告知・広告していないか
(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準)
実務においては、新製品やアップデート時は承認書・認証書と広告コピーを突き合わせる運用を習慣化すると安全です。たとえ担当者が入れ替わってもルールが継承されるよう、社内マニュアル化+定期研修を行うよう体制を整えましょう。
2.専門家・弁護士に広告や該非判定を相談する
最終的な法的判断は、薬機法に精通した弁護士や専門家に相談することが最も確実です。特に以下のようなケースでは、内部だけの判断はリスクが高まります。
- 新しいタイプの製品(AI医療機器やウェアラブルデバイスなど)の該非判定
- 大規模なキャンペーン広告・SNSプロモーションを実施する場合
- 承認範囲が複雑な高リスク医療機器を扱う場合
- 過去に行政指導や薬機法違反の指摘を受けたことがある場合
過去にはEMS機器を販売する会社で誇大広告による景表法の課徴金納付命令が求められ、500万円以上の行政処分を受けた事例もあります。
“自社ウェブサイトで配信した動画において、「使用前ウエスト102.4cm→ 使用後88.0cm」、「-14.4cm」等と表示することにより、あたかも、本件商品を腹部に使用すれば、本件商品の電気刺激によって腹部の筋肉が鍛えられることにより、1か月又は6週間で腹部の痩身効果が得られるかのように表示していた(引用:措置命令・課徴金納付命令・確約データベース)”
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法・景表法対応のリーガルチェックや広告の事前審査、PMDAとの該非相談サポートなどを提供しています。承認範囲を逸脱していないか、広告全体の印象が適正かを法的にレビューできる点が最大のメリットです。
薬機法に関する弁護士へのご相談はこちらまでお寄せください。
薬機法と医療機器に関するよくある質問
医療機器と雑品の境目はどう判断する?
医療機器か雑品かの判断は、製品の目的と作用によって決まります。薬機法第2条では、人体の構造や機能に影響を及ぼすことを目的とするものは医療機器と定義されています。
“医療機器等法の規制対象製品に類似するものとして、食品、除菌グッズ、園芸用品、健康雑貨、美容器具、芳香剤、着色剤などがあり、これらは薬事規制の対象とならない、いわゆる雑貨です(引用:東京都保健安全研究センター|いわゆる雑貨について)”
| 判断の観点 | 雑品の例 | 医療機器とみなされる例 |
| 目的 | 美容目的で肌を温めるフェイススチーマー | 肌の治療やニキビ改善をうたう美顔器 |
| 作用 | リラックス用のマッサージャー | 血流改善・肩こり治療を目的とする低周波治療器 |
| 広告表現 | 「リフレッシュに最適」 | 「腰痛を治療」「コリを改善」などの治療効果 |
ただし、製品の本来の仕様よりも、広告表現のほうが医療機器認定のトリガーになりやすいことに注意が必要です。
健康雑貨として販売していても「肩こり改善」「ニキビ治療」などと広告すれば医療機器とみなされるリスクがあります。グレーゾーン製品で判断に迷う場合は、各都道府県の薬務課に問い合わせ等すると安全です。
医療機器の広告はどこまで可能?
医療機器の広告は、承認(認証)範囲内の効能効果や性能を正確に伝えることが条件です。それを逸脱した表現や、安全性を断定する表現は薬機法66条で禁止されています。
| 許容される広告 | NG広告 |
| 「血圧を測定できます」 | 「高血圧を改善します」 |
| 「皮膚の汚れを除去します」 | 「ニキビを治療します」 |
| 「歯の表面を研磨します」 | 「虫歯を予防・治療します」 |
| 「視力矯正用コンタクトレンズ」 | 「視力が回復する」 |
(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準)
承認(認証)範囲内での表現を重視する必要があり、承認内容の範囲を超えた治療効果や安全性の断定(例:副作用ゼロ)はNGです。広告全体の印象で判断されるため、単語だけでなく画像・ビフォーアフター・権威付けの有無も注意しましょう。
海外製の医療機器を輸入販売する際の注意点は?
海外で医療機器として販売されている製品を日本に輸入する場合でも、日本国内では改めて薬機法の承認・認証が必要です。
海外の承認(FDA、CEマークなど)があっても、日本国内では効力を持たないため、そのまま販売・広告すると薬機法68条(承認前広告の禁止)違反として行政指導や販売停止処分の対象となる可能性があります。さらに、表示・添付文書では日本語化が義務付けられています。
| 注意ポイント | 詳細 |
| 製造販売業許可の取得 | 輸入販売を行うには、輸入者が製造販売業許可を取得する必要あり |
| 商品の承認・認証 | クラス分類(Ⅰ~Ⅳ)に応じて申請が必要 |
| 表示・添付文書の日本語化 | 承認後の製品表示・添付文書は日本語で整備する義務あり |
| 広告表現 | 日本の承認範囲を超える効能効果を広告すると66条違反 |
(参考:PMDA|医療機器等外国製造業者の登録申請について)
承認取得や広告表現の適正化を早期に進めるには、薬機法に詳しい弁護士とPMDA相談を併用するのが安全です。
まとめ|薬機法を理解して医療機器の安全な運用と広告を目指そう
医療機器を扱う事業では、薬機法の定義やクラス分類、承認制度、広告規制といった複数のルールを正しく理解することが欠かせません。とくに、製品が医療機器に該当するかどうかは目的や作用、広告表現によって判断されます。医療機器とみなされれば、リスクの高さに応じてクラスⅠ〜Ⅳまでに分類され、特定保守管理医療機器に該当する場合には定期点検や安全管理体制の整備が義務付けられます。
こうした仕組みを理解せずに製品を販売・広告すると、未承認広告や虚偽・誇大表現として薬機法第66条や第68条に違反し、行政指導、販売停止、課徴金、さらには企業名の公表によるブランド毀損、最悪の場合刑事事件になるといった深刻な影響を受けるおそれがあります。
また、医療機器の広告は単語単位ではなく、画像や周辺の文脈を含めた全体の印象で判断される点にも注意が必要です。特に新しいタイプの医療機器や輸入製品の販売、SNSキャンペーンなど大規模なプロモーションを行う場合は、薬機法に精通した専門家や弁護士によるレビューを受けることで、後から広告停止や是正命令を受けるリスクを大幅に減らせます。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、医療機器の該非判定サポート、PMDA相談の事前整理、広告やパッケージのリーガルチェック、行政対応や課徴金への対応など、開発から販売・広告までを包括的にサポートしています。自社だけの判断では不安な場合や、新しい分野の製品を市場に投入する際は、早めの段階でお気軽にご相談ください。
医療・美容機器の販売に関するご相談はこちらにまでお寄せください。

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。