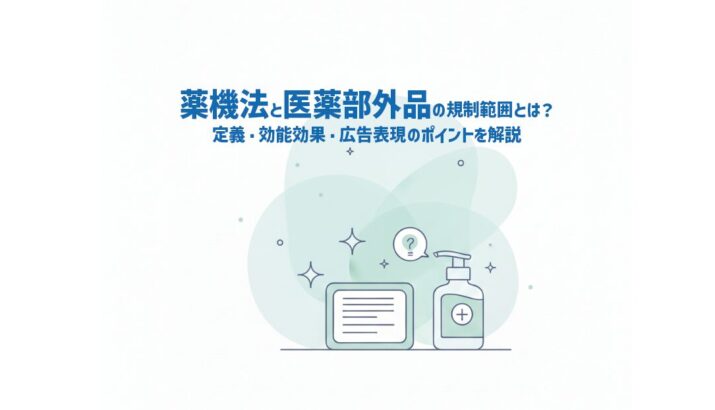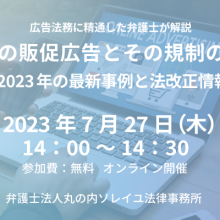「医薬部外品と化粧品の違いがよくわからない…」
「医薬部外品として承認を受けた商品をどう広告すれば違反にならないの?」
化粧品や医薬部外品を扱う広告担当者・ライター・EC事業者の中には、こうした疑問を抱えている方が少なくありません。
薬機法は消費者保護の観点から、医薬部外品の効能効果の表現や広告範囲を厳しく制限しています。しかし「どこまでが化粧品で、どこからが医薬部外品なのか」「医薬部外品なら自由に効能をうたえるのか」という理解が曖昧なまま広告を出稿してしまうと、行政指導や課徴金命令、ブランド毀損のリスクを招く恐れがあります。
この記事では、薬機法における医薬部外品の定義・効能効果の範囲・広告表現のルールをわかりやすく解説します。さらに、表現チェックの実務ポイントや専門家に相談すべきタイミングも紹介するので、広告制作やプロモーションを行う方にとってリスク回避の実践的な指針になります。
薬機法や景表法に精通した弁護士による広告リーガルチェックや表現監修を依頼したい場合は、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所のサービスを活用するのが安心です。広告コピー・パッケージ・Webサイトの表現を専門家が総合的に確認し、違反リスクの早期発見から行政対応までサポートしてもらえます。
薬機法における医薬部外品の定義とは?
医薬部外品は、医薬品と化粧品の中間に位置するカテゴリーで、特定の効能をうたうことができる一方、薬機法によって厳格に規制されています。
たとえば「美白」「シワ改善」「フケ・かゆみ防止」など、消費者の関心が高い効能を広告で訴求できるのが特徴ですが、承認を受けた範囲を超えた表現や医薬品的な効能の標榜は違反とされます。
薬機法は、医薬部外品の広告表現を承認された効能・効果の範囲に限定しています。定義を把握しておけば、化粧品や医薬品との境界を正しく判断し、法的リスクを回避できます。
医薬部外品の法的な位置づけ
薬機法第2条では、医薬部外品を「人体に対する作用が緩和され、医薬品ほど強い作用はないが、特定の効能効果を目的として使用されるもの」と定義しています。
たとえば「美白化粧水」であれば、化粧品なら「肌にうるおいを与える」までしか表現できませんが、医薬部外品なら「メラニンの生成を抑えてシミ・そばかすを防ぐ」と広告できます。
このように、医薬部外品は限定的に効能をうたえる点が最大の特徴です。代表的な製品には、薬用化粧品(美白・抗炎症)、育毛剤、薬用歯磨き、制汗剤などがあります。
医薬品・化粧品と医薬部外品の違い
薬機法上、医薬品・医薬部外品・化粧品はそれぞれ効能範囲や広告可能な表現が異なります。
| 区分 | 定義 | 効能効果の範囲 | 代表例 |
| 医薬品 | 疾病の診断・治療・予防を目的とし、人体に直接作用するもの | 治療・改善まで表現可能 | 処方薬、総合感冒薬 |
| 医薬部外品 | 医薬品より作用が緩やかだが、特定の効能が承認されているもの | 「美白」「育毛」「ニキビ予防」など承認範囲内で表現可能 | 薬用美白化粧品、育毛剤、薬用歯磨き |
| 化粧品 | 清潔・美化・魅力を増すことを目的とするもの | 「うるおいを与える」「清潔にする」など印象表現まで | 保湿クリーム、ファンデーション |
この比較からもわかるように、医薬部外品は「医薬品ほど強い効能は表現できないが、化粧品よりは踏み込んだ訴求が可能」という立ち位置にあります。
指定医薬部外品と薬用化粧品の関係
医薬部外品には「指定医薬部外品」と呼ばれるカテゴリーがあります。これは、もともと医薬品に分類されていた製品のうち、安全性が高いと判断されて医薬部外品に移行したものを指します。
例として、かつては医薬品扱いだった「うがい薬」「口内殺菌薬」「しもやけ・あかぎれ用薬」などが指定医薬部外品に含まれています。
また、広告やパッケージでよく目にする「薬用化粧品」という表現も、実際は医薬部外品の一種です。薬用化粧品には厚生労働省が承認した有効成分が配合されており、「美白」「シワ改善」「肌荒れ防止」といった効能をうたうことができます。
「薬用=医薬部外品」であり、承認された効能を正しく理解したうえで広告表現を行うことが求められます。
薬機法における医薬部外品で表現できる効果効能の範囲
医薬部外品は、厚生労働省が承認した特定の効能効果リスト(承認基準)の範囲であれば広告に表現できます。ただし、承認を超えた断定的な効果(例:完全に治る、必ず効く)は薬機法第66条違反になるため注意が必要です。
ここでは、特に広告で使われやすい「美白」「シワ改善」「ニキビ・抗炎症」「発毛促進」の分野について、どこまで表現できるかを解説します。
美白で表現できる範囲
医薬部外品の美白表現は、基本的に「メラニンの生成を抑える」「しみ・そばかすを防ぐ」という範囲に限定されています。美白有効成分(トラネキサム酸、アルブチン、ビタミンC誘導体など)は「メラニンの生成抑制」の効能が承認されていますが、シミを消す・治療するという表現は一切不可です。
| 表現できるOK例 | NG例(薬機法違反の恐れ) |
| メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ | シミを消す/必ず薄くなる |
| 肌を明るく保つ | 肌の色を白く変える |
| 日焼けによるしみ・そばかすを防ぐ | 肌を漂白する/必ずトーンアップする |
(参考:厚生労働省|医薬部外品の効能効果)
厚生労働省は、美白に関する広告表現について「予防・防止」は認められる一方、「治療・改善」を示唆する表現は禁止しています。(参考:厚生労働省|医薬部外品の効果効能の範囲)この区別を守らない場合、薬機法第66条違反として行政指導の対象となる可能性があります。
また、「美白」という表現が使えるのは、有効成分が厚生労働省に認可された医薬部外品のみです。代表的な美白有効成分には、トラネキサム酸、アルブチン、ビタミンC誘導体、プラセンタエキスなどがあります。これらの成分が含まれていない通常の化粧品では、「美白」という表現自体が薬機法違反になるため注意が必要です。(参考:薬用化粧品(医薬部外品)における美白表現の範囲|広告表現で気をつけるべきポイントとは?)
| 区分 | 定義 | 美白効果の表示 | 承認プロセス |
| 医薬部外品 | 医薬品と化粧品の中間。厚生労働省が有効成分と効能を個別に承認 | 可能(「メラニンの生成を抑えて、シミ・そばかすを防ぐ」など) | 有効成分・効能効果を厚生労働省に申請し承認を得る |
| 化粧品 | 皮膚・毛髪などを清潔・美化・保護するもの | 原則不可(「美白」「シミ予防」など医薬的な効能はNG) | 成分の安全性通知のみ。効能効果の個別審査なし |
関連記事:薬機法と化粧品の広告規制とは?正しい表現ルールをわかりやすく解説
シワ改善で表現できる範囲
シワ改善は、2017年に「ニールワン」や「純粋レチノール」などが承認されたことで、医薬部外品でもシワ改善効果を広告できるようになりました。ただし表現には制約があり、「シワを改善する」までが限界で、「完全に消す・若返る」などはNGです。
| 表現できるOK例 | NG例(薬機法違反の恐れ) |
| シワを改善する | シワが完全になくなる |
| 肌のハリを与える | 若返る/年齢を巻き戻す |
| 表皮のシワを改善 | 老化を止める |
厚労省の承認条件では、「表皮の真皮レベルまで働く」「長期間の使用でシワの溝を改善」など、科学的根拠に基づく表現のみが許されています。「即効で消える」「老化防止」などは過大広告とみなされるリスクが高いため、使用を避けるべきです。
ニキビ・抗炎症・殺菌で表現できる範囲
ニキビや肌荒れ、抗炎症系の医薬部外品は、肌トラブルを「防ぐ」または「改善をサポートする」といった、治療を表さない範囲でのみ表現可能です。
| 表現できるOK例 | NG例(薬機法違反の恐れ) |
| ニキビ・肌荒れを防ぐ | ニキビを治す/必ず治る |
| 肌をすこやかに保つ | 炎症を完治させる |
| 殺菌・抗炎症成分配合 | 完全に菌を死滅させる |
抗炎症・殺菌効果は、厚生労働省が承認した成分(イソプロピルメチルフェノール、グリチルリチン酸ジカリウムなど)を含む場合のみ広告で表現可能ですが、作用機序が効能効果として受け取られないよう表現方法には注意が必要です。(参考:医薬部外品原料規格 2021)
しかし、「治す」「治療」など医薬品的な表現は不可で、あくまで予防・軽減を目的とした記述にとどめる必要があります。SNSや口コミサイトも注意が必要で、「この化粧水でニキビが治った」というユーザーの声をそのまま広告に掲載すると、広告主責任で薬機法違反に問われるリスクがあります。
発毛促進・育毛で表現できる範囲
医薬部外品の育毛剤では、厚生労働省が承認した成分(例:センブリエキス、グリチルリチン酸ジカリウム、D-パントテニルアルコール、ニコチン酸アミドなど)を配合していれば、「発毛促進」「育毛」「脱毛の予防」「毛生促進」「養毛」「薄毛の進行を防ぐ」といった表現が認められています。
(参考:厚生労働省|医薬部外品の効能効果の範囲)
一方で、AGA(男性型脱毛症)の治療や発毛効果を断定する表現は医薬品の領域となり、医薬部外品でうたうと薬機法第66条違反のリスクが高まります。
| 表現できるOK例 | NG例(薬機法違反の恐れ) |
| 発毛促進・育毛をサポート | 絶対に髪が生える |
| 脱毛の予防 | 脱毛症を治療する |
| 毛髪をすこやかに保つ | はげが治る/完全回復する |
育毛・発毛促進の広告は、「予防・促進の範囲にとどめ、治療・改善の断定を避ける」ことが鉄則です。
特にAGAというキーワードを使う場合は、「治療」や「改善」を想起させる文言は医薬品の広告規制に触れるリスクが非常に高いため、慎重な表現が求められます。
実務で特に注意すべきポイント
「薬用=医薬部外品」だが効能範囲外の表現はNG
医薬部外品であっても、承認を受けた効能(例:メラニンの生成抑制)以外の効果を暗示すれば違反。たとえば美白医薬部外品でも「肌の赤みを抑える」「シミを消す」などはアウトです。
「安全性」や「即効性」の表現は特に監視が厳しい
消費者庁や厚生労働省は、薬機法に基づき「100%安全」「副作用がない」「即効で効く」といった断定表現を重点的に監視しています。これらは科学的根拠のない効能保証とされ、行政指導や課徴金命令につながるケースが多いため、特に注意が必要です。
画像やデザインの印象でもNG判定されることがある
「シミが消える」などの言葉を使っていなくても、ビフォーアフター写真や医師の白衣、医療現場の写真を組み合わせると治療効果を暗示すると判断される場合があります(厚生労働省広告ガイドライン)。
薬機法違反が発覚した場合のリスク
薬機法違反が発覚した場合、厚生労働省や都道府県から行政指導・業務停止命令が出されることがあります。その他にも、景表法の規制対象となり、過去には「美白効果でシミが消える」と誤認させる広告を行った企業に対し、課徴金納付命令が科された事例があります(参考:消費者庁|景品表示法関連報道発表資料)。NG表現は単なる注意事項ではなく、経営リスクに直結するため実務での管理が不可欠です。
SNSやインフルエンサー投稿も対象
自社公式SNSはもちろん、依頼したインフルエンサーの投稿も薬機法の広告とみなされます。実際に厚労省は、「消費者が購入判断をする媒体は問わない」と明示しており、SNSでも広告規制の対象になります。
医薬部外品の広告では、「承認された効能効果の範囲を超えない」「医学的に断定しない」「安全・即効の保証を避ける」のが鉄則です。
特にSNSやLPなど多様な媒体で広告を展開する現場では、画像や権威付け表現まで含めて総合的にチェックする必要があります。迷った場合は内部チェックリストだけでなく、弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所のような専門家に広告監修を依頼することで、リスクを最小化できます。
医薬部外品を販売する際の薬機法のポイント
医薬部外品は、医薬品と化粧品の中間に位置する製品カテゴリであり、販売や広告の際には薬機法による規制を理解しておく必要があります。特に、表示義務や成分の取り扱い、パッケージ変更時の要件、承認・届出制度は実務で見落とされやすいポイントです。ここでは、医薬部外品を安全かつ適法に販売するために押さえるべき基本事項をまとめます。
1.表示必須項目に注意する
医薬部外品を販売する際、パッケージや容器に記載しなければならない項目が薬機法で定められています。厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」や関連通知では、以下のような表示が義務付けられています。
- 製品名(販売名)
- 有効成分の名称とその分量
- 効能・効果(承認された範囲内)
- 使用方法および使用上の注意
- 製造販売業者の名称・住所
- 製造番号または製造記号
これらが欠落していたり、承認された効能効果と異なる表現が記載されていたりする場合は、薬機法違反となる可能性があります。特にECサイトの商品ページでは、パッケージと同等の情報を記載する必要がある点が見落とされやすいので注意が必要です。
2.成分表示の考え方を知っておく
医薬部外品では、有効成分とその他成分を分けて表示することが求められます。特に注意すべきポイントは次の通りです。
- 有効成分は承認書に記載されている名称・含有量を正確に表示する
承認書と異なる表記や略称の使用は、薬機法違反になる可能性があります。 - 配合目的を誤って記載しない
例:グリチルリチン酸ジカリウムを「保湿成分」として記載するのは誤解を招くためNG。抗炎症成分であることを明示する必要があります。 - 化粧品と異なり全成分表示は義務ではない
ただし、消費者の安全性を考慮して任意で表示するケースも増えています。
(参考:JCIA|医薬部外品の成分表示の趣旨説明)
成分表示の正確さは、薬機法上のコンプライアンスだけでなく、消費者からの信頼確保にも直結します。
3.詰め替え製品の表示要件をチェック
詰め替え用製品を販売する際には、容器やパッケージを簡略化できるわけではない点に注意が必要です。厚労省の通知では、詰め替え用であっても以下の情報は記載する義務があります。
- 製品名・販売名
- 有効成分
- 効能・効果
- 使用方法・注意事項
- 製造販売業者名
また、元のパッケージと異なるデザインにした場合、承認内容との整合性を保つ必要があります。変更の度合いによっては、再度の申請や変更届が必要になる場合があるため、デザインを刷新する際は薬事担当者や弁護士に確認するのが安全です。
(参考:厚生労働省|医薬部外品の承認・届出制度)
4.承認・届出の基本を知る
医薬部外品は、化粧品よりも強い作用を持つ有効成分を配合していることが多く、誤った使用や成分の不具合が健康被害につながる可能性があります。
そのため、厚生労働省が事前に有効成分・効能・用法を確認し、安全性・有効性を担保する仕組みが届出・承認制度です。
届出をせずに販売すると、薬機法第55条違反となり業務停止命令・製品回収・罰金刑(最大100万円)などの行政処分・刑事罰が科される可能性があります。(参考:厚生労働省|医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
実務上の注意点
- 新規有効成分を含む場合や新しい効能・効果を訴求する場合は「承認申請」が必要
- 既承認成分を用いた一般的な医薬部外品は「製造販売届出」で対応可能
- パッケージ変更や効能表記の修正でも、内容によっては変更届や承認申請が必要になることがある
特に、D2CブランドやEC事業者は、スピード重視で届出を省略しがちですが、後から行政指導や販売停止命令が出るリスクが非常に高いため、必ず確認する必要があります。
医薬部外品の薬機法チェックを進める方法
医薬部外品は「美白」「シワ改善」などの効能をうたえる一方、広告表現の規制が非常に細かく定められています。
承認された効能の範囲を超えた表現や、あいまいなコピーが違反と判断されるリスクがあり、社内の自己点検と専門家によるリーガルチェックを組み合わせることが重要です。ここでは実務で実践しやすい3つのステップを解説します。
1.社内ガイドライン/チェックリストを整備する
最初の一歩は、社内向けの薬機法ガイドラインとチェックリストを作ることです。社内体制を整えることによりライター・デザイナー・広告担当者が初稿の段階でリスクを自己点検でき、弁護士などへの最終相談前に手戻りを減らせます。
チェックリスト例(医薬部外品向け)
| チェック項目 | 内容 |
| 効能・効果 | 承認を受けた効能のみを広告に使っているか |
| NG表現 | 「必ず」「100%」「絶対」など保証表現を使っていないか |
| 医薬品的表現 | 「治療」「治す」「治癒」など医薬品領域の言葉を避けているか |
| 根拠 | 効能・効果を裏付ける成分・承認情報が自社で確認できるか |
| ビジュアル | ビフォーアフター画像や過剰なイメージがないか |
| 口コミ | 個人の体験談で治療効果を暗示していないか |
また、ガイドラインには自社製品が承認を受けた効能一覧や使用可能な表現例をまとめておくと、現場の判断がスムーズになります。特にECサイトやSNS運用チームが外注ライターを使う場合、初稿段階でのトラブル回避に役立ちます。
2.表現の言い換え例をテンプレート化する
薬機法チェックで最も迷いやすいのが「NG表現をどう言い換えるか」です。医薬部外品は「美白」「シワ改善」「フケ・かゆみ防止」など限定的な効能を使えるため、それを踏まえた表現テンプレートを用意することが有効です。
| NG表現 | 言い換え例 |
| シミが消える | メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ |
| 肌が若返る | うるおいを与え、肌をすこやかに保つ |
| 絶対安全 | 肌にやさしい成分を配合 |
| 髪が必ず生える | 発毛を促し、抜け毛を防ぐ |
| ニキビを治す | ニキビや肌荒れを防ぐ |
(参考:厚生労働省|医薬部外品の効能・効果の範囲)
例えば、企画会議の段階から「NG表現をこう置き換えられる」という例を共有しておくと、デザインやコピーが手戻りしにくくなります。特にSNS広告やLPはキャッチコピーの自由度が高く、つい「薬機法アウト」な表現になりやすいので、事前にパターン集を作ると効率的です。
関連記事:薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法
3.専門家・弁護士にチェックを依頼する
医薬部外品の広告は、承認された効能を超えない表現かどうかの判断が特に難しく、SNS・LP・パッケージなど複数媒体で一貫性を持たせる必要があります。最終的な法的判断は弁護士の領域です。社内チェックだけではグレーゾーン判断が難しい場面や、新商品発売・大規模キャンペーンの前には、必ず専門家にリーガルレビューを依頼しましょう。
弁護士は広告全体の文言・デザイン・画像を総合的に確認し、薬機法・景表法の両面から違反リスクを判定してくれます。特に「承認範囲内かどうかの判断」「グレー表現のリスク見積もり」「行政指導が入った際の対応策」など、企業内では判断できない部分をサポートしてもらえるのがポイントです。
関連記事:薬機法を弁護士に相談するメリットとは?広告チェックから違反対応のポイントを解説
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、医薬部外品や化粧品の広告に精通した弁護士が広告コピー・パッケージのリーガルチェック、薬機法適合表現の提案、万が一の行政対応支援まで一貫してサポートしています。月額55,000円の顧問契約では、以下のようなサポートが可能です。
- 幅広いリーガルサービス 広告審査、契約書作成、社内セミナーなど、業界特有の課題に対応
- 迅速な相談対応 電話・メール・チャットツール(Zoom・Teams等)で柔軟に対応
- コスト削減 自社で法務部を抱えるよりも、専門知識を低コストで活用可能
- リスクヘッジ トラブル時に即対応できる顧問契約で、企業の安心を確保
(引用:弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所|サービス・料金)
法務部門を持たない中小企業やD2Cブランドでも、専門家レビューを取り入れることで広告停止や課徴金のリスクを大幅に減らせます。
薬機法に関する弁護士へのご相談はこちらまでお寄せください。
医薬部外品と薬機法のよくある質問
承認番号はどこまで載せる?
医薬部外品は、厚生労働省の承認または届出を受けた際に付与される承認番号(例:医薬部外品承認番号◯◯◯)を広告に記載する義務はありません。
ただし、パッケージや添付文書など製品情報を正しく伝える媒体では、表示が推奨される場合があります。特に薬用化粧品などでは、信頼性を高めるために「医薬部外品」「承認番号」を併記する企業が多いことも覚えておきましょう。
消費者庁や厚生労働省が承認番号の表示を強制しているわけではありませんが、誤解を避けるために「医薬部外品」である旨を明記することは実務上メリットがあります。
(参考:厚生労働省|医薬部外品の申請承認について)
「殺菌」「抗菌」「除菌」はどう使い分ける?
医薬部外品で特に混乱しやすいのが、「殺菌」「抗菌」「除菌」の使い分けです。
| 表現 | 意味・薬機法上の扱い | 実務上の注意点 |
| 殺菌 | 微生物を死滅させる作用。医薬部外品で有効成分と効能が承認されている場合のみ使用可 | イソプロピルメチルフェノール・塩化ベンザルコニウムなど承認成分を含む必要がある |
| 抗菌 | 微生物の増殖を抑える作用。医薬部外品以外でも使えるが、医薬品的な効能を連想させる表現はNG | 雑貨・化粧品では「抗菌加工」程度までが限度 |
| 除菌 | 一時的に菌を取り除くこと。雑貨や化粧品でも比較的自由に使える | 持続的・治療的な効果を示唆する表現は避ける |
例えば「抗菌スプレー」と表示できても、「菌を殺す」「感染を防ぐ」といった表現は医薬部外品または医療機器の範囲となり薬機法違反のリスクがあります。
(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準)
実務上でのポイントとしては、広告で「殺菌」「抗菌」をうたう場合は有効成分と効能の承認を確認しましょう。雑貨や化粧品の場合は「抗菌」「除菌」までが安全域です。「殺菌」は基本NGとなります。
医薬部外品でもSNSでの口コミは規制対象になる?
医薬部外品であっても、SNS上の投稿が「広告」とみなされれば薬機法の規制対象になります。
厚生労働省は「広告かどうかは、発信者・内容・対価の有無など総合的に判断される」としています。
- 企業公式アカウントが投稿する内容:明確に広告として扱われ、薬機法の効能範囲を超える表現は違反。
- インフルエンサーに依頼したPR投稿:金銭・商品提供がある場合は広告と見なされる可能性が高い。
- ユーザーの自主的な口コミ:原則広告ではないが、企業が再共有・引用する際は広告と解釈されることがある。
「広告かどうかは単語ではなく全体の印象で判断される」と厚労省は解説しています。たとえば「薬用クリームでシミが消えた」とインフルエンサーが発信した場合、企業が依頼していれば、薬機法違反に問われる可能性があります。
(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項)
まとめ|医薬部外品は薬機法で安全な広告表現を行おう
医薬部外品は、美白・シワ改善・ニキビ予防・殺菌などの効果を広告でうたえる一方、薬機法に基づく承認範囲を超えた表現は違法広告とみなされるリスクがあります。特に「必ず効く」「治療できる」といった医薬品的な表現や、インフルエンサー・SNS投稿での不適切な宣伝は、広告停止・課徴金・企業名の公表といった大きなダメージにつながりかねません。
安全に広告を行うためには
- 社内ガイドラインやチェックリストを整備し、初稿段階から自己点検する
- 承認された効能の範囲を超えないよう、言い換えパターンをマニュアル化する
- グレーゾーンは弁護士にレビューを依頼し、薬機法・景表法の両面から確認する
という3段階の体制を構築することが重要です。
特に新商品のローンチやSNSを活用したプロモーションを計画している場合は、社内チェックだけでは判断が難しいグレーゾーンが多く存在します。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所 では、薬機法・景表法に精通した弁護士が広告コピー・パッケージ・SNS施策のリーガルチェックから、行政対応・再発防止策の提案まで一貫してサポートしています。
自社ブランドを守りながら、安心して魅力的な広告を打ち出すためにも、早い段階から専門家をパートナーにすることが、薬機法対応の最も有効なリスクマネジメントです。

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。