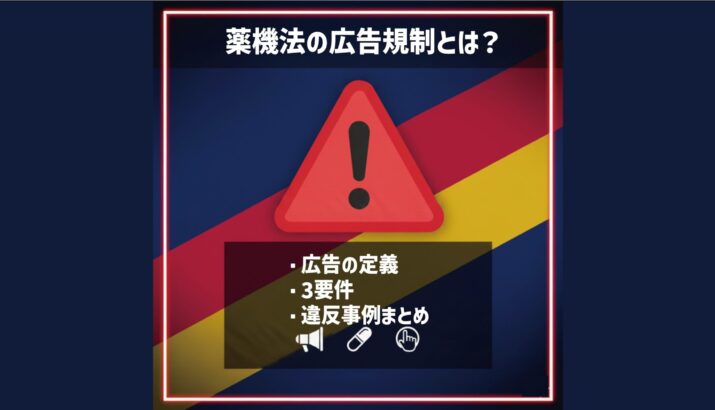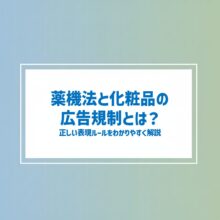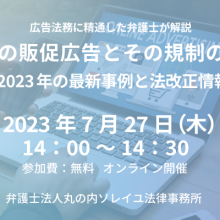「薬機法の広告ってSNS投稿やインフルエンサーの紹介も規制されるの?」
「広告表現では実際どんな表現がNGなのか分からない…」
広告担当者やマーケティング担当者の中には、こうした疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか? 薬機法は消費者保護の観点から広告表現を厳しく規制しており、曖昧な理解のまま運用を続けると、行政処分や課徴金といったリスクを招く恐れがあります。
この記事では、薬機法における広告規制の基本から、広告の定義・規制される製品の範囲・違反事例までをわかりやすく解説します。さらに、適法な広告を作成するためのチェックポイントや弁護士に相談するメリットもご紹介します。
この記事を読むことで、「自社の広告がどこまで薬機法の対象になるのか」「どんな表現がNGで、どう言い換えればいいのか」が明確になり、日々の広告運用に安心して取り組めるようになります。
薬機法に関する広告表現のチェックや修正は、専門知識を有する 弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所にご相談ください。実際の事例をもとにした具体的なアドバイスで、貴社の広告運用をサポートします。
薬機法と広告規制の基本
医薬品や化粧品、医療機器、健康食品などを扱う事業では、広告表現の適正化が法律上の最重要ポイントです。薬機法は、これらの製品の安全性を守り、消費者が誤解や不当な広告によって健康被害や経済的損失を受けることを防ぐために制定されています。
一見、医療機器や医薬品だけが対象と思われがちですが、化粧品・医薬部外品・健康食品・サプリメントなども広告規制の対象となります。さらに食品や雑貨のように薬機法の直接対象外の製品であっても、「疲労回復」「肩こり改善」「免疫力アップ」といった医薬品的な効能を示す表現をした瞬間に薬機法違反とみなされる可能性があります。
まずは薬機法が広告をどのように規制しているのか、その基本的な考え方と対象となる製品の範囲を整理します。
薬機法とは?広告が規制される理由
薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器などの安全性を確保し、消費者を保護するための法律です。
特に広告については、消費者が虚偽や誇大な情報に惑わされて健康被害を受けることを防ぐ目的で、第66条(虚偽・誇大広告の禁止)を中心に規制が定められています。
なぜ広告が厳しく規制されるのかというと、商品を購入する際に、多くの人が広告を判断基準にするからです。もし「シミが完全に消える」「糖尿病が治る」といった表現が野放しになれば、消費者は誤認して商品を選び、結果的に健康被害や経済的被害を受ける可能性があります。そのため、薬機法では広告表現を細かく制限しています。
(参考:厚生労働省|医薬品等の広告規制について)
規制対象となる製品
薬機法で広告規制の対象となるのは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器の4つです。たとえば薬用化粧品や育毛剤、美顔器やコンタクトレンズなどはすべて規制下にあり、効能効果の表現が細かく定められています。
基本の対象
- 医薬品:処方薬・OTC医薬品(市販薬)
- 医薬部外品:薬用化粧品、育毛剤、制汗剤、薬用歯磨きなど
- 化粧品:スキンケア・ヘアケア・メイクアップ製品
- 医療機器:コンタクトレンズ、補聴器、家庭用脱毛器、美顔器など
一方で食品や雑貨は薬機法の対象外ですが、「疲労回復」「肩こり改善」など医薬品的な効能をうたった瞬間に規制の対象となります。特に健康食品やサプリメントは、食品でありながら実務では最も厳しく監視される分野で、ダイエットや免疫関連の表現は違反リスクが高い領域です。
つまり、薬機法の規制対象かどうかは製品カテゴリだけでなく、広告で「医薬品的効能」を示していないかどうかで判断されます。食品や雑貨であっても、誤解を招く表現をすれば薬機法違反に問われる可能性があります。
なお、薬機法の広告規制は媒体を問わず適用される点にも注意が必要です。テレビCMや新聞広告だけでなく、自社運営のWebサイトやLP(ランディングページ)、通販サイト、SNSアカウントの投稿、さらにはインフルエンサーによるPR投稿もすべて規制の対象となります。
(参考:厚生労働省|医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について)
薬機法における広告の定義(広告3要件)
薬機法における「広告」とは、単にテレビCMや新聞広告だけでなく、LP、SNS投稿、ブログ記事、チラシ、店頭ポップなど幅広い媒体が対象となります。厚生労働省が示す「広告3要件」に当てはまる場合、薬機法の規制対象です。
“広告の該当性
1 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。
2 特定の商品名が明らかにされていること。
3 一般人が認知できる状態であること。
以上3点全てを満たすと広告とみなされる。(引用:東京都保健医療局|医薬品等適正広告基準について)
広告の定義(広告3要件)
| 要件 | 概要 | 広告とみなされる例 | 広告とみなされない例 |
| 顧客を誘引する意図 | 消費者を購買に導く意図があるか | 「この化粧水で肌が若返る!」/記事末尾に購入リンク付き解説記事 | 学術論文・社内教育資料 |
| 特定の商品名の提示 | 商品やブランドを特定しているか | 「当社のビタミンサプリ◯◯」/商品画像やパッケージ掲載 | 「ビタミンCは美容に良い」といった一般論 |
| 一般人が認知可能 | 不特定多数が閲覧できる状態か | SNS投稿/YouTube動画/店頭ポップ/Web広告 | 社内メール |
広告にあたる3要件を満たした場合、たとえ「ブログ記事」「口コミ風のSNS投稿」であっても薬機法上は広告と判断されます。つまり「自社が広告として出したつもりはない」という言い訳は通用しないため、注意が必要です。
要件① 顧客を誘引する意図があること
薬機法で広告とみなされるためには、まず「商品購入や利用を促す意図」があることが前提です。
たとえば「この化粧水で肌が若返る!」といった直接的な訴求は典型的な広告ですが、一見中立的に見える「美容成分の豆知識記事」も、記事末尾に販売ページへのリンクがあれば誘引意図ありと判断されます。
一方で、社内教育資料や学会発表用のスライドなど「販売に直結しない」ものは広告には該当しません。つまり、コンテンツの形式ではなく「最終的に消費者を購買に導く目的があるかどうか」が判断基準となります。
要件② 特定の商品名が示されていること
広告とされるもう一つの要件は、商品やブランドが具体的に特定されているかどうかです。 「ビタミンCは美容に良いとされます」といった一般論であれば広告ではありませんが、「当社のビタミンサプリ◯◯」と記載すれば広告にあたります。
意外と見落とされやすいのが、商品画像やパッケージの掲載です。文章で商品名を出さなくても、画像を載せることで「特定の商品が示された」と解釈されるケースがあります。つまり「商品名を出さなければセーフ」とは限らず、実質的に何を宣伝しているのかがポイントです。
また、厚生労働省の「医薬品等の広告規制に関する検討会資料」でも、製品名・販売名・ブランド名のいずれかが提示されれば、広告としての「特定性」が満たされると説明されています。
たとえ文章内に正式な製品名を記載していなくても、「ブランドロゴだけを掲載」「パッケージ画像を掲載」といった方法でも、消費者が特定の商品を連想できる場合は広告と判断される可能性があります。あらゆる要素が特定性の判断材料になる点を理解しておくことが重要です。
要件③ 一般人が認知できる状態にあること
広告とみなされる最後の要件は、それが「不特定多数の人に認知可能な状態かどうか」です。
たとえば、社内メールは広告には該当しません。
SNSやYouTubeのような個人発信も例外ではなく、アフィリエイトリンクや販売誘導を含む投稿は「個人の体験談」ではなく広告と見なされます。重要なのは、誰が発信したかではなく「一般消費者がアクセスできるか」という点です。つまり、公開範囲と到達可能性が広告判断に直結します。
薬機法の広告規制となる内容
薬機法では、消費者を誤認させる広告を防止するために広告規制が細かく定められています。特に第66条〜68条は広告実務に直結する重要な条文です。
- 第66条:虚偽・誇大広告の禁止
- 第67条:特定疾病用医薬品の広告制限
- 第68条:承認前医薬品の広告禁止
以下でそれぞれの内容と具体例を見ていきましょう。
第66条:虚偽・誇大広告の禁止
第66条では、製品の効能や性能について事実と異なる、または誇大な広告を禁止しています。例えば「数日でシミが消える」「誰でも痩せる」といった表現は典型的な違反です。
さらに、医師や薬剤師など専門家が保証しているかのような誤認を与える広告として、「医師が推奨」「産婦人科医監修」といった表現はNGとなります。さらにはわいせつな表現や堕胎を暗示する表現までも幅広く規制対象に含まれ、性的な興奮を過度に誘発する写真やイラストや、妊娠中絶を連想させるコピーや画像なども規制対象です。
定義(薬機法第66条)
医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器について、虚偽または誇大な内容を広告・記述・流布することを禁止。また、承認を受けていない効能効果について標榜することも禁止。
意味
・「誰でも必ず痩せる」「シミが3日で消える」といった誇張や虚偽の広告はNG。
・効能効果について事実であっても、承認されていない表現なら違反。
実際に、株式会社Libeiroの「エゴイプセビライズ」や株式会社シズカニューヨークの「シズカゲル」に関して、アフィリエイト広告で「シミが数日で確実に消える」と表示していたことが問題視され、消費者庁から措置命令を受けました(参考:消費者庁|エゴイプセ・シズカゲルに関する措置命令)。
誇大広告は「アフィリエイト広告」「体験談」「画像表現」など、複数要素の組み合わせでも規制対象となる点に注意が必要です。
第68条:承認前医薬品の広告禁止
第68条では、まだ厚労省の承認を受けていない医薬品や医療機器について広告を出すことを禁止しています。 「開発中の薬でがんが治る見込み」「試験中の新成分で効果が実証済み」といった表現はNGです。
定義(薬機法第68条)
厚生労働大臣の承認・認証を受けていない医薬品や医療機器を広告することを禁止。
意味
・臨床試験中、研究段階の薬やデバイスを広告することはNG。
・未承認の製品は安全性・有効性が確認されていないため、広告により消費者に誤認を与えるのを防ぐ。
2021年8月には薬機法改正で課徴金制度が導入され、虚偽・誇大広告を行った事業者には対象商品の売上の4.5%が課徴金として命じられるようになりました。(参考:課徴金制度について)
承認を得ていない段階で広告を行えば、売上の数%がそのまま罰金として課される可能性があり、企業の経営に直結する大きなリスクになります。
関連記事:広告規制とは?主要法律やよくある違反例・必要な措置・罰則を弁護士が解説
薬機法を補完するガイドライン「医薬品等適正広告基準」とは?
薬機法そのものは「虚偽・誇大広告は禁止」といった抽象的なルールしか示していません。そこで厚生労働省は、薬機法を補完する形で 「医薬品等適正広告基準」 というガイドラインを定め、広告表現の判断基準を具体的に示しています。
例えば薬機法の条文だけでは「どの表現が誇大に当たるのか?」が分かりづらいですが、適正広告基準では「必ず治る」「誰でも痩せる」「シミが消える」といった具体的なNGワードが列挙されています。つまり、広告制作の現場では、この基準をチェックリスト的に利用することで、違反リスクを未然に防げるのです。
この基準は法的拘束力を持つ「法律」そのものではありませんが、行政指導や広告審査の場面では実質的なルールとして機能しており、違反すれば薬機法違反と同様に行政処分の対象になる可能性があります。
制作フローの中でまずこの基準を確認し、疑問点があれば弁護士に相談して薬機法の条文解釈を踏まえた判断を仰ぐ、という二段構えでの運用が推奨されます。こうした使い分けによって、現場レベルのスピード感と法的な正確性の両方を担保することができます。
薬機法における違反広告のNG表現と具体例
薬機法では、消費者に誤認を与える可能性がある広告表現を厳しく規制しています。特に化粧品・健康食品・美容機器などの分野は、効果を強調しようとして「医薬品的効能」や「安全性保証」に踏み込みやすく、違反リスクが高い領域です。ここでは代表的なNG表現と、その理由、さらに適法な言い換え例を紹介します。広告制作時に必ずチェックすべきポイントとして活用してください。
関連記事:薬機法NGワード一覧|使える表現への言い換え例とチェック方法
「治る・改善する」など医薬品的な表現
最も典型的なNG表現は「治る」「改善する」といった医薬品的な効能を示す言葉です。化粧品や健康食品はあくまで「美容や健康の維持」が目的であり、病気や症状を治す効能をうたうことは許されません。例えば「シミが消える」「ニキビが治る」「がんを予防する」といった表現は、消費者に医薬品と誤認させるため薬機法違反になります。
| NG表現例 | 許容される表現例 |
| シミが消える | 皮膚を健やかに保つ |
| ニキビが治る | 肌を清浄にし、ニキビを防ぐ |
| がんを予防する | 健康維持をサポートする |
「安心・安全」「永久」など保証を示す表現
「絶対に安全」「副作用はない」「永久に効果が続く」といった保証表現も薬機法ではNGです。なぜなら、どんな製品であっても副作用やアレルギー反応がゼロであるとは断定できず、誤認を招くからです。さらに「永久脱毛」や「ずっと続く効果」といった表現も永続性を保証するため禁止されています。
| NG表現例 | 許容される表現例 |
| 絶対に安全 | 製造工程で〇〇の安全基準を満たしています |
| 副作用はありません | 使用上の注意を明記し、リスク情報を公開 |
| 永久脱毛 | ムダ毛ケアをサポート |
代替表現としては「成分や製造工程を開示し、一定の安全基準を満たしています」「使用中のムダ毛ケアをサポートします」など、具体的な事実に基づく説明が適切です。
さらに「永久に効果が続く」「100%安全」「絶対に効く」といった保証表現は薬機法第66条の趣旨に反し、使用が禁止されています。日本医療機器産業連合会(JFMDA)の「医療機器適正広告ガイド」でも、これらの表現は消費者に過度な安心感や誤解を与える恐れがあるため回避すべきと明記されています。
特に「絶対」「完全」「永久」といった言葉は、科学的根拠があっても承認内容を超えた印象を与える可能性があるため、広告制作時は慎重に表現を検討する必要があります(参考:日本医療機器産業連合会|医療機器適正広告ガイド(2024年改定版))。
「No.1」「最高」など最大級表現
「No.1」「世界初」「最高」といった最大級表現は、客観的な根拠がない限りNGです。これらの言葉は消費者に「他社より優れている」と誤認させるため、薬機法や景品表示法に違反するリスクがあります。もし使用する場合は、調査機関名・調査年・調査範囲などの根拠を必ず明示する必要があります。
| NG表現例 | 許容される表現例 |
| 世界初 | 〇〇機関調査に基づく新技術を採用 |
| 最高 | 当社従来品比で〇%改善 |
| No.1 | 〇〇調査(2024年/全国〇人対象)で売上1位 |
代替としては「当社従来品比〇%改善」「〇〇調査(2024年/〇〇機関)にて売上1位」といった具体的な裏付けを提示する方法が挙げられます。
医師や専門家による推薦コメントや体験談の禁止
「医師が推奨」「専門家が効果を認めた」といった推薦表現も注意が必要です。薬機法上、化粧品や健康食品においては、権威者の推薦を効果の裏付けとして使うことが禁止されています。また、利用者の体験談を「効果保証」と誤認させる形で掲載するのもNGです。
| NG表現例 | 許容される表現例 |
| 医師推奨 | 医学的知見に基づく一般的な情報を紹介 |
| 専門家が効果を認めた | 成分や研究データを客観的に提示 |
| ユーザー体験談(効果保証のように記載) | 使用感についての体験談にとどめる |
使用前後の写真やビフォーアフター表現
「使用前」と「使用後」の写真を並べるビフォーアフター広告は、効果を断定的に見せるためNGとされています。とくに美容機器や健康食品では「これだけ変わった」と強調する表現が虚偽・誇大広告にあたる可能性が高いです。
| NG表現例 | 許容される表現例 |
| 使用前/使用後の比較写真 | 使用イメージ写真として掲載し、注意書きを明記 |
| Before → After で劇的変化 | 個人差があることを明記したうえで雰囲気を伝える写真 |
一方で「使用イメージ写真」として、効果を保証しない形での活用であれば可能です。その際は「効果には個人差があります」といった注意書きを必ず併記する必要があります。
実際に薬機法違反で摘発された広告の事例はある?
薬機法違反は、最悪の場合に行政処分や逮捕に至るケースもあります。ある事業者は、厚生労働省から承認を受けていない「水」をあたかも医薬品であるかのように販売しました。
“腫瘍やアレルギー、高血圧の予防効果が期待できると称した水を販売したとして、警視庁生活環境課が、令和5年11月30日までに、薬機法違反の疑いで、東京都港区の医療機器販売会社の代表取締役ら4人を逮捕したと発表しました。(引用:腫瘍に効く水を販売したとして薬機法違反で逮捕された件について弁護士が解説)
この事例は、商品そのものが医薬品として承認を受けていない場合、広告で効能効果を示すこと自体が違法になることを示しています。特に「水や食品で病気が治る」といった宣伝は典型的な薬機法違反であり、最悪の場合は刑事罰に発展します。
また、大手製薬会社のロート製薬は、SNSでインフルエンサーを起用したマーケティングを行いました。しかし、実際には広告であるにもかかわらず「広告・PR」であることを明示せず、消費者にあたかも第三者の自然な発信であるかのように誤認させました。(参考:【令和7年3月】ロート製薬にステマ措置命令 ― SNS活用企業が見落としがちな法的リスクとは?)
この行為は、景品表示法および薬機法に基づく「ステルスマーケティング(ステマ)」と判断され、消費者庁から措置命令が下されました。薬機法だけではない関連法全般での「表示の透明性」が強く求められていることを示しています。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法はもちろん、景品表示法や健康増進法など広告に関わる幅広い法規制を一括してチェックしています。実際の対応事例も多数あり、豊富な知識を持つ専門家がリスクを洗い出し、安全な代替表現まで提案してくれます。
「この表現は大丈夫かな?」と迷った段階で相談すれば、広告差し止めや行政処分といった重大リスクを未然に防ぐことができます。
薬機法の広告違反を防ぐためのポイント
薬機法の広告違反は「知らなかった」では済まされず、行政処分やブランド毀損につながります。実際に違反が発覚すると、まずは改善命令や広告差し止めが下され、それでも不十分な場合は業務停止命令や課徴金、最悪は刑事罰(懲役2年以下または200万円以下の罰金)に発展するリスクがあります。
さらに行政処分の内容は公開されるため、報道やSNSで拡散されることで企業の信頼を大きく損ない、販売停止や取引先からの契約解除といった二次的な被害にもつながります。こうしたリスクを避けるためには、以下の3つのポイントを押さえておくことが重要です。
関連記事:薬機法違反とは?事例・罰則・防止策をわかりやすく解説
1.厚生労働省ガイドラインを確認する
広告制作では、厚生労働省が公表している以下の基準を参照することが不可欠です。
これらは法律を補完する「チェックリスト」としての役割を持ち、行政もこの基準をもとに違反の有無を判断しています。つまり、単に法律条文だけでは判断が難しい「グレーゾーン」を具体的に整理してくれる存在です。
たとえば、法律には「誇大広告は禁止」としか書かれていませんが、ガイドラインには「シミが消える」「抜け毛が治る」といったNG例が具体的に列挙されています。そのため、担当者が「これは大丈夫かな?」と迷ったときに参照すれば、行政判断と同じ基準で確認でき、結果として違反リスクを大幅に減らせます。
化粧品会社については、「厚生労働省の通知」の確認も必要になります。
2.社内で広告ガイドラインを整備する
現場任せでは判断がばらつき、リスクが高まります。そのため、企業として共通の基準をまとめた「社内広告ガイドライン」を整備することが重要です。ガイドラインを用意しておけば、誰が広告を作っても一定水準でリスク回避ができ、教育や引き継ぎにも活用できます。
整備すべき内容例
| 項目 | 内容例 | 実務上の効果 |
| NGワードリストの作成 | 「治る」「改善する」「永久」「No.1」「安全」など、薬機法や景表法で禁止・注意が必要な表現を一覧化 | 担当者が一目で判断できるため、誤用の初期段階で防止できる |
| チェック担当者の配置 | 制作部門だけでなく、法務部や品質保証部も関与 | 部署間で責任を分担し、見落としを減らす |
| チェックフローの作成 | 原稿作成 → 法務チェック → 修正 → 最終承認 → 配信 | 一連の流れを標準化することで、配信直前のトラブルを回避 |
| 言い換え表現リスト | 「肌が若返る」→「ハリ・ツヤを与える」など | NG表現を削るだけでなく、広告効果を損なわない形で修正可能 |
| 事例共有 | 過去の行政処分事例や社内での修正履歴を蓄積 | 新人教育や再発防止に役立ち、ナレッジが蓄積する |
このように具体的なルールを整備しておけば、担当者は「表現を考えるたびに不安になる」状態から解放され、制作スピードと安心感が両立できます。さらに、ガイドラインは一度作って終わりではなく、定期的に更新し、最新の行政指導や法改正に対応させることも不可欠です。
3.専門家や弁護士に相談する
薬機法の広告チェックにおいて、最終的なグレーゾーンの線引きを正確に判断できるのは法律の専門家です。担当者や制作会社レベルでは「この表現は大丈夫そう」と思っても、行政の判断基準とは異なるケースが多く見られます。
一方、弁護士に相談すれば、以下のようなサポートが受けられます。
| 項目 | 弁護士に依頼した場合 | 弁護士に依頼しない場合(リスク) |
| リスク評価 | 過去の行政処分事例を参照し、法的観点で「安全/危険」を明確化 | 判断基準が曖昧でNG表現を放置する可能性 |
| グレー表現の対応 | 「治る」→「ハリを与える」など、広告効果を保った言い換え提案 | NG表現を削除するだけで、広告の訴求力が弱まる |
| 行政対応 | 照会・聴聞に対して法的に整合性ある回答を代理提出 | 説明不足や誤解を招く回答で処分が重くなる |
| 再発防止 | ガイドラインや社員研修を整備し、組織的にリスクを回避 | 属人的な判断が続き、同じミスを繰り返す |
| コスト比較 | 広告1本あたりのチェック費用:3〜10万円程度/顧問契約:月5〜10万円 | 違反が発覚した場合:景品表示法に基づき売上の最大3%課徴金+薬機法で2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金の可能性 |
例えば、月商1,000万円規模のECサイトなら、違反が発覚した場合に課徴金に加えて広告停止・回収対応の損害まで発生します。弁護士に広告チェックを依頼しておけば数万円で済むリスク管理が、放置すると数百万円単位の損失に直結するのです。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、広告審査サービスを 1ページ(A4判)11,000円〜で提供しています。実際の審査例も公式サイトで公開されており、薬機法チェックに強みを持っています。違反リスクを最小限に抑えながら、広告効果を維持したい企業にとって、極めてコストパフォーマンスの高いサービスといえるでしょう。
関連記事:薬機法を弁護士に相談するメリットとは?広告チェックから違反対応のポイントを解説
薬機法に関する弁護士へのご相談はこちらまでお寄せください。
薬機法と広告に関するよくある質問
広告規制の違反が見つかったらどんな罰則を受ける?
薬機法違反が発覚した場合、まずは厚生労働省や都道府県からの「改善指導」や「是正命令」が下されることが多いです。しかし、改善対応が不十分であったり悪質であったり判断されれば、業務停止命令や課徴金に発展するリスクがあります。
さらに虚偽・誇大広告にあたるケースでは、薬機法第66条違反として2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科される可能性もあります。
単なる広告表現の一文が、企業にとって大きな損失やブランド毀損に直結する点に注意が必要です。
一般人のSNS投稿も薬機法の広告規制対象になる?
対象になります。販売促進を目的とした投稿は個人アカウントであっても規制対象です。
例えば、インフルエンサーが企業から報酬や商品提供を受けて「このサプリで免疫力がアップしました!」と投稿した場合、それは明確に広告に該当します。
一方で、一般消費者が自発的に感想を書いただけなら規制対象外となることもありますが、企業が「レビューしてください」と依頼していたり、アフィリエイトリンクが含まれていたりする場合は広告扱いになります。
厚生労働省も「SNSや口コミなどインターネット上の表現も広告規制の対象」と明言しており(参考:厚生労働省|医薬品等の広告規制について)、企業側が「個人の投稿だから大丈夫」と油断するのは危険です。
医療用医薬品の広告はなぜ禁止されているの?
薬機法第67条では、医師の処方が必要な医療用医薬品については、原則として一般消費者向けの広告を禁止しています。理由は、医療用医薬品が医師や薬剤師などの専門家による適正な判断と管理を前提としているためです。
もし「この薬でがんが治る」といった広告が許されれば、患者が医師の診察を受けずに誤った自己判断をしてしまい、健康被害につながる危険性があります。そのため広告・宣伝は、医療関係者向けの情報提供に限定することが求められています。
そのため、医療用医薬品は「医師や薬剤師など専門家の指導下でのみ適正に使用されるべき」とされており、広告は厳しく規制されています。違反した場合、広告差し止めや業務停止命令だけでなく、刑事罰に問われるケースがあります。
一方で、学会・専門誌・医療従事者向けのポータルサイトなど、医療関係者のみを対象とする媒体では、一定の条件を満たす範囲で広告が可能です。(参考:厚生労働省|薬事法における広告規制)。
関連記事:薬機法における医薬品とは?定義・販売規制・広告ルールを徹底解説
まとめ|薬機法を理解して安全な広告表現を目指そう
薬機法は、化粧品や健康食品などの広告を制作するうえで絶対に無視できないルールです。「少しくらいなら大丈夫」と思っていても、違反が発覚すれば改善命令や業務停止命令、さらには課徴金や刑事罰といった重い処分に発展するリスクがあります。
この記事で解説したように、広告表現には「治る」「改善する」といった医薬品的効能や、「No.1」「安全」といった誇大・保証表現など、うっかり使ってしまいがちなNGワードが多数存在します。これらを回避し、適法かつ消費者に誠実な広告を作るためには、厚生労働省のガイドラインを参照し、社内チェック体制を整備することが欠かせません。
とはいえ、グレーゾーンの判断や行政対応まで含めると、現場担当者だけでの対応には限界があります。弁護士によるリーガルチェックを組み込むことが、リスクを最小化しながらスピーディーに広告を運用する最も確実な方法です。
弁護士法人丸の内ソレイユ法律事務所では、薬機法をはじめとする広告関連法に精通した弁護士が、広告文案やLP、パッケージ表示まで幅広くチェックを行っています。スポットでの広告審査はもちろん、顧問契約による継続的なサポートも提供しており、行政処分リスクを回避しながら安心して広告運用を行う体制を整えることが可能です。

■監修者プロフィール
弁護士と薬剤師のダブルライセンスを有し、薬機法・景表法・健康増進法・特定商取引法・ステマ規制などヘルスケア領域に関わる法規制に精通。大手調剤薬局企業で企業内弁護士としてM&A、DX推進、新規事業の薬機法対応等に従事してきた経験を基に、法律と医療の双方の専門知識を活かした実務的なアドバイスを提供。その知見を活かし、健康食品・化粧品・美容機器・EC分野における広告表現のリーガルチェック、薬機法対応、関連申請支援、コンプライアンス体制構築まで幅広く担当し、多数のセミナー・講演実績を通じて最新の規制動向も踏まえた支援を行っている。2026年1月より、美容健康部門リーダーに就任。